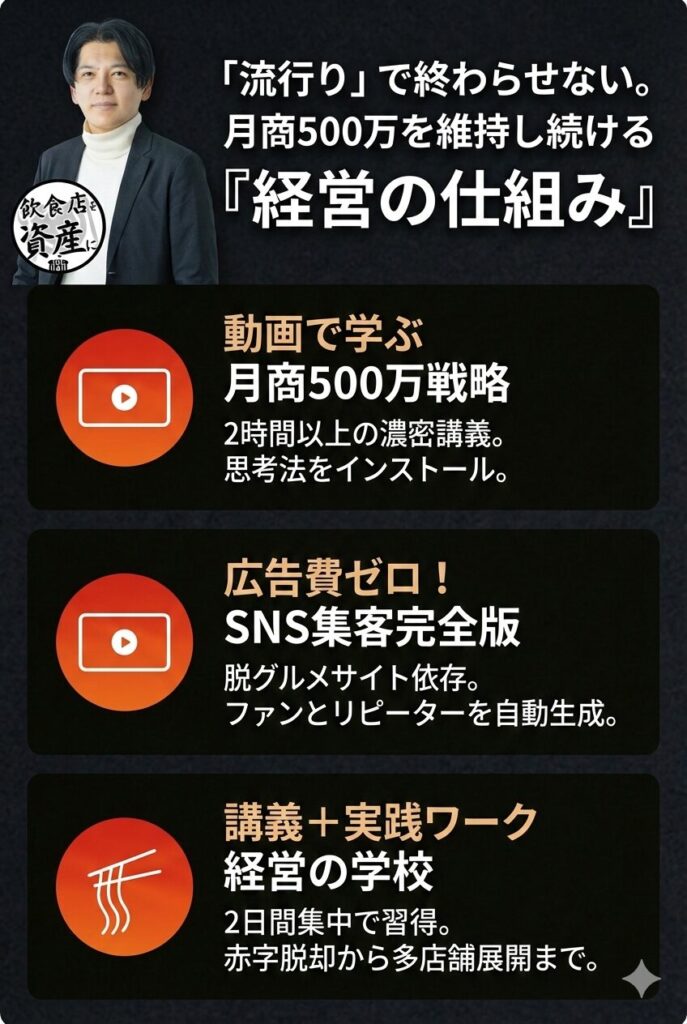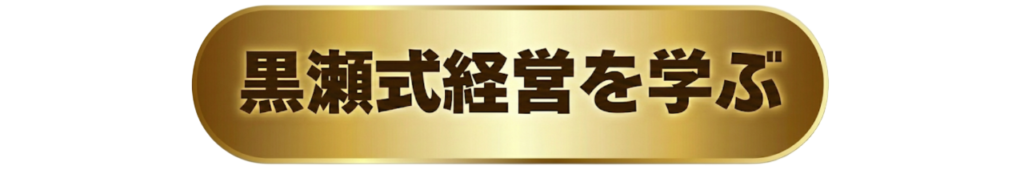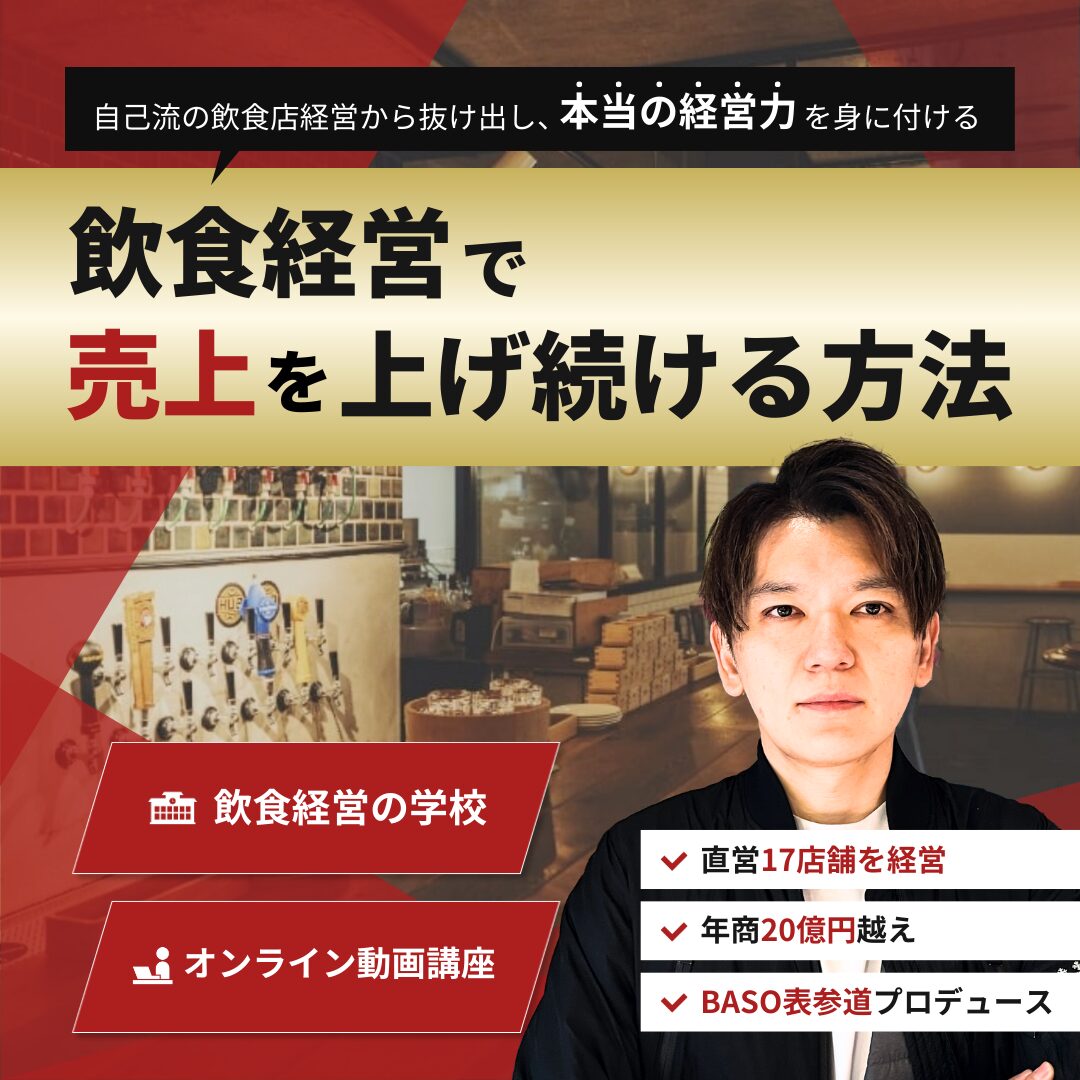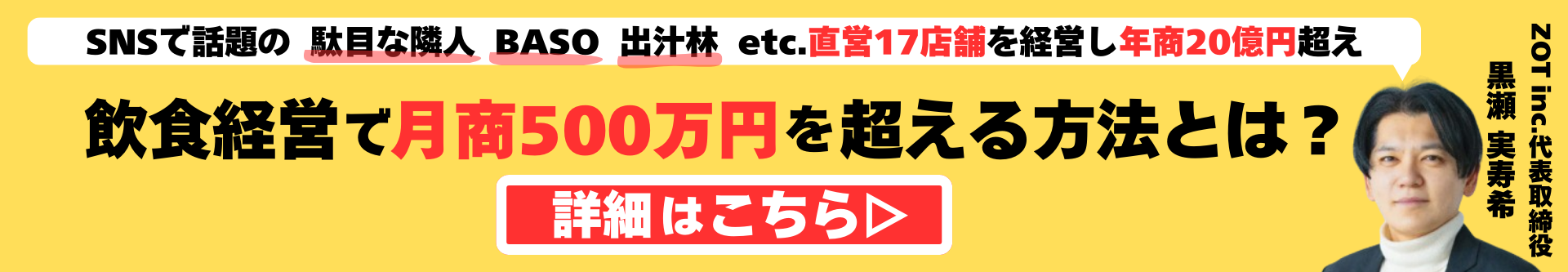【観光地飲食店 必勝戦略】新規顧客を掴み、売上を最大化する集客術
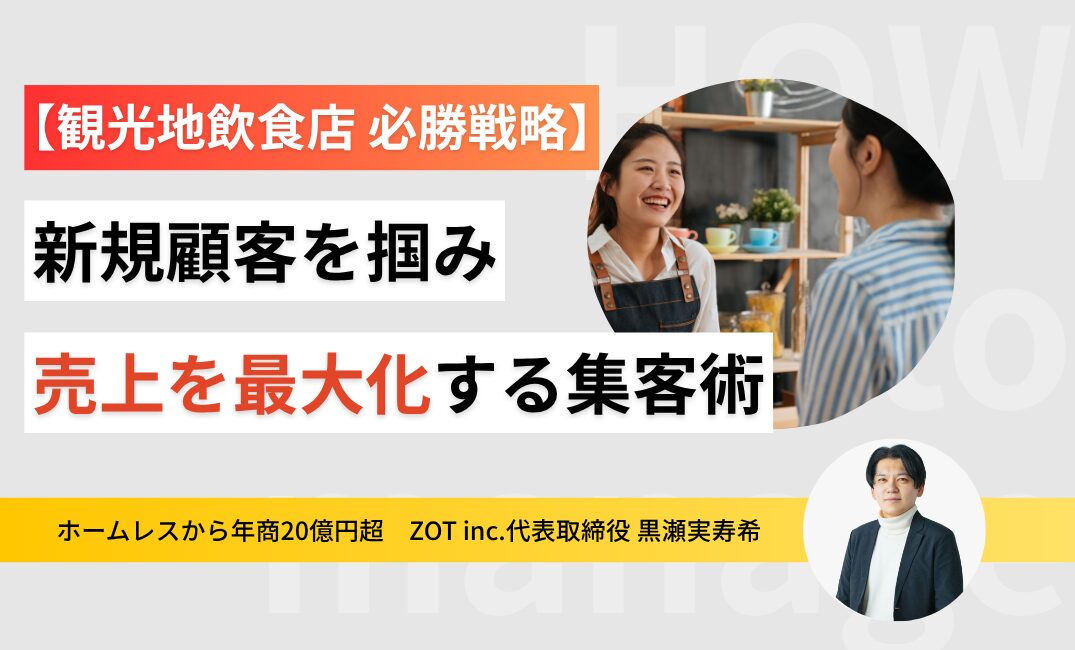
郊外の観光地にある飲食店は、常に多くの観光客で賑わうイメージがあるかもしれません。しかし、実際には都市部とは異なる独自の集客課題を抱えています。
観光客の流動性、情報収集の変化、そして地元住民との関わり方など、これまでの常識が通用しない場面も少なくありません。
本記事では、埼玉県秩父市で創業して100年以上の歴史がある「パリー食堂」の事例も参考にしながら、観光地の飲食店がどのようにして新規顧客を効果的に獲得し、売上を最大化していくべきか、その具体的な戦略を徹底解説します。
本記事のリンクには広告を含んでいます。
秩父の老舗「パリー食堂」とは?その魅力と挑戦

埼玉県秩父市に位置する「パリー食堂」は、1927年(昭和2年)創業という、まもなく100周年を迎える歴史を持つ老舗食堂です。建物自体が登録有形文化財にも指定されており、そのレトロで趣のある外観と内観は、訪れる人々に懐かしさと安らぎを与え、お店の大きな魅力となっています。
現在のオーナーである川邊さんは、30代という若さで4代目として家業を継ぎました。都心から2時間離れた秩父という観光地で、夜間集客の難しさといった地域特有の課題に直面しながらも、伝統の味を守りつつ、現代のニーズに合わせた新たな経営戦略を模索しています。
現在は、月商300万~400万円を安定させることを目標に、日々挑戦を続けている注目の飲食店です。
【観光地での戦い方】観光客の行動心理を捉え、来店に繋げる
観光地の飲食店が成功するためには、観光客特有の行動パターンや情報収集の仕方を深く理解し、それに合わせた戦略を立てることが不可欠です。
観光客の情報収集と意思決定プロセス

現代の観光客は、スマートフォンを片手に旅をします。急に「ランチを食べたい」「休憩できるカフェを探したい」と思った時、多くの人が地図アプリや検索エンジンで「現在地から近くの〇〇」「地名+業種」といったキーワードで情報を探します。この「今すぐ行きたい」というニーズを捉えることが、来店に直結する重要なポイントです。
また、旅行前からSNSやブログなどで事前に情報を収集し、行きたいお店を決めてから訪れる観光客も少なくありません。そのため、ただ存在しているだけでなく、数ある選択肢の中から「選ばれる」ための工夫が求められます。
地域特性を活かした集客と課題への対応
観光地ならではの集客の難しさも存在します。夜間は観光客が日中の観光を終えて宿泊施設に戻るため、飲食店への流入が減少する傾向があります。
これらの課題に対し、自分たちが売りたいものを売る「プロダクトアウト」ではなく、市場にどのような需要があるかを探り、その需要に応える「マーケットイン」の視点が重要です。
例えば、秩父では「ホルモン」が地元の名物として非常に愛されており、地元住民が日常的に消費する文化があります。観光客だけでなく、地元住民の強いニーズが存在することを示しており、地域に根ざした食文化への着目と、新メニュー開発の可能性が生まれます。
このようにマーケットインの視点を持つことで、夜間帯に地域住民に利用してもらえる戦略を立てることができるでしょう。
新規顧客を取りに行くためのSNS戦略
観光地における観光客は、まさに「新規顧客」そのものです。彼らを効果的に呼び込み、さらに満足度を高めて口コミやSNSでのシェアに繋げることが、売上最大化の鍵となります。特にSNSは、視覚的な訴求力が高く、新規顧客獲得に直結する強力なツールです。
視覚で魅了するオンライン情報発信
オンラインでの情報発信は、新規顧客獲得の強力な手段であり、特にSNSは視覚的な魅力でユーザーを惹きつけます。
InstagramやYouTubeなどのSNSを活用し、SNS映えするメニュー写真や店内の雰囲気、季節感を取り入れた投稿(例:桜の時期の特別メニューなど)は、ユーザーの目を引き、来店を促す効果があります。ハッシュタグを効果的に活用することで、検索からの流入も増加させられます。

また、店舗名、住所、電話番号、営業時間などの基本情報を、自社ウェブサイト、SNS、グルメサイトなど、オンライン上のあらゆる場所で完全に一致させ、常に最新の状態に保ちましょう。
これにより、ユーザーは迷うことなく正確な情報を得られます。新メニュー、期間限定キャンペーン、イベント告知など、鮮度の高い情報を積極的に発信し、写真や動画付きの投稿でユーザーの目を引きましょう。
さらに、よくある質問には迅速に回答し、Wi-Fiや駐車場などの店舗属性情報も正確に設定することで、ユーザーの疑問を解消し、来店へのハードルを下げられます。
影響力を活用した集客と信頼構築
デジタルだけでなく、地域に根ざした媒体や影響力のある人物との連携も、新規顧客獲得に繋がります。
観光系のYouTuberやブロガー、Instagramerなどに直接連絡を取り、お店を紹介してもらうことを提案してみましょう。彼らの発信力によって、お店の魅力が動画や記事を通じて広がり、新たな顧客層の獲得に繋がる可能性があります。
顧客からの評価は、新規顧客が「この店に行くべきか?」を判断する上で最も重視する情報の一つです。
良いレビューを増やし、丁寧に返信することで、お店の信頼性は飛躍的に向上し、集客に直結します。店内POPやレジ付近にレビュー投稿を促すQRコード付きPOPを設置したり、会計時や退店時にスタッフが声かけをしたりすることが有効です。(ただし、レビューの見返りに割引や特典を与えることは、プラットフォームのポリシー違反となる可能性があるため避けましょう。)
良いレビューには感謝を込めて具体的な内容に触れてお礼を伝え、低評価・ネガティブなレビューには誠実かつ迅速に対応することが重要です。
また、地方では地元の雑誌やフリーペーパー、観光客が情報収集に使う地域のまとめサイトなどが依然として読まれています。「秩父に行くなら〇〇選」といった記事に掲載を依頼することも、ターゲット層への効果的なアプローチとなります。
店内POPや名刺、チラシにオンラインレビューページやSNSへのQRコードを設置するなど、オフラインでの接点からオンラインへの誘導を促しましょう。
最終的に最も重要なのは、お客様に「また来たい」「誰かに教えたい」と感じさせる質の高い料理とサービスを提供することです。良い体験は、自然と良いレビューにつながり、それがオンラインでの評価を高め、さらなる集客を生む好循環を生み出します。
メニューの適正化:顧客満足度と利益率を両立させる具体策
顧客に「美味しい」「また来たい」と思わせるメニューは、集客の根幹です。同時に、原価やオペレーションを考慮した適正化は、利益率を向上させ、経営を安定させる上で不可欠です。
顧客を惹きつけるメニュー開発と「見た目」戦略
視覚的な魅力は、特にSNS時代において、集客に直結します。写真映えするメニューの開発や提供しているメニューが最も魅力的に見える高画質な写真を撮影し、オンライン上で積極的に活用しましょう。

例えば、丼ぶりから具材がはみ出すようなビジュアルは、写真映えしやすく、ユーザーの興味を強く引きます。また、創業当初からのレトロな内装にマッチしたメニューの写真を掲載することで、お店の雰囲気に合ったブランディングを強化し、SNSでの拡散を促します。
また、メニュー開発においては、「マーケットイン」思考も重要ですし、地域に根ざした食文化(例:秩父のホルモン文化)に着目し、地元のニーズに応える新メニューを開発する視点を取り入れましょう。
原価・ボリューム・オペレーションの最適化
顧客満足度を維持しつつ、利益率を高めるための具体的な原価管理とボリューム調整、そして効率的なオペレーションは重要です。
- 原価の最適化:食材の仕入れルートの見直し、ポーション(一人前の量)の適正化、廃棄ロスの削減などにより、原価を抑える工夫をしましょう。例えば、特定の食材のカット方法や提供量を工夫することで、品質を保ちつつコストを削減できます
- ボリュームの戦略的調整:顧客ニーズに合わせて、ミニサイズやハーフサイズ、あるいは大盛り無料といったオプションを戦略的に提供しましょう。大盛りを希望する顧客は全体の一部であるため、基本のボリュームを適正化することで、全体の原価削減に繋がり、同時に多様なニーズに応えることができます
- オペレーションの効率化:調理プロセスの見直し、仕込みの工夫、注文から提供までの動線改善などにより、スタッフの負担を減らし、少ない人数でも店舗が回る仕組みを構築しましょう。例えば、顧客自身が一部の調理に参加するスタイル(例:卓上調理)や、セルフサービスを導入することも、効率化に繋がります。また、季節限定メニューなど、常に新しい魅力を提供することで、顧客の興味を引きつけ、リピートや新規来店を促します
まとめ:観光地の飲食店が持続的に繁盛するための3つの柱

観光地の飲食店が成功するためには、「観光客の行動心理を捉えた集客戦略」「新規顧客を効果的に獲得し、リピーターにも繋げるSNS戦略」、そして「顧客満足度と利益率を両立させるメニューの適正化」という3つの柱が不可欠です。
パリー食堂の事例が示すように、地域特性を深く理解し、デジタルツールとオフライン施策を組み合わせ、常に顧客のニーズに応える柔軟なメニュー開発を行うこと。そして何よりも、質の高い料理とサービスを提供し続ける「現場主義」の姿勢が、老舗を再生させ、未来へと繋ぐ鍵となります。
変化を恐れず、これらの戦略を実践することで、あなたの飲食店も観光地で輝き続ける繁盛店となるでしょう。
観光地の飲食店における顧客獲得戦略について、より深く学ぶことができる環境も提供しています。ご興味がある方はぜひ公式LINEの登録をお願いします。