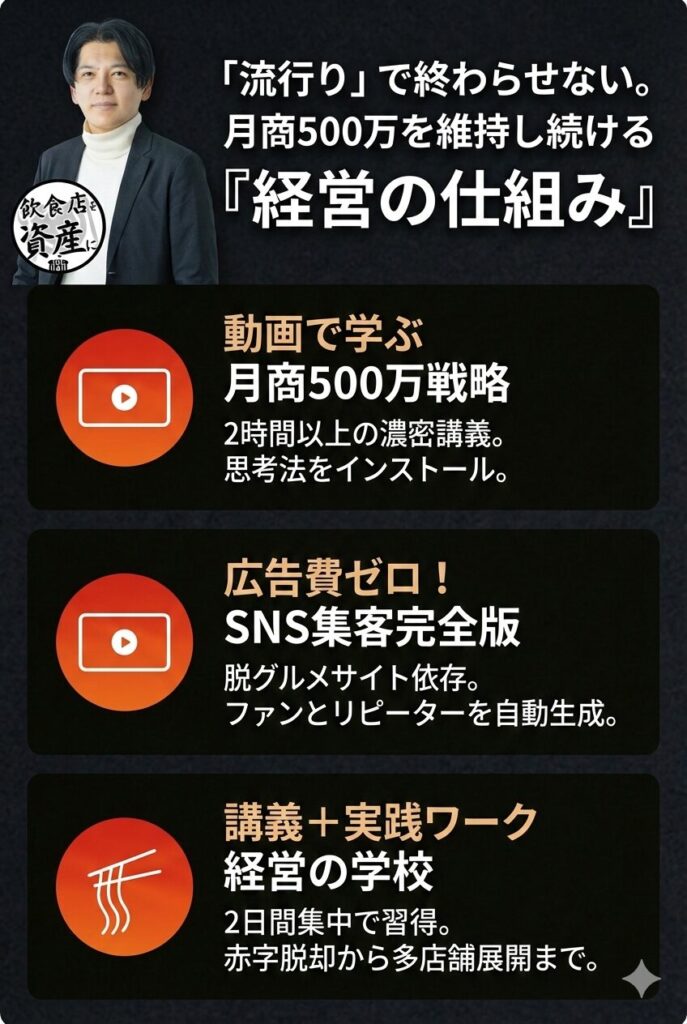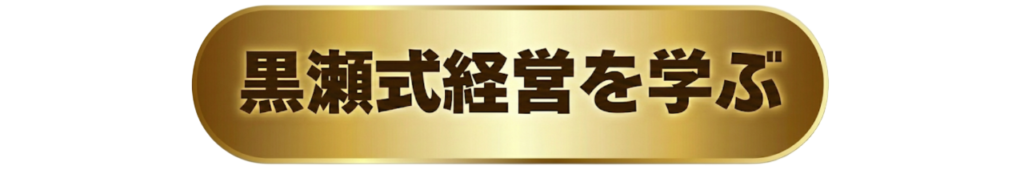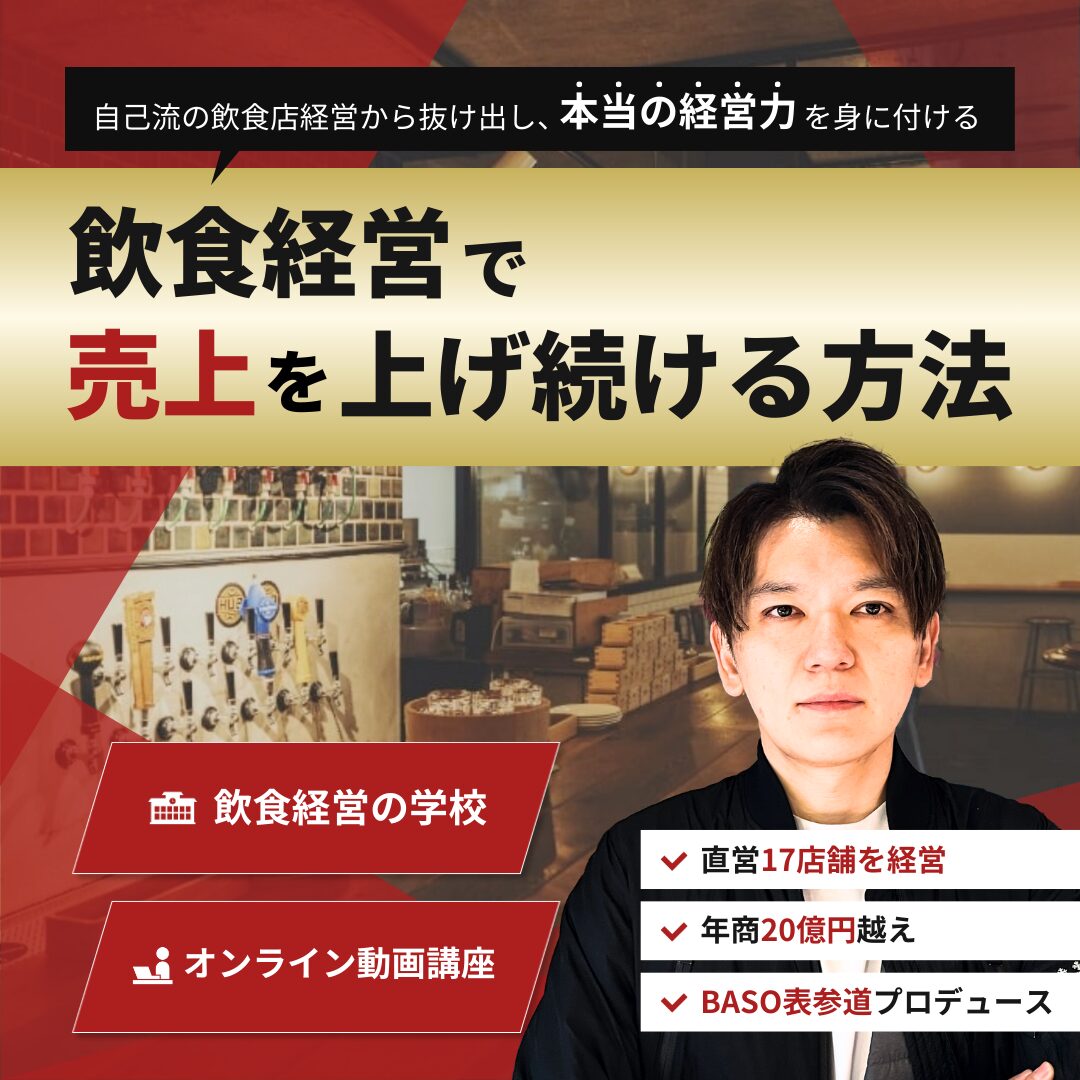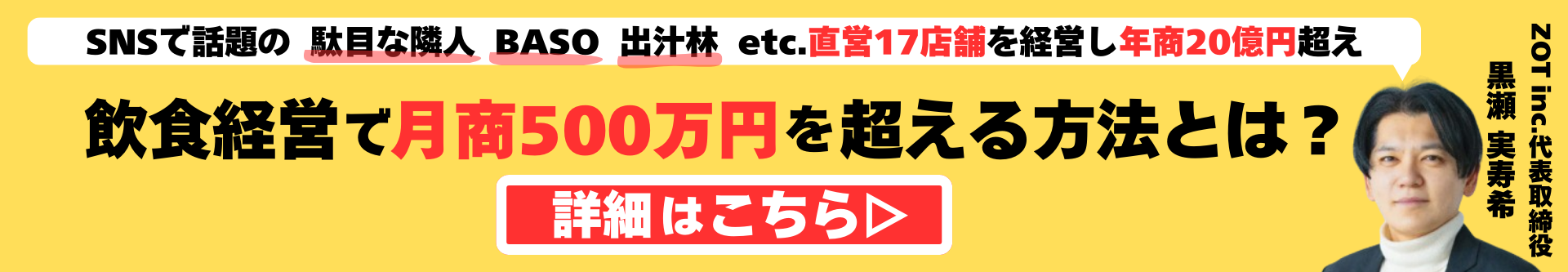飲食経営で赤字になるサイン3選:失敗を避けて利益を生み出すための視点

飲食店経営は夢とロマンに溢れていますが、その一方で廃業率が高いという厳しい現実もあります。成功を収め、安定した利益を出すためには、赤字に転落するサインを早期に察知し、対策を講じることが極めて重要です。
本記事では、プロの経営者が指摘する「飲食店が赤字になるサイン」を3つに絞り、その根本的な原因と、利益を確保するための正しい考え方について深掘りしていきます。これらのサインを見逃さず、絶対に負けない飲食経営を目指しましょう。
▽記事の内容を動画で視聴したい方はコチラ
本記事のリンクには広告を含んでいます。
①開業前から決まっている赤字のサイン:立地と業態の致命的な不一致
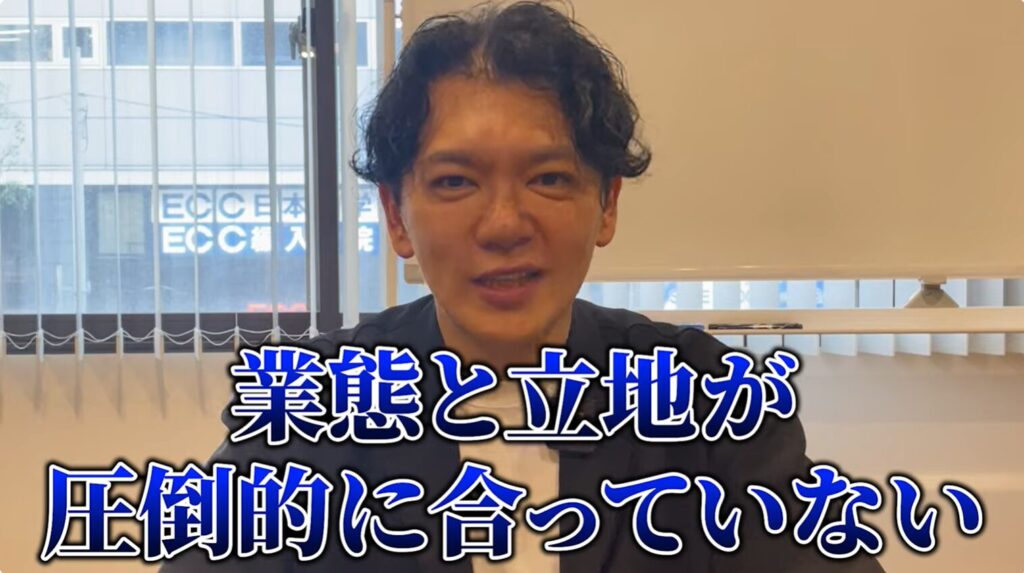
飲食店経営の成否は、最初の一歩である物件選びと業態選定で大半が決まってしまうと言っても過言ではありません。
「立地と業態が合っていない」という大元
赤字の最も大きな原因の一つは、立地と業態の選定ミスです。
例えば、ラーメン屋という低単価の業態を、駅から遠い、あるいは人通りが少ない「奥地」のような場所で開業した場合、儲かる可能性は極めて低いです。ラーメン屋は客単価が低いため、利益を出すには客数を多く集めることが必須です。しかし、そもそも立地が悪い場所を選んだ時点で、自ら客数を絞り、売上が立たない状況を作り出していることになります。
この「低単価なのに客数が少ない」という状況は、赤字の第一歩です。この基本的な経済原則が理解できていないまま、「やりたい業態」を「借りられた物件」で始めてしまうケースが非常に多いのです。
良い物件が取れない場合の戦い方
飲食店の創業において、一店舗目から最高の立地を取るのは非常に難しいのが現実です。多くの良い物件はすでに大手や成功している店舗に抑えられています。
そのため、残された「イケてない場所」で戦うことを前提とするならば、その立地なりの戦い方をする必要があります。
- 低単価業態の鉄則: 立ち食い蕎麦屋やラーメン屋などの低単価業態は、人通りが多い場所、エリアの人口ボリュームが多い場所、あるいは観光客のボリュームが圧倒的に多い場所(例:京都の観光地)でなければ成り立ちません。
- 悪い立地での戦い方: 悪い立地で勝負するなら、単価を高く設定できるレストランや、予約をベースにした業態など、客数に依存しないビジネスモデルを選ぶ必要があります。
「場所が悪かったら、店主が怪我をした」「修行したスタッフが辞めた」など、ちょっとしたアクシデントが起きた瞬間に経営が傾き、即座に赤字に転落してしまうのが、立地の悪い店舗の宿命です。まずは、立地を正しく見極め、それに見合った業態を選ぶことが、赤字を回避する最重要ポイントです。
②お客様の満足度を度外視する経営:FLを守ろうとしすぎるリスク
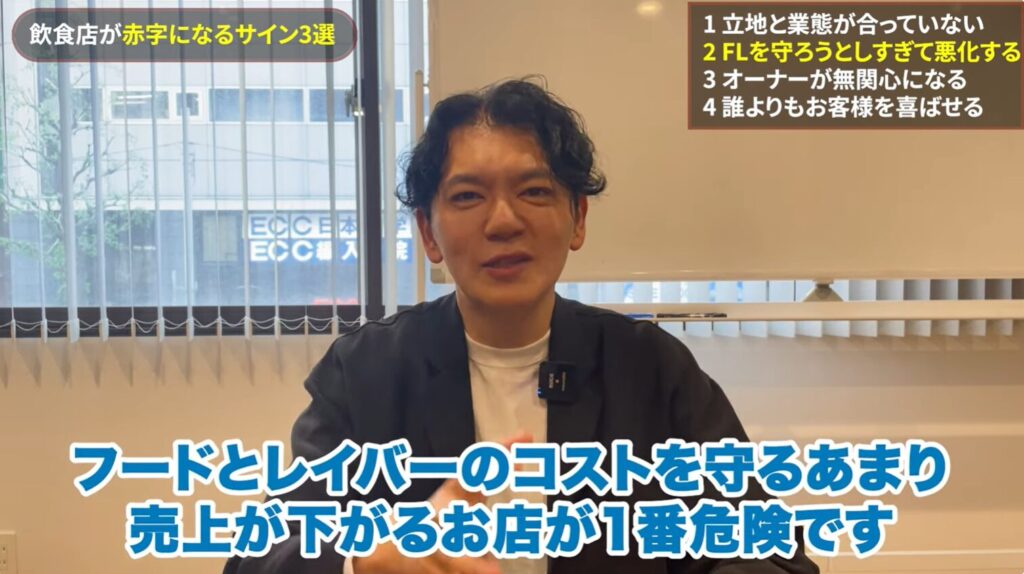
多くの経営者が「利益率の維持」のために意識するのが、FLコスト(Food Cost:食材費とLabor Cost:人件費)です。しかし、この数値を守ろうとするあまり、かえって売上を下げ、赤字に加速させてしまう危険性があります。
FLコスト意識が品質を落とすメカニズム
売上が下がり始めた時に、多くの飲食店はFLコストを守るために、食材費を抑えようとします。これが、赤字を深める最も危険なサインの一つです。
- 食材の使い回し: 売上予測を誤り、食材が余剰になった際、FLを守ろうとすると、余った食材を翌日以降に使い回すことになります。新鮮なものを出すべきところを、「1日置いたもの」「2日置いたもの」を使うことになり、当然味と品質は落ちてしまいます。
- お客様の満足度低下: 品質が落ちた食材や料理は、お客様の満足度を確実に下げます。これがリピーターの減少を招き、結果として売上ダウンに拍車をかけるという悪循環に陥ります。
「利益を残すために古い食材も使わなきゃ」という考え方は、お客様に喜んでもらうという飲食店の大前提から外れています。数値ばかりを追って、お客様の満足度を度外視する経営は、一時的にFL比率が改善しても、長期的には赤字を招く行為です。
お客様満足度を起点とした売上アップの思考
飲食店の正しい考え方は、お客様に喜んでいただいた上で、売上を上げて利益を残すことです。
売上を伸ばすことは、「飲みたくないお客様に無理やりお酒を勧める」ことではありません。お客様が満足して売上が伸びる方法はたくさんあります。
- サービスを通じた提案: 「もう一杯いりますか?」「最後の〆にこれ、おすすめです」といった提案は、お客様が求めているにも関わらず、店員が気づかなかったことで生まれる機会損失を防ぎます。
- Win-Winの関係構築: お客様が提案されたものを食べて(飲んで)満足すれば、お客様も喜び、売上も伸びるというWin-Winの関係が成立します。
FLコストは重要な指標ですが、それはお客様の満足度と売上が確保された上での話です。品質を落としてまで数値を守ろうとする行為こそ、赤字へのサインだと認識すべきです。
③売れている店舗を蝕む慢心:オーナーの無関心と劣化
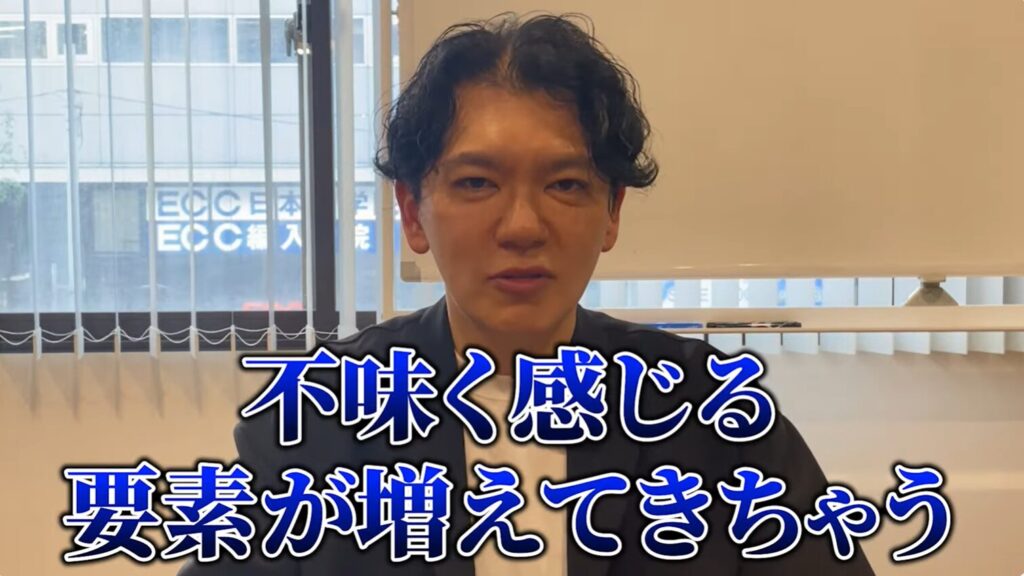
赤字のサインは、売れていない店舗だけに現れるものではありません。軌道に乗った店舗にこそ、経営者の慢心からくる赤字のサインが潜んでいます。
オーナーが無関心になることの危険性
これは、お店が一定の成功を収め、現場を部下に任せるようになったオーナーによく見られます。
- 品質の「劣化」: オーナーが現場を見なくなると、「前より良くなくなった」「イケてないよね」という常連さんの声が目立ち始めます。料理のクオリティは変わっていなくても、サービスや店舗の雰囲気が劣化することで、お客様は「まずい」と感じる要素が増えてしまうのです。
- 従業員の意識低下: オーナーが現場を離れ、利益や数字だけを追うようになると、現場の従業員は「見られていない」という意識から、サービスの質を落とし始めます。例えば、人件費を増やしても、従業員に余裕が生まれるだけで、お客様には何のメリットも提供されず、逆に従業員同士の私語が増えて不評を買うケースもあります。
オーナーの無関心は、商品開発の停止や「現状維持で良い」という思考を生み出し、時間が経つごとに店舗のクオリティをどんどん劣化させていきます。
現場から離れた際の正しいマネジメント
オーナーが現場を離れることは、店舗展開においては必要なプロセスですが、それは「放置」を意味しません。現場から離れた時こそ、より細かく店舗をチェックし続ける必要があります。
- 競争意識の醸成: 従業員に店舗を任せる際は、「僕より売上を高く出してね」と伝え、オーナーが現場にいる時よりも高いレベルでの営業を求めましょう。これにより、現場のスタッフは競争意識を持ち、積極的に売上アップのための工夫をするようになります。
- 数字による監視と教育: オーナーがいない時ほど、時間帯ごとの売上、人件費、発注額などの数字を細かくチェックし、現場にフィードバックすることが重要です。「社長がいない日でも、数字は必ず突っ込まれる」という意識を持つことで、従業員は細部にまで気を配るようになります。これは、現場を離れても現場を最も見ているという意識をスタッフに持たせるための教育プロセスです。
- 外部からのチェック: 監視カメラの活用や、他のスタッフに頼んで抜き打ちで営業を見てもらうなど、「見られている意識」を現場に絶えず持たせる仕組みづくりも必要です。
オーナーの関心度が、店舗のクオリティを維持する生命線です。売上が安定している時ほど、このサインに注意し、現状維持ではなく常に前進を目指すことが、赤字を回避し、持続的な成功を収める秘訣です。
まとめ:赤字のサインを見逃すな
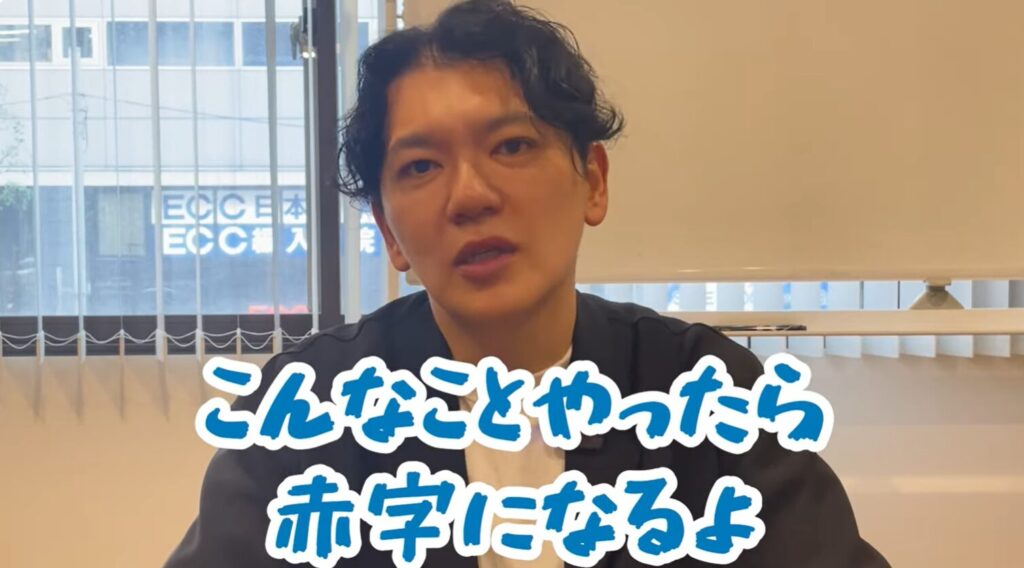
飲食店が赤字になるサインは、主に以下の3点に集約されます。
- 立地と業態の不一致: 低単価業態を人通りの少ない場所で始めてしまう、根本的な戦略ミス。
- FLコストの過剰な意識: FLを守ろうとするあまり品質を落とし、お客様の満足度と売上を下げてしまう本末転倒な経営判断。
- オーナーの無関心: 成功した店舗を放置することで、店舗のクオリティが劣化し、常連客が離れていく。
これらのサインは、一つでも当てはまると赤字への道を加速させます。特に、オーナーは現場から離れた時こそ、数字と状況を細かく監視し、お客様の満足度を最優先にするという大前提を決して忘れてはいけません。
このような経営状況の管理について、より深く学ぶことができる環境を提供しています。ご興味がある方はぜひ公式LINEの登録をお願いします。