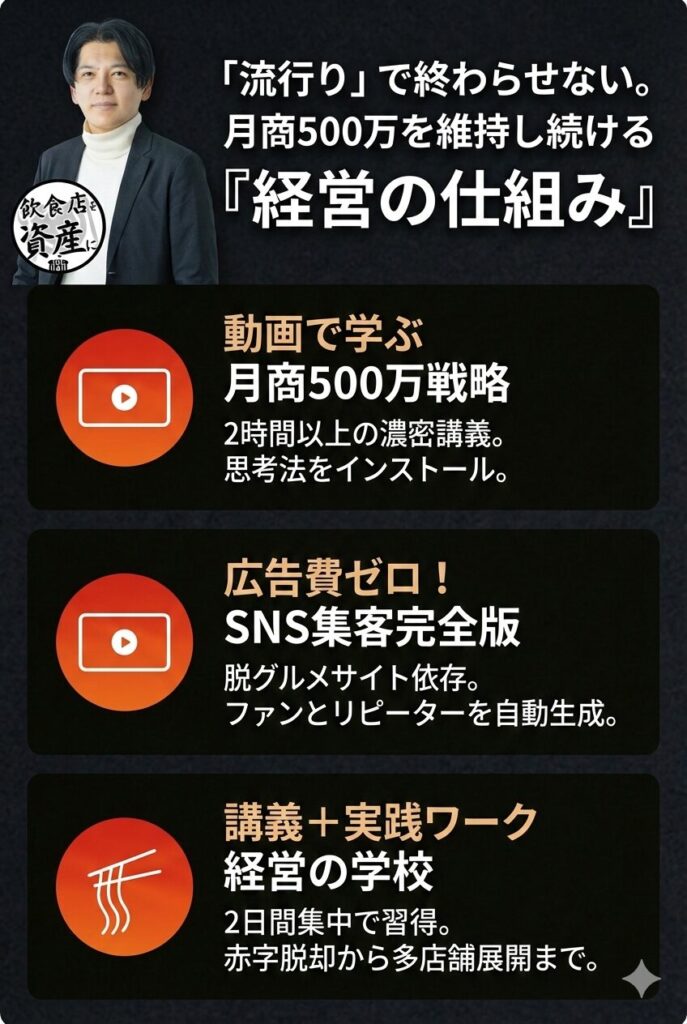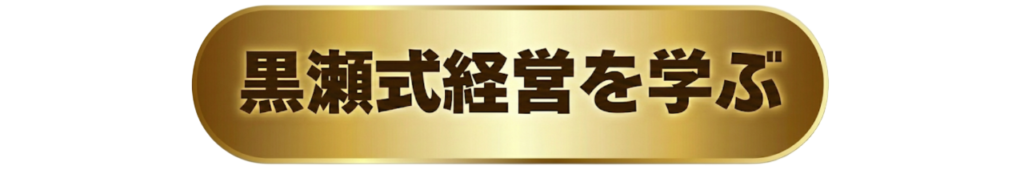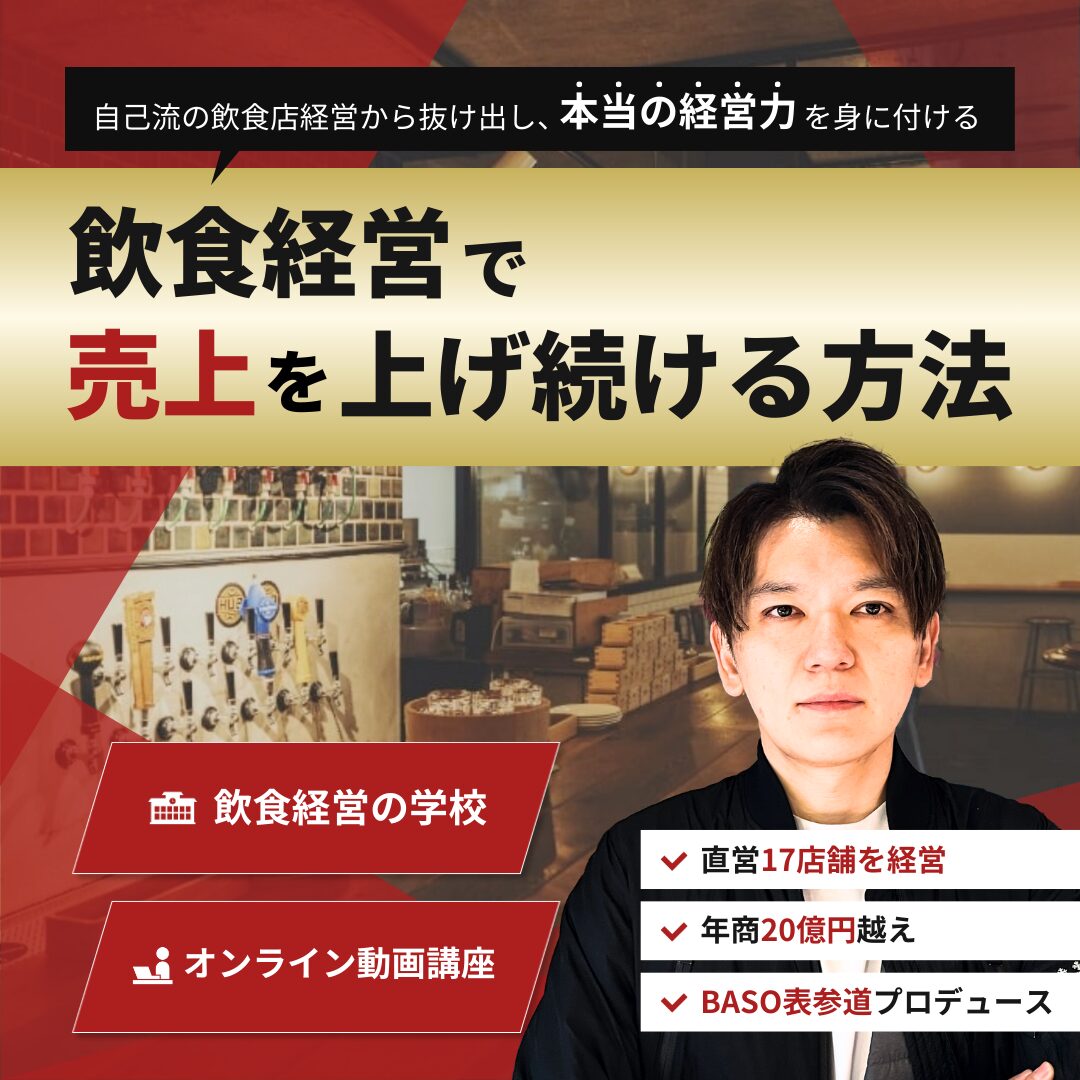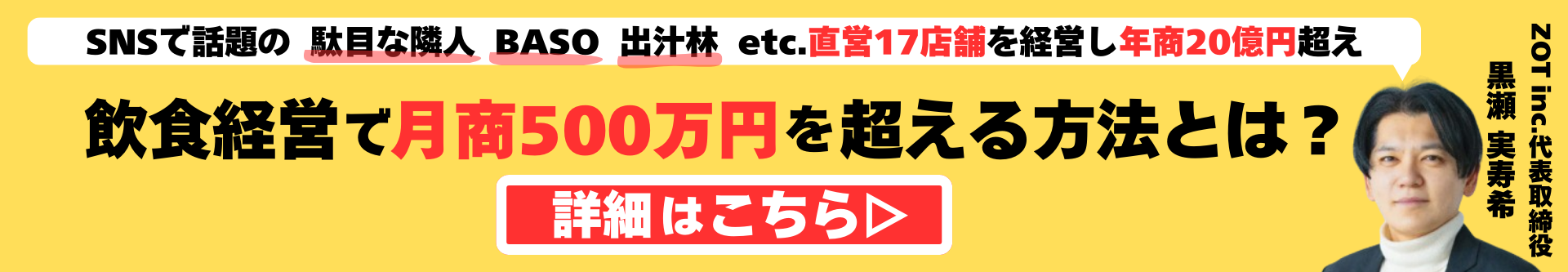デザート業態で成功するための秘訣と落とし穴

デザート業界は常に新しいトレンドが生まれ、華やかなイメージがありますが、実際にビジネスとして成功し続けるにはいくつかの重要な要素があります。単なるブームに終わらず、安定した収益を上げるデザート業態の共通点、そしてジャンルごとの成功と課題について、具体的な事例を交えながら深掘りしていきます。
▽記事の内容を動画で視聴したい方はコチラ
本記事のリンクには広告を含んでいます。
デザート業態の成功を左右する二つの共通点

デザート業界において、業態的にうまくいっている店舗には、共通する明確な特徴が二つあります。それは「単価が取れること」と「ピークタイムの分散」です。この二点を押さえているかどうかが、その店舗が残り続けるかどうかの大きな分かれ目となります。
高い客単価を実現する戦略
デザート系業態で成功している共通点の第一は、何よりも「単価が取れること」です。単価が低いと客数を多く集める必要があり、経営が不安定になりがちです。
例えば、デザートなのにコーヒーとセットで2000円取れるような店舗は「強い」と言えます。また、ドリンクだけでも通常のカフェであれば500円程度のものを800円で提供できるような価格設定の店舗は、比較的残りやすい傾向にあります。客単価が高いということは、少ない客数でも安定した売上を確保できるため、経営の自由度が高まります。
ピークタイムを分散させる集客力
売上を伸ばすためには、単価が取れることに加えて、「ピークタイムがいわゆるカフェタイム(15時前後)以外で取れる」という点が非常に重要になります。つまり、特定の時間帯に集中せず、1日を通して集客できる能力が求められます。
あるパンケーキ屋さんの例では、最も客が集まるのは「朝」で、朝8時には既に行列ができるほどでした。このお店は朝食専門店だったという背景もありますが、予約が取れないほどの人気で、しかも客単価が大体3000円という高単価でした。パンケーキだけで2000円程度、それにドリンクやトッピングを頼むと3000円に達するのです。この事例は、単価が高く、かつ通常のカフェタイムから外れた時間帯に強力なピークタイムを作り出すことが、いかに売上に貢献するかを示しています。
ブームを追いかけることの難しさ
時代によって「当たり」となるデザートはありますが、その中で生き残っているのは、ブームの中で1位を取った人たちだけです。例えば、パンケーキブームの時に最も認知度が高かった店舗など、ブームを「一番最初」に作った店舗には、後発ではなかなか勝てません。
そのため、ブームを追っかけで始めるのであれば、「単価が取れて、ピークタイムが2個ぐらい取れるもの」でないと、正直なところ経営は厳しいと言えます。単なる流行に便乗するのではなく、独自の強みや集客の仕組みが不可欠なのです。
特定ジャンルの課題と成功の鍵:クレープ、タピオカ、夜パフェ
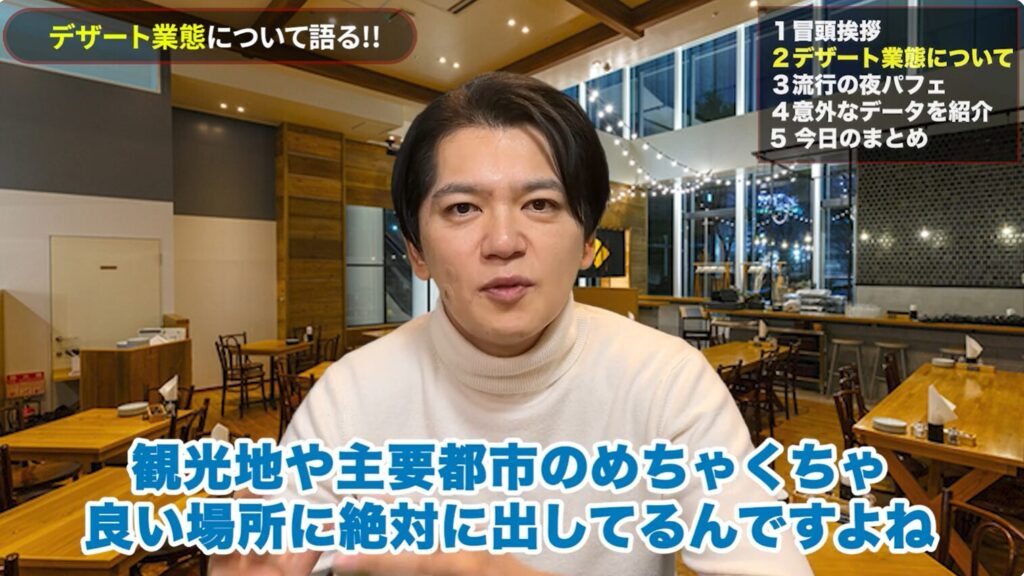
デザート業態の中でも、ジャンルによって成功の難易度や求められる戦略は大きく異なります。クレープ、タピオカ、夜パフェといった特定のジャンルが持つ特有の課題を見ていきましょう。
クレープ業態の難しさ:客単価と立地
ジャンルとして見た場合、クレープは相当難しい業態であると言えます。
一見、気軽に買えそうなイメージはありますが、実際は購入頻度が低かったり、店内で食べるパターンがあまり当たらないため、客単価が上がりづらいという構造的な問題があります。さらに、売れる時間帯が少ないという点も、クレープ業態が抱える辛い課題です。ピーク時には売れるものの、全体に平すと売上が微妙なことが多いのです。
クレープは持ち帰りの需要もあるものの、そうなると今度は「場所」の問題が非常に大きくなります。現在でも売れているクレープ屋さんで残っている店舗は、観光地や主要都市の非常に良い場所に出店していることがほとんどです。これはラーメン屋の事例と同様で、立地が良ければ客数が取れるため、単価が低くても売上が積み上がります。しかし、立地が悪いところでは集客が厳しくなります。
地方で並んでいるクレープ屋さんがあったとしても、それは単に人気なだけではなく、「料理が出てくるのが遅い」など、何かしらの他の理由が関わっていることが多いです。
ブームに左右されるデザートの共通点:タピオカの例
タピオカドリンクのブームは非常に大きかったですが、ブームが去った後、当時の半分の店舗も残っていないのが現実です。
このようなブームや時期に左右されてしまうデザートの基本的な共通点は、「想像してこれ食べたいな」と無意識に思わないものです。デザート系では、ケーキやパフェなどは想像できますが、それ以外のものは「見たら食べたい」と思うことはあっても、「無意識に今日これ食べたい」となることはないため、継続的な集客が難しくなります。人の動線としてマーケットがないところに出店してしまうと、ブームが去った後に苦戦することになります。
夜パフェ専門店:高い単価と曜日の制約
スイーツの中でも、パフェは比較的イメージがつくジャンルですが、最近よくある「夜パフェ」はどうでしょうか。
会員制の夜パフェ店などは、優越感や人を連れて行くエンタメ性があり、お金がかかっている分美味しいものが出てくるという点では良いのですが、「よっぽど気に入らないと行きたいなとは思わない」という側面もあります。
夜パフェ屋さんは単価が高く、平均で2000円〜3000円程度です。若い層は居酒屋に行った後に行くことが多いですが、居酒屋で3000円払った後に、さらに3000円を支払うのは厳しいと感じる人もいるでしょう。また、夜パフェは主食にしづらいため、その需要がある特定の場所でやる分には良いものの、展開して拡大していくのは難しいと考えられます。
夜遊びの延長で夜パフェ屋に行くという利用シーンが多いことから、「明日から仕事の日」には行かず、金曜や土曜のように曜日は限られます。また、夜パフェ専門店は昼営業をしないことが多く、カフェと同様に時間帯も限られます。夜パフェ専門店という業態は、お酒を飲んだ後や軽い食事の後に行くというイメージから、ターゲットとするマーケットが縮小している状態にあるため、積極的に参入するメリットは少ないかもしれません。ただし、飲み屋街のようなエリアには必要とされる需要はあります。
国民食の落とし穴と成功の戦略:たい焼き屋の事例
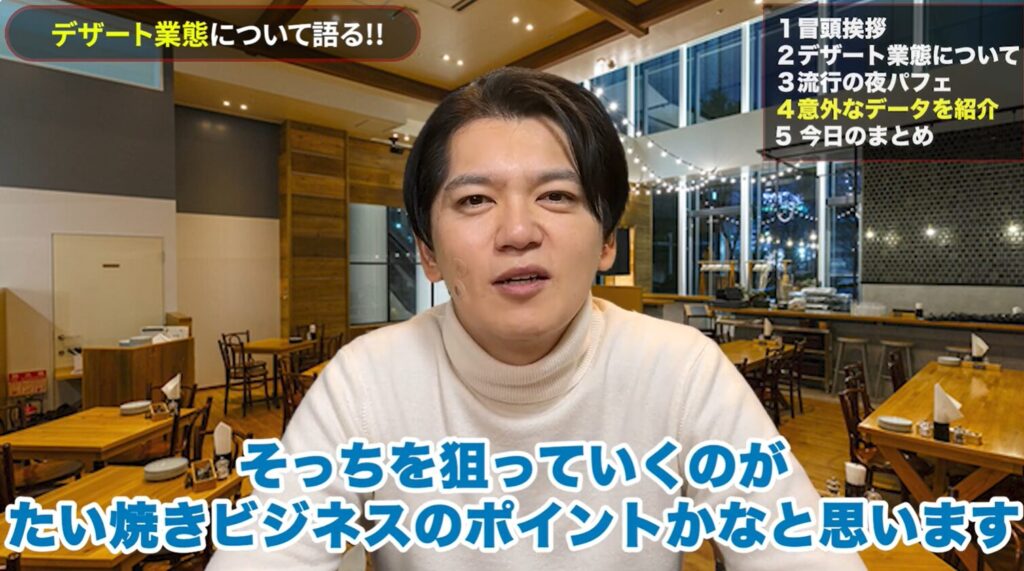
国民食として親しまれているたい焼きのような和風スイーツも、ビジネスとしては特有の課題と成功の戦略が存在します。季節要因や立地選びが非常に重要になります。
たい焼き屋を悩ませる季節的な要因
たい焼き屋の売れ行きはシーズンがはっきりしています。暖かい時期になると売上が下がり、その時期はいかに人件費を抑え、赤字を掘らないようにするかが勝負となります。冬になると売上が回復するという、季節的な要因が売上を大きく左右する業態です。国民食であるため通年でずっと売れているかというと、厳しい側面があります。
成功する立地:観光地よりオフィス街
たい焼き屋の成功において、エリア選びも非常に大事になってきます。多くの人がイメージするのは観光地への出店ですが、実はオフィス街の方が売れるというデータがあります。
その理由は、販売のロット数の違いにあります。食べ歩きで10人が1個を買うよりも、オフィス街で1人がお土産や挨拶用に20個買っていく方が、一度の販売ロットが大きいからです。このロット数の大きい需要をしっかりと取れているお店は、売上が非常に高くなります。
危険な立地の見極め方
たい焼き屋さんで出店してはいけない立地、つまり「危険な場所」として挙げられるのは、売れそうでも人がいない商店街などです。ベッドタウンによくある商店街は、人がいっぱい通るから売れそうだと思われがちですが、意外と売上が立たないことは少なくありません。もちろん商店街でも需要はありますが、ロット数が低いことが多いので、オフィス街の方が売れる傾向にあるのです。
まとめ:デザート業界は甘くない

デザート業態は総じて、どれを選んでも「大変」であると言えます。
それでも挑戦するのであれば、まずはマーケティングを徹底することが重要です。そして、普通の料理と異なり、スイーツはグラム単位で味が変わってしまう繊細さがあるため、パティシエと組むなどして「ちゃんと美味しいもの」を提供できることが、成功のためには不可欠となります。単なるブームではなく、確かな商品力と戦略に基づいた経営が求められるのです。