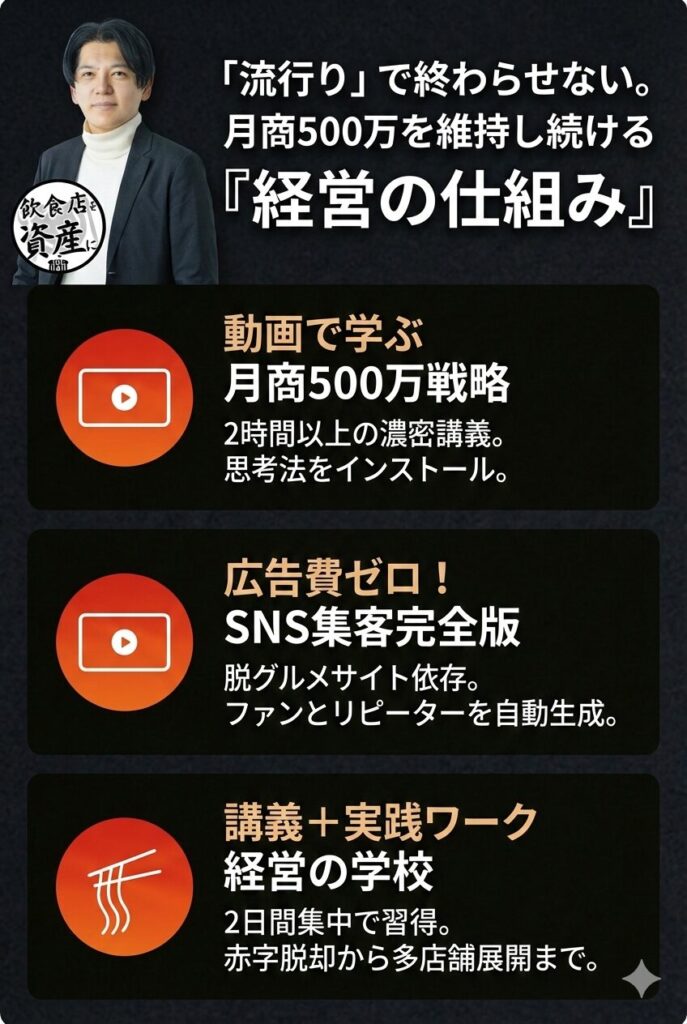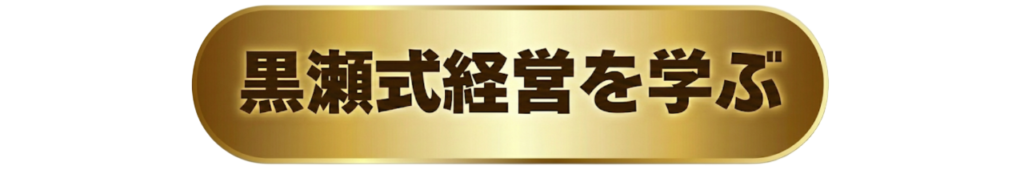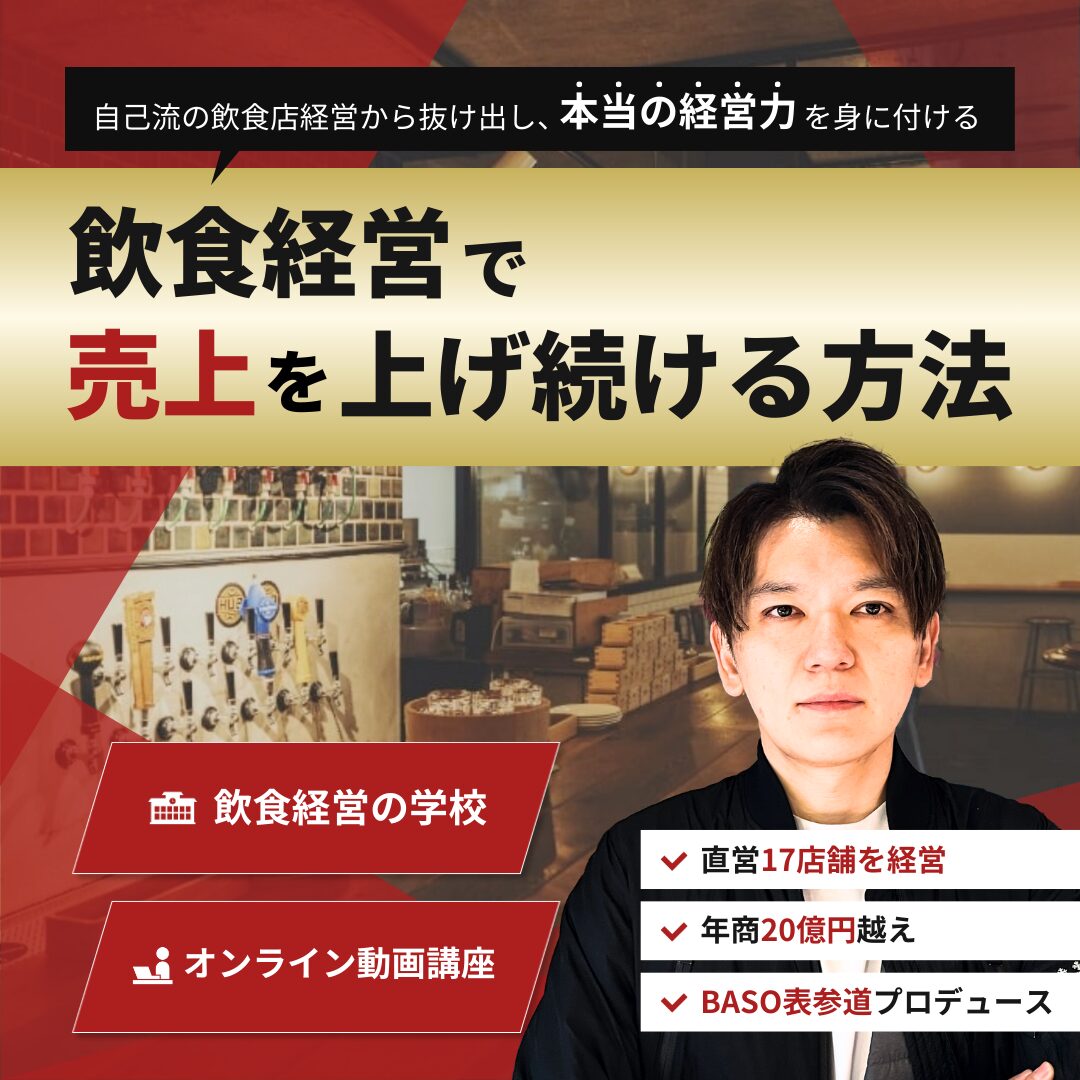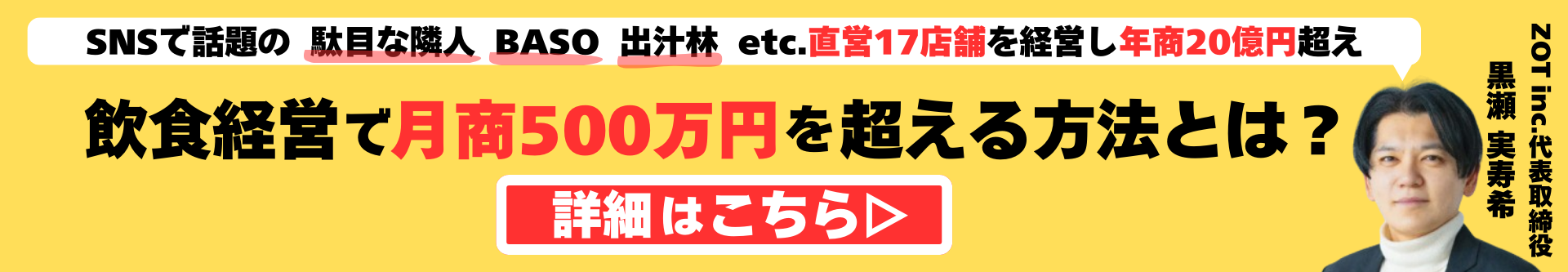【飲食経営の極意】創業42年うどん老舗「こんぴら茶屋」の挑戦から学ぶ、フランチャイズ展開で大事なこと

目黒に店を構え、創業から42年を迎える老舗うどん店「こんぴら茶屋」。
長年にわたり、その名物「カレーうどん」で多くの客を魅了し続けてきたこの店が、今、大きな転換期を迎えています。
創業者から事業を引き継いだ新社長の笹川氏のもと、フランチャイズ展開という新たなステージへの挑戦が始まりました。
実際に店舗を訪れ、この老舗が持つ強みと課題を徹底的に分析し、プロの視点から導き出された戦略の一部をご紹介します。
▽記事の内容を動画で視聴したい方はコチラ
本記事のリンクには広告を含んでいます。
老舗の「今」を徹底解剖する現地視察

圧倒的な「味」が支える繁盛の秘密
まずは名物である「カレーうどん」を試食。その味は、長年愛されてきた理由を証明するものでした。特にもちもちとした手打ちのような独特の麺の食感は、深い感銘を受けます。
店主へのヒアリングから、その美味しさの秘密が明らかになります。
使用している小麦粉は全粒粉という日本で唯一の粉を香川県で作って送っているとのこと。このこだわりの素材が、唯一無二の麺のコシともちもち感を生み出しているのです。
また、創業以来、広告宣伝をほとんど行わずとも口コミだけで集客できていることは、味が良い証拠だとも評価できます。実際に、土日には1日400食を販売することもあるといい、その圧倒的な人気ぶりが数字でも示されました。
プロの視点が暴き出す、繁盛店の「経営課題」

立地・顧客層と席配置のミスマッチ
JR目黒駅から徒歩5分という好立地にあり、周辺には多くのオフィスビルが立ち並び、ランチタイムには多忙なビジネスパーソンがひっきりなしに行き交います。
このような立地の特性から、必然的に「一人で食事を済ませたい」というニーズを持つ顧客層が非常に多いと推測できます。
しかし、店内を視察すると、客席のレイアウトは4人掛けのテーブル席が中心となっており、一人客が気軽に利用できるカウンター席はわずか数席しかありませんでした。
この席配置では、ピーク時に一人客が来店しても、テーブル席が空いていないために店に入ることができず、結果的に「席効率の低下」と「売上の機会損失」という大きな課題を生み出していました。
多くの来店客を抱えながらも、さらに売上を伸ばすためのボトルネックになっている可能性が高いことがわかります。
味だけに頼った集客の停滞
創業以来、広告宣伝を行っていないことは一見素晴らしいことですが、裏を返せば、集客が「口コミ」と「既存のリピーター」に強く依存している状態を意味します。
新規顧客の獲得に向けた積極的な施策が不足していることから、本来顧客になるはずの客層にアプローチできていない可能性があります。
新たなステージへの挑戦と「事業承継」

フランチャイズ成功の鍵は「明確なターゲット」
フランチャイズ展開を成功させるには、単に味が良いだけでは不十分であり、「誰に、何を、どのようにして売るか」という主要顧客層を明確にすることが最も重要です。
このターゲット設定が曖昧なままでは、どれだけ良い立地や物件を選んだとしても成功は難しいです。この主要顧客層を明確にすることで、上記の課題にあった「席配置や集客」などの戦略が定まり、効果のある施策を行うことができます。
実際に、BASO表参道店では、立地の特性を活かして、ターゲットを原宿に来る若い女性、特にヘルシーなものが食べたい人に絞った上で、業態や商品、盛り付け、内装を決めたことでヒットしました。

また、フランチャイズ展開においては、既存店舗の主要顧客のデータ取得が必須となり、それを活用できるかが重要なポイントになります。
それに加えて、加盟店オーナーの教育や店舗運営のマニュアル化も不可欠です。味を忠実に再現できるシステムを構築した上で、ターゲットに合わせた戦略を練り、一貫したブランドイメージを保つことが求められます。
まとめ:味と戦略の両輪で未来を切り拓く

創業42年の伝統で培われた「味」という揺るぎない強みと、プロの視点から導き出された「経営戦略」という革新的なアプローチ。
この2つが融合することで、「こんぴら茶屋」は新たな成長物語を築こうとしています。
この挑戦は、すべての飲食店経営者にとって、自身の店舗の現状を見つめ直し、未来への一歩を踏み出すための貴重な示唆を与えてくれます。
このような経営戦略の立て方について、より深く学ぶことができる環境を提供しています。ご興味がある方はぜひ公式LINEの登録をお願いします。