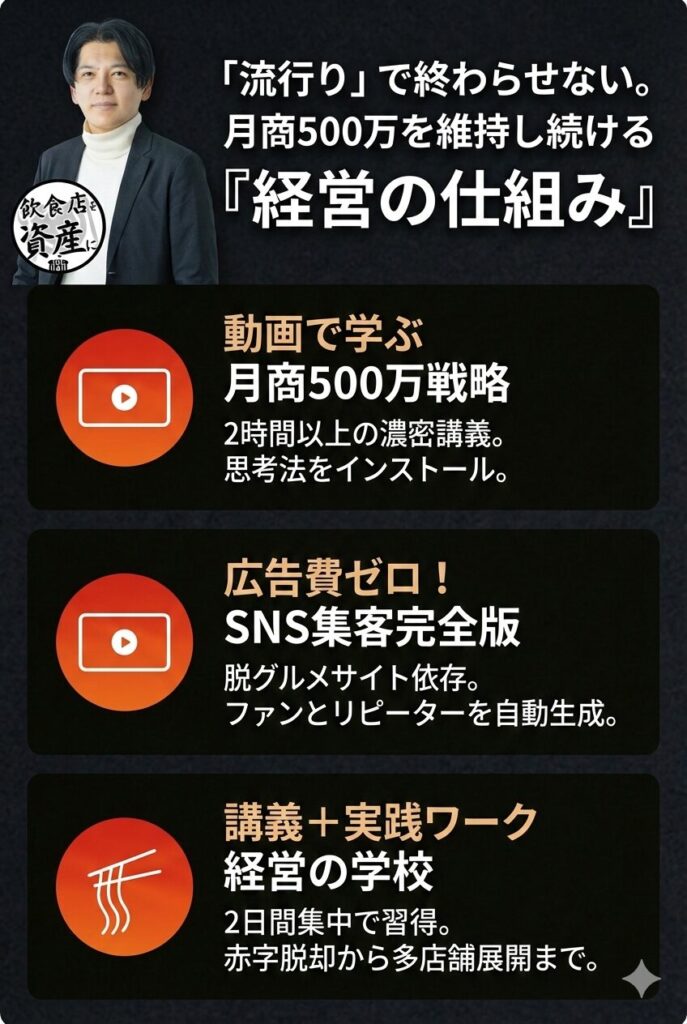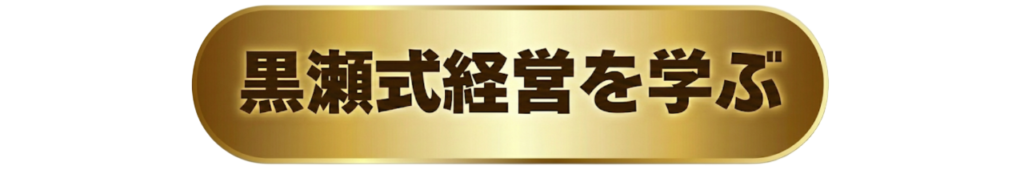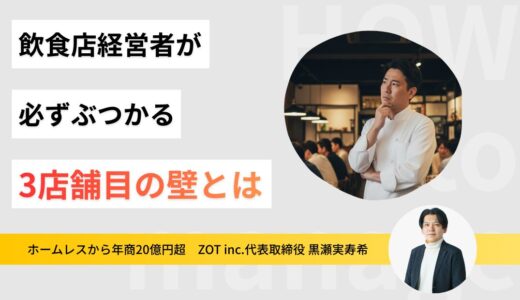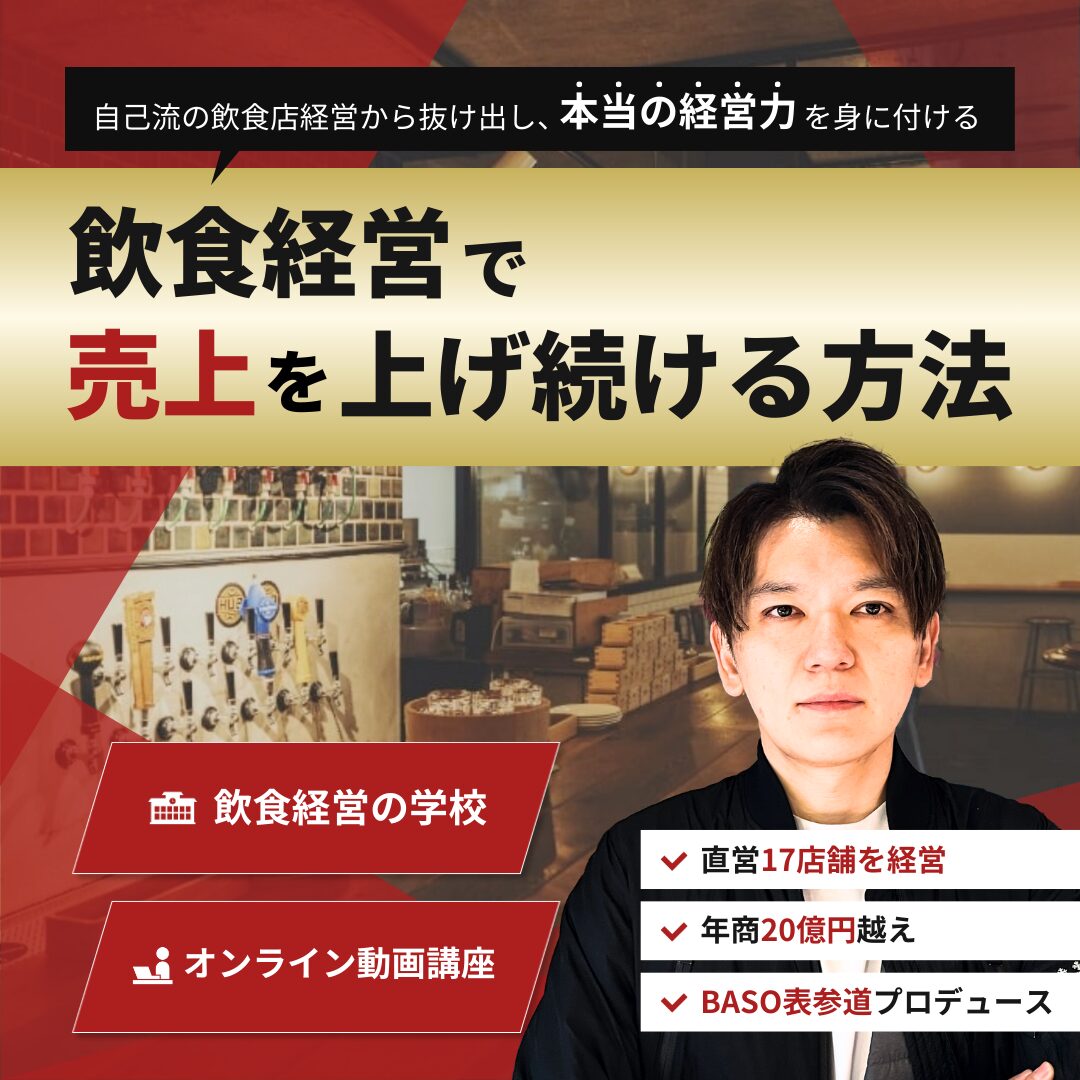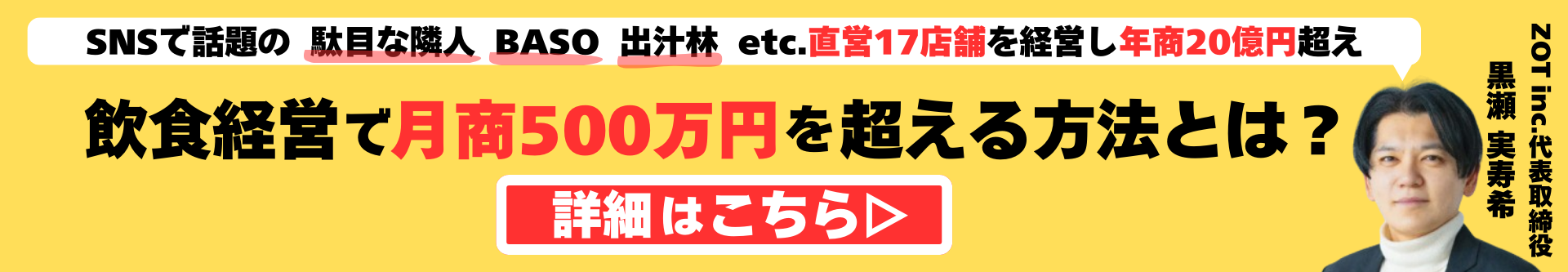飲食店でよくあるSNSの意味のない使い方3選

現代の飲食店経営において、SNSは集客の要として不可欠なツールとなりました。しかし、多くの店舗がSNSアカウントを持ちながらも、「やっているけれど効果が出ない」「フォロワーは増えるけれど、来店につながらない」といった悩みを抱えています。これは、知らず知らずのうちに「意味のない使い方」をしていることが原因かもしれません。
今回は、飲食店が陥りがちなSNSの落とし穴を3つに絞って深掘りし、集客に本当に役立つSNS活用術を提案します。これからSNSを始める方、そしてすでに活用しているものの成果に伸び悩んでいる方は、ぜひこの記事を参考に、ご自身のSNS戦略を見直してみてください。
▽記事の内容を動画で視聴したい方はコチラ
本記事のリンクには広告を含んでいます。
意味のない投稿で埋め尽くす罠:商品以外の情報ばかりを発信していませんか?

SNSを始めたばかりの頃、多くの人が直面するのが「何を投稿すればいいか分からない」という壁です。この壁にぶつかった結果、お店の外観や内装、スタッフの集合写真、あるいは「本日も元気に営業しています!」といった、誰でも投稿できるような無意味な情報を発信してしまいがちです。
投稿すべきは「お客様が食べたい」と思う商品のみ
実際のところ、お店の外観や内装の写真は、よほどの独創性がない限り、お客様の「行きたい」という気持ちをかき立てることはありません。また、「本日の営業時間」や「定休日のお知らせ」といった情報は、SNSのプロフィール欄やGoogleビジネスプロフィールに記載していれば十分な内容です。
なぜなら、お客様がSNSを見てお店を知る際、最も知りたいのは「どんな商品が食べられるのか」だからです。もしあなたがステーキを食べたいと思っているとして、お店のSNSに外観やスタッフの写真ばかりが並んでいたらどう感じるでしょうか? おそらく「結局、どんなステーキがあるんだろう?」という疑問が残り、他の情報源を探しに行くか、最悪の場合は興味を失ってしまいます。
お店のSNSは、言わば「動くメニュー表」です。お客様の「食べたい!」という気持ちをかき立てるような、シズル感あふれる商品写真や動画をメインに投稿することが最も重要です。
お店の看板メニューはもちろん、季節限定のメニューや、他店では味わえないユニークな商品に焦点を当てることで、お客様の興味を強く引きつけることができます。
映えない商品は投稿するな:SNSで「映える」商品を作り、研究し、投稿する

商品写真の投稿に切り替えられたら、次のステップです。ただ単に写真を撮って載せるだけでは、多くのお客様の目に留まることはありません。
SNSで「映える」商品を作り込む重要性
現代のSNSは、多くの情報が流れる「タイムライン」と呼ばれる空間で、一瞬でスクロールされてしまいます。その中で、お客様の指を止めさせ、投稿をじっくり見てもらうためには、圧倒的なビジュアルのインパクトが必要です。いくら味が美味しい料理でも、写真や動画でその魅力が伝わらなければ、お客様の心は動かないのです。
そのためには、SNSで「映える」ことを意識して商品を開発することが重要です。例えば、蕎麦のように通常は平たく盛られる商品でも、あえて縦に高く盛り付けたり、麺一本一本の美しさが際立つように盛り付けたりすることで、見る人に強いインパクトを与えることができます。
味、見た目、色、すべてにおいて「SNS映え」を意識して作り込む。そして、投稿する際には、どの角度から撮れば最も魅力的に見えるか、どんな照明を使えば料理が引き立つかといった研究を重ねることが不可欠です。
投稿後の「研究」が成長を促す
投稿は「して終わり」ではありません。投稿後に、どれだけのリーチ数があったか、どのようなコメントがついたか、どれくらいの「いいね」や保存がされたかといったデータを分析することが非常に重要です。
データ分析を通じて、どの商品がお客様に響いたのか、どのような投稿がより多くの人の目に触れたのかを把握し、その要素を次の投稿に活かす。このPDCAサイクルを回し続けることで、SNSの運用スキルは飛躍的に向上し、結果として集客効果も高まっていきます。
フォロワー数ばかりを追うな:投稿頻度とリーチ数を意識せよ
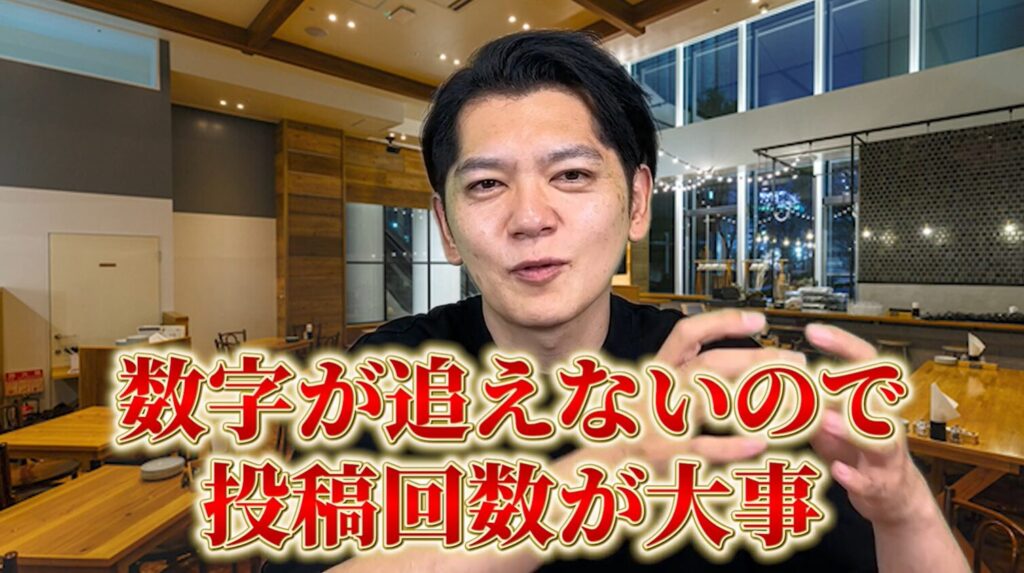
SNS運用を始めた多くの人が陥りがちなのが、「フォロワー数を増やすこと」を第一の目標にしてしまうことです。しかし、フォロワー数はあくまで目安に過ぎません。
投稿頻度が少ないと成果は見込めない
SNSで成果を出すためには、まずお客様の目に留まる回数を増やす必要があります。週に1回の投稿では、毎日投稿している競合店と比べて、お客様との接点が圧倒的に少なくなります。当たり前ですが、投稿回数が少ないと、投稿を見てもらう機会が減り、結果として集客効果も薄れてしまいます。
SNS運用を始めたばかりの頃は、1日1投稿を目標にしましょう。軌道に乗ってきたら、最低でも2〜3日に1回は投稿するように心がけることが大切です。投稿頻度を上げることで、より多くのお客様の目に触れ、お店の存在を認知してもらう機会を増やすことができます。
登録者数(フォロワー数)ではなく「リーチ数」を追え
フォロワー数が多くても、それがお店に来店してくれる「本当のお客様」でなければ意味がありません。そして、フォロワー数が多くても、投稿がフォロワーのタイムラインに表示されなければ、それは「見ていない」のと同じです。
SNS運用において本当に重要なのは、投稿がどれだけの人に届いたかを示す「リーチ数」です。X(旧Twitter)における「インプレッション」も同様の指標です。これらの数字を追うことで、どの投稿がどれだけの人の目に触れたのかを正確に把握することができます。
リーチ数を増やすためには、投稿頻度を上げ、お客様の興味を引くコンテンツを継続的に発信することが不可欠です。フォロワー数に一喜一憂するのではなく、地道にリーチ数を伸ばすための努力を続けることが、SNSを成功させるための王道と言えるでしょう。
まとめ:SNSを効果的に使おう

飲食店が陥りがちな「SNSの意味のない使い方」は、以下の3つに集約されます。
- 商品以外の画像を載せない: お客様が本当に見たいのは、お店の商品です。外観やスタッフの投稿は最小限に抑え、料理の魅力にフォーカスしましょう。
- SNSで映える商品を作れていない、載せていない: 味だけでなく、見た目や色も意識して商品を開発し、どうすれば魅力的に見えるかを研究してから投稿しましょう。
- 投稿頻度が少ない・フォロワーを追ってしまう: 投稿頻度は毎日、少なくとも2〜3日に1回は投稿することが重要です。フォロワー数ではなく、投稿がどれだけの人に届いたかを示すリーチ数を追って分析しましょう。
SNSは、ただやればいいというものではありません。効果を最大化するためには、戦略的な思考と地道な努力が不可欠です。これらのポイントを意識して、SNSを強力な集客ツールへと進化させましょう。
SNSの使い方について、より深く学ぶことができる環境を提供しています。ご興味がある方はぜひ公式LINEの登録をお願いします。