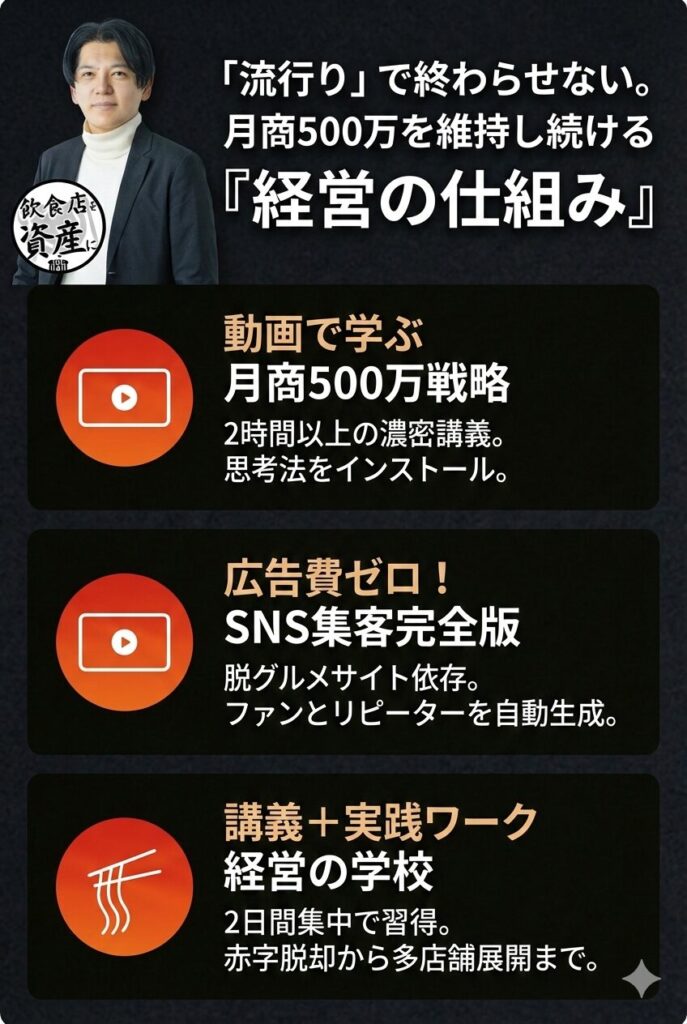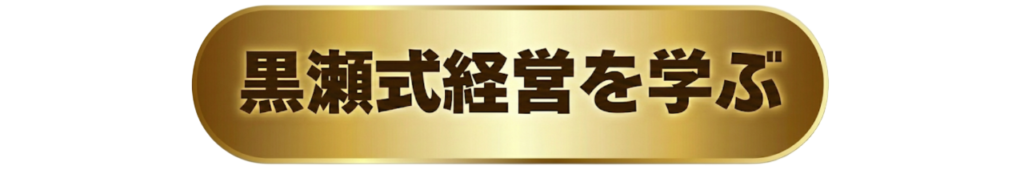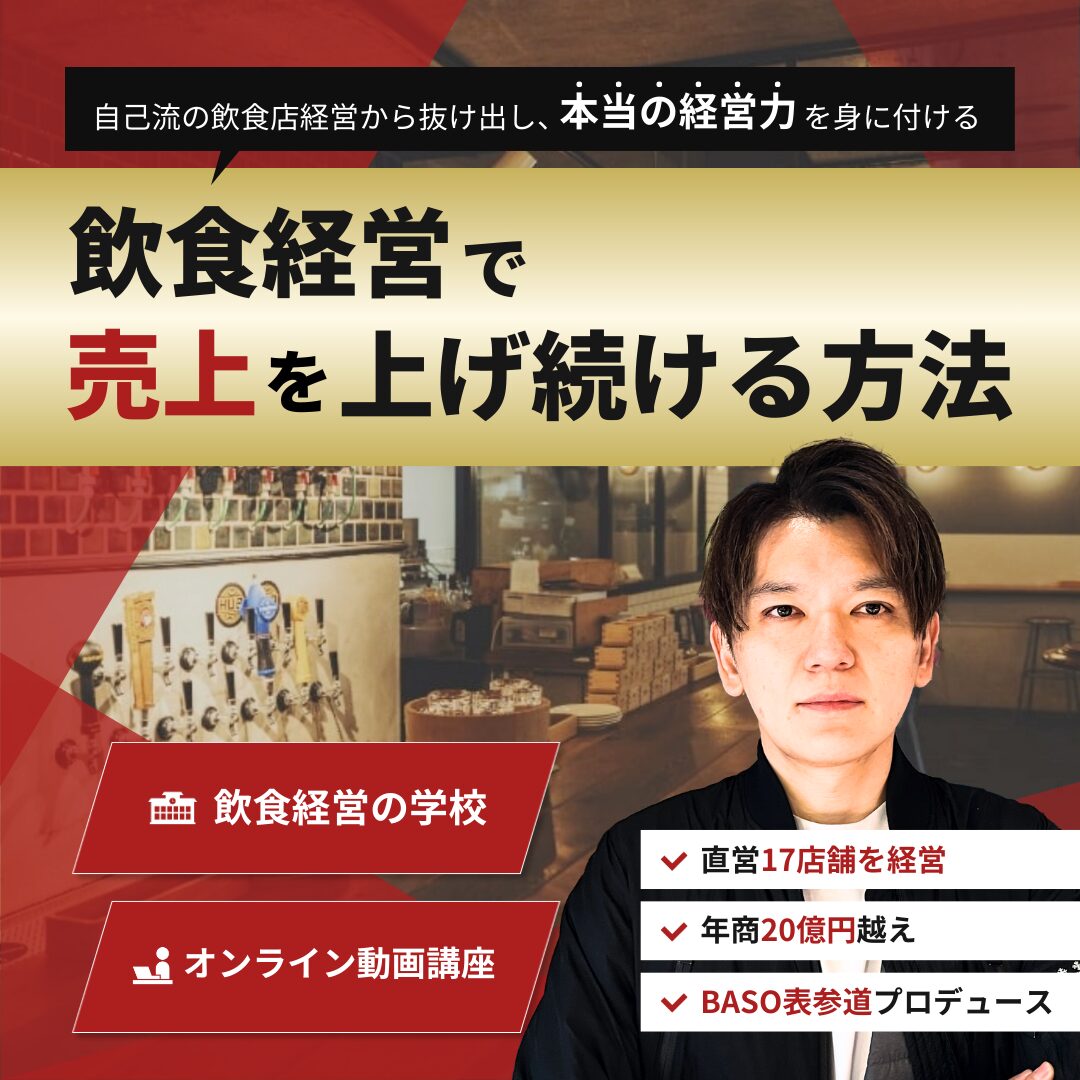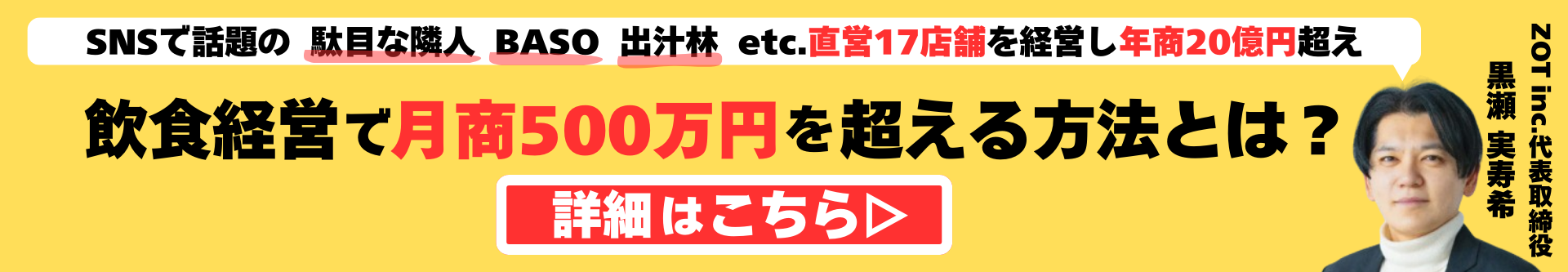【飲食店経営者必見】原価率を抑える3つの方法|仕入れ・管理・値付けの見直しで利益体質に!

物価の高騰が続くなか、飲食店オーナーにとって「原価率」はますます重要なテーマとなっています。
「仕入れコストが上がって利益が出ない」「値上げしたいけどお客さんに嫌われそう」──そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「原価率を抑えるための具体的な方法3選」を徹底解説します。今日から実践できるポイントばかりなので、ぜひ自店の経営改善に役立ててください。
▽記事の内容を動画で視聴したい方はコチラ
本記事のリンクには広告を含んでいます。
原価率の目安はどれくらい?
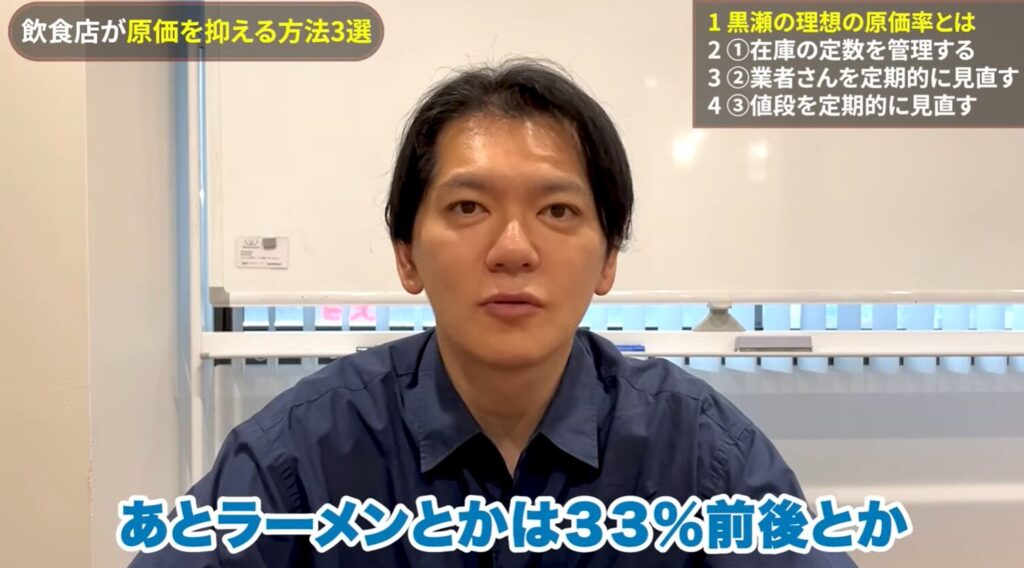
飲食業態によって、理想的な原価率は異なります。一般的には以下の通りです。
- 高級業態(鰻や和食など):40〜45%前後
- ラーメン店:33%前後
- 居酒屋業態:35%前後
原価率を下げればいい、というわけではありません。お客様は「良い食材=美味しい」と感じやすいため、ある程度の原価をかけることはむしろプラスにもなります。大切なのは、利益を確保しつつ、お客様に満足してもらえるラインを守ることです。
原価率を抑える方法①:在庫の「定数管理」を徹底する
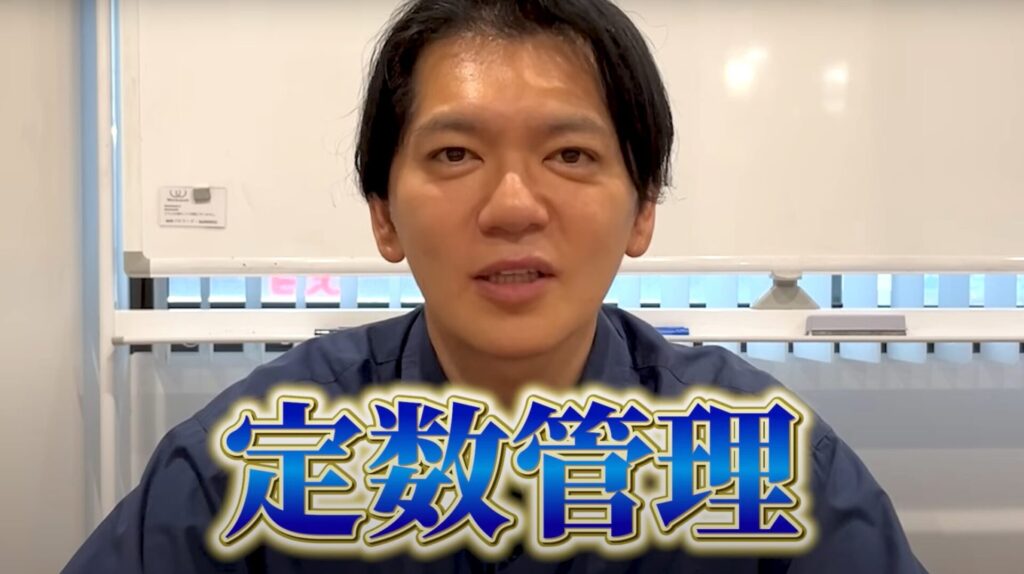
在庫を抱えるリスク
原価管理の基本は 「定数管理」。
つまり、1日あたりに必要な使用量をあらかじめ設定し、それに基づいて発注を行うことです。
在庫を過剰に抱えると、以下のような問題が発生します。
- 仕入れが多くなり、原価率が上昇する
- 在庫が余って鮮度が落ちる
- 新鮮でない料理を提供することになり、リピーターが減る
結果として、「原価が上がる」「売上が下がる」という二重のダメージにつながります。
個人店で導入されていない現状
大手チェーンでは当たり前に行われている定数管理ですが、個人経営の飲食店では実践されていないケースが多いのが実情です。
しかし、過去の売上データや季節変動を参考にすれば、 どのくらい仕入れるべきかは予測可能です。オープンしたばかりのお店でも「予想ベース」からスタートし、実績に合わせて調整すれば十分対応できます。
原価率を抑える方法②:業者を定期的に見直す
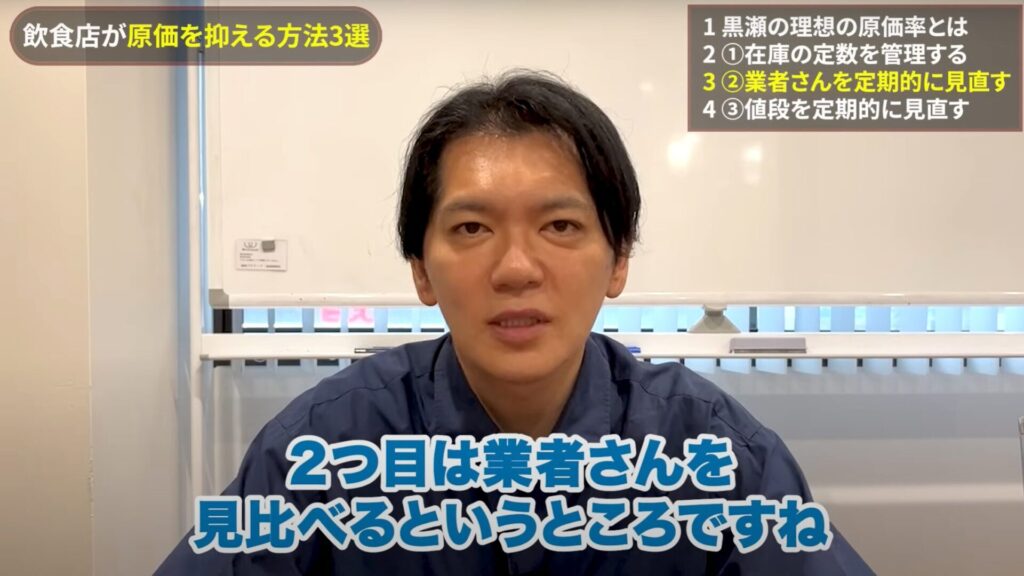
業者ごとに得意分野がある
飲食店オーナーが最初に契約した業者を「ずっと使い続ける」というケースは少なくありません。
しかし、実際には業者ごとに得意分野があり、
- A社 → 肉類が得意
- B社 → 野菜が安くて品質が良い
といった違いがあります。
そのため、「特定の食材だけ別の業者に切り替えること」が原価率を抑える大きなポイントになります。
良い業者の探し方
食材の仕入れ価格はネットにはほとんど出ていません。そこで有効なのが、経営者仲間からの情報交換です。
- 「今この食材、いくらで仕入れてる?」と聞く
- プロデュース先や知り合いオーナーから紹介してもらう
こうしたネットワークを活用することで、より安く・品質の良い業者を見つけることができます。
目安としては、最低でも2ヶ月に1回は業者を見直すことです。
原価率を抑える方法③:売値の調整(値付け戦略)

値上げは最終手段?
値上げは誰でもできることから、基本的には推奨されません。
ただし、お客様が納得できる値上げであれば問題ありません。
例えば:
- 土日だけ値上げする「ダイナミックプライシング」
- ニュースで米価高騰が話題になった時期に定食の価格を調整する
- 銀座のような立地で「エリア価格」として上乗せする
こうした、お客様が理由を理解できる値上げは不満につながりにくいのです。
値上げの判断基準
値上げを行う際は、周りの動向をチェックすることが重要です。
- 周囲の競合店も同じタイミングで値上げしているか?
- 相場感に合った価格か?
牛丼チェーンが横並びで価格調整をするように、個人店でも市場に合わせた値付けが成功のカギとなります。
まとめ:原価率を抑える3つのステップ
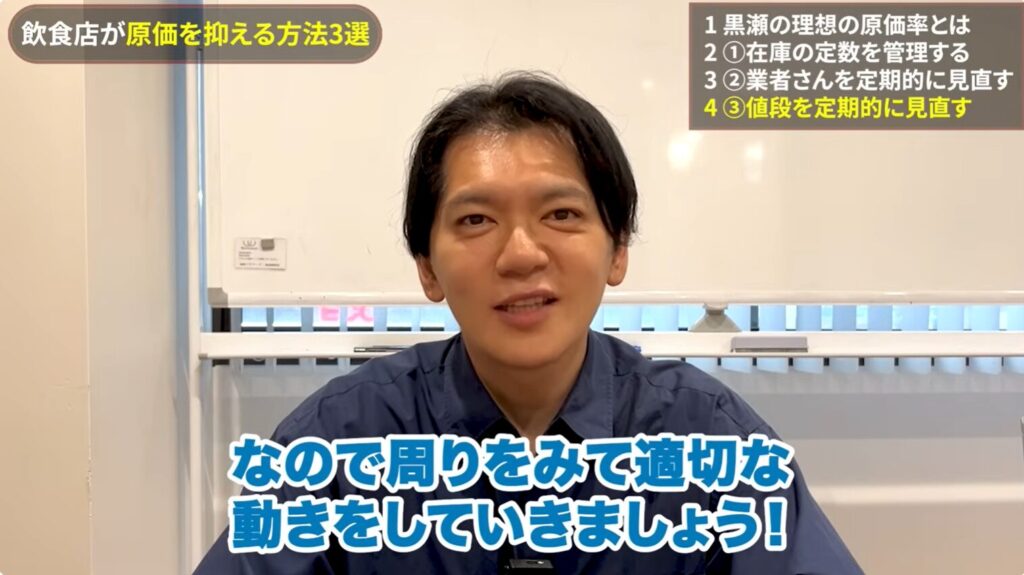
今回ご紹介した、原価率を抑える方法は以下の3つです。
- 在庫の定数管理を徹底する
- 業者を定期的に見直す
- 売値を市場に合わせて調整する
いずれも特別なスキルや投資が必要なわけではなく、 「経営者の意識」さえ変えれば実行できる施策です。
値上げラッシュの時代を乗り切るために、ぜひ今回の3つの方法を自店で取り入れてみてください。
原価率の抑え方について、より深く学ぶことができる環境を提供しています。ご興味がある方はぜひ公式LINEの登録をお願いします。