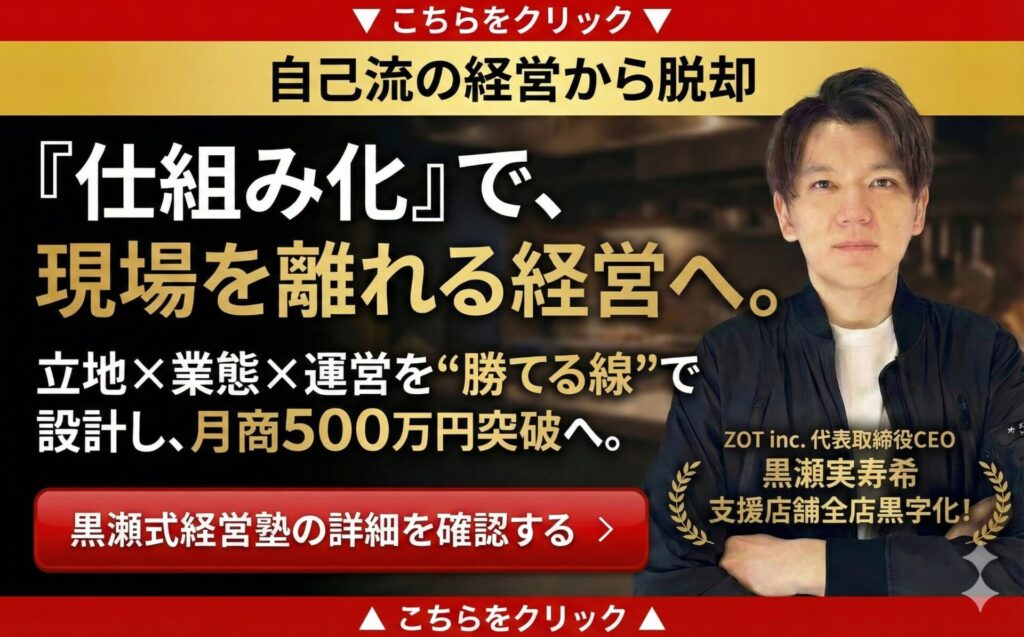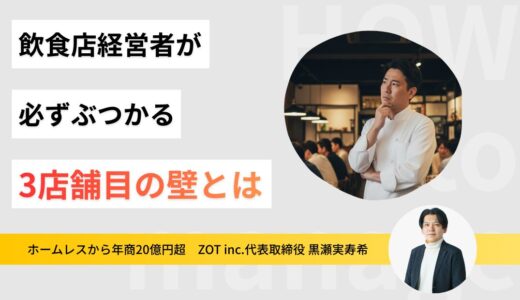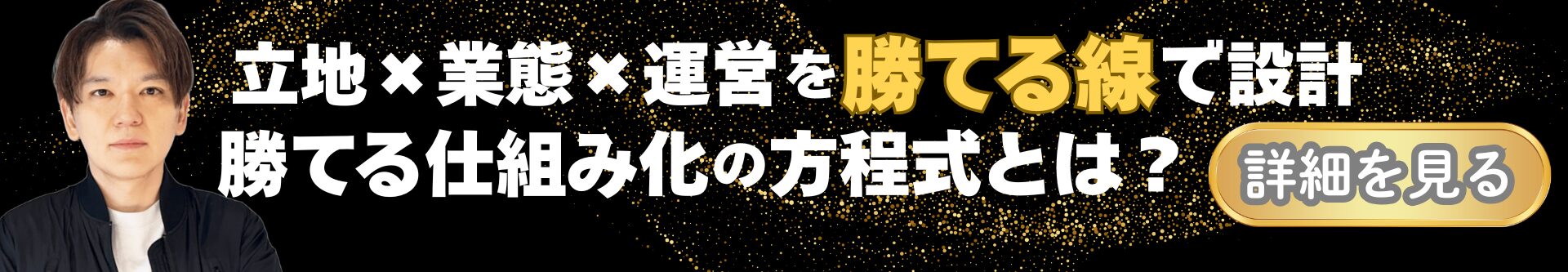繁盛する飲食店の共通点とは?繁盛させる6つの法則を解説!
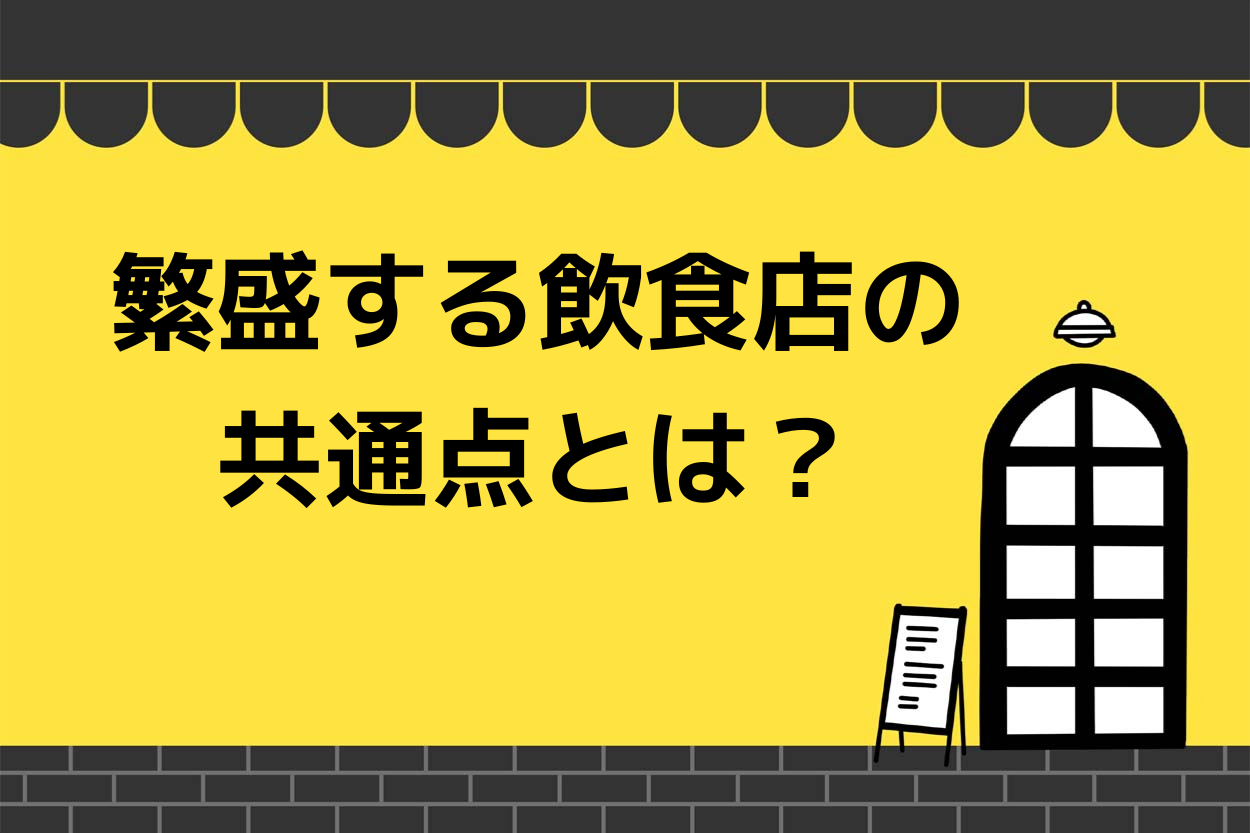
なぜ同じエリアで営業していても、繁盛する店とそうでない店があるのでしょうか?
この記事では、飲食店を繁盛させる6つの法則を解説します。
コンセプトの明確化、効果的なマーケティング、リピーターを増やす接客術など、売上を伸ばし成功するための具体的なポイントを紹介します。
飲食店経営を軌道に乗せたい方はぜひ参考にしてください。
本記事のリンクには広告を含んでいます。
繁盛する飲食店の6つの共通点

ここでは、繁盛店が実践している6つのポイントを詳しく解説します。
独自のコンセプトがある
繁盛する飲食店の多くは、競合にはない独自のコンセプトを持っています。
単に目新しいアイデアではなく、お客様の「隠れたニーズ」を満たすものであることが重要です。
飲食店でも、ターゲット層のライフスタイルや好みを深く理解し、競合が見落としているポイントを押さえたコンセプトを作ることが成功につながります。
独自性を打ち出すためには、単なるメニューの違いだけでなく、店舗のデザイン、接客スタイル、サービス内容など、トータルで統一感のあるコンセプトを構築することが大切です。
他店と差別化された魅力を持つことで、リピーターを増やし、安定した集客につなげることができます。
正しい立地選定ができている
繁盛する飲食店の多くは立地選定を慎重に行い、ターゲットに最適な場所で営業しています。
どれだけ優れた料理やサービスを提供していても、立地が悪ければ集客に苦戦し、売上を伸ばすのが困難です。
反対に適切な立地を選べば、新規顧客の獲得がしやすくなり、リピーターの増加にもつながります。
立地選定では「ターゲット層の動向を把握すること」が重要です。
以下の記事では、立地の悪い飲食店の集客方法を解説しています。
マーケティングに力を入れている
繁盛する飲食店はただ美味しい料理を提供するだけでなく、効果的なマーケティング戦略を駆使しています。
競争が激しい飲食業界では適切なマーケティング施策を行うことで、新規顧客の獲得やリピーターの増加が可能です。
以下の記事では飲食店のマーケティング戦略を解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
リピート率を上げる接客・サービス
飲食店の売上を安定させるには、新規顧客の獲得だけでなく、QSC(品質・サービス・清潔さ) を意識した店舗運営が重要です。
QSCを高水準で維持することで、顧客満足度が向上し、リピーターの増加につながります。
接客の質はリピート率を左右するため、スタッフ教育やサービス改善 を徹底することが必要です。
明るい挨拶や丁寧な対応を標準化し、どのスタッフでも均一なサービスを提供できる体制を整えましょう。
また、店内の清潔さを保つ こともQSCの重要な要素であり、快適な空間が再来店の決め手になります。
さらに、ポイントカードやクーポン、限定メニューなど再来店を促す施策も有効です。QSCを意識しながら接客・サービスを向上させ、リピーターを増やすことで、安定した経営につなげましょう。
人気メニューと高利益メニューの効果的な配置
飲食店の売上を伸ばすためには、メニューの構成を戦略的に考えることが重要です。
人気メニューと高利益メニューの配置を工夫することで、顧客満足度を向上させながら収益を最大化できます。
人気メニューは集客力が高く多くの顧客が注文するため、適切に配置することで客単価の向上が期待できます。
高利益メニューは利益率が高いため、売上を効率的に伸ばすためには戦略的な設計が不可欠です。
売上データを活用して、注文が多いメニューと利益率が高いメニューを明確に分類することが必要になります。
POSシステムなどを用いてデータを分析し、どの料理が最も支持されているのか、またどのメニューが収益性に優れているのかを把握しましょう。
そのうえで、人気メニューをメニュー表の目立つ位置に配置し、注文率を維持しながら高利益メニューへと誘導するレイアウトを構築します。
セットメニューの提案や高利益メニューの横に人気メニューを配置することで、顧客の注文を促すことが可能です。
季節限定メニューや話題性のある料理を定期的に導入することで、リピーターの来店意欲を高めることができます。
これらの施策を組み合わせることで飲食店の売上を安定させ、長期的な繁盛につなげることができます。
シェフからレシピを買う
レシピは、シェフから購入することも可能です。
業界のトップオブトップの人たちに教えてもらうことでお客様や調理者にとって付加価値の高いレシピを入手できる可能性があります。
集客に繋がる内装を意識している
美味しい料理を提供していても、内装が魅力的でなければ新規顧客の獲得やリピーターの増加は難しくなります。
特に、ユニバーサルデザイン を意識した内装は、年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが快適に利用できる環境を提供するため、幅広い客層の支持を得やすくなります。
また、SNSの影響で「写真映えする店」が話題になりやすく、洗練された内装や適切な照明は集客に直結します。
逆に、動線が悪かったり、使いにくいレイアウトでは顧客満足度が下がります。
ユニバーサルデザインを取り入れることで、機能性と魅力を両立させ、長く愛される店舗を実現できるのです。
内装について詳しく確認したい場合は、以下の記事をご確認ください。
小さいお店を繁盛させる法則

飲食店の成功には、店舗の規模は関係ありません。
小さな店舗でも特徴を活かした経営戦略を立てることで、繁盛店にすることが可能です。
むしろ、小規模だからこそオーナーの個性を強く打ち出し、差別化しやすいというメリットもあります。
重要なのは大型店と同じ土俵で戦うのではなく、小さな店舗ならではの強みを活かし独自のブランドを築くことです。
小規模店舗では「オーナーの魅力がそのまま店舗の魅力になる」と考えることが重要です。
お客様との距離が近く、オーナーのこだわりや価値観がダイレクトに伝わるため、ファンを獲得しやすいという特徴があります。
そのため、大手チェーンのように多くのメニューを提供するよりも、得意な料理やコンセプトを絞り込み、専門性を高めることが成功のポイントになります。
駅近の一等地でなくても特定の客層に支持されるコンセプトが確立されていれば、目的来店型の店舗として成功する可能性があります。
店舗の見せ方やデザインにも工夫が必要です。
小規模だからこそ、店内の雰囲気やブランディングを強く打ち出し、唯一無二の空間を演出することが重要になります。
内装の配色や照明の使い方を工夫し、ターゲット層に響く雰囲気を作り上げることで、SNSでの拡散や口コミによる集客につながります。
また、ターゲットとメッセージを明確にすることも重要です。
誰に向けた店なのか、どんな価値を提供するのかをはっきりさせることで、共感する顧客が増えリピーターの獲得につながります。
小さな店舗はその規模を活かした戦略を立てることで、繁盛店へと成長させることが可能です。
オーナーの個性を前面に出し、特化型のメニューとブランディングを強化し、ターゲット層にしっかりとアプローチすることが成功のカギとなるので意識していきましょう。
潰れる飲食店の共通点

飲食店の経営は簡単ではなく、多くの店舗が数年以内に閉店へと追い込まれています。
開業後3年以内に約70%、10年以内には約90%の店舗が廃業するとも言われ、飲食業界の競争の激しさがうかがえます。
以下は飲食店が潰れる前に見られる9つの前兆です。
- 提供時間が遅い
- 入れ替わりが激しいテナントで営業している
- 清潔感がない
- 割引やキャンペーンを多く行っている
- コンセプト設計が曖昧
- メインメニューの注文数が少ない
- SNSの活用ができていない
- 原価率を管理できていない
- 店内スペースを無駄遣いしている
潰れる飲食店にはいくつかの共通点があり、それを回避するための対策を講じることで生き残る可能性を高めることができます。
繁盛店の坪単価売上

飲食店の売上を評価する指標の一つに「坪単価売上」があります。
この数値は1坪あたりの月間売上を示し、繁盛店かどうかを判断する際の重要な基準になります。
一般的な居酒屋では坪単価売上が20万円程度で標準的な店舗、30万円を超えると繁盛店とされています。
逆に10万円を下回ると、経営の持続が難しくなる可能性が高いため、早急な改善が必要になります。
坪単価売上を向上させるためには、「客単価の向上」と「回転率の向上」が欠かせません。
客単価を上げる方法としては、メニューの見直しやセットメニューの導入、高付加価値の料理提供が有効です。
料理の品質を向上させることで単価を自然に引き上げる手法は、顧客満足度を損なわずに売上を増やすことができます。
サイドメニューの提案やドリンクのペアリングを活用することで、1回の注文金額を増やす工夫も求められます。
繁盛店を目指すためには坪単価売上の目標を明確にし、客単価と回転率の両面から戦略を立てることが不可欠です。
飲食店経営の安定化には、売上向上のためのデータ分析と継続的な改善が欠かせません。
飲食のプロ黒瀬が売上を上げる施策を解説
ROLANDさんのイタリアン店舗での調査をもとに、飲食のプロ黒瀬が売上を上げる施策を解説しています。
外観や値段のつけ方に関してコメントしているので、ご興味ある方はぜひ確認してみてください。
繁盛するお店の戦略を実践しよう

飲食店を繁盛させるには、短期的な施策だけでなく、長期的な視点で戦略を立て、一貫して実行することが重要です。
すぐに効果が出る集客施策もありますが、それだけに頼ると持続的な成長は難しくなります。
他店と差別化できる独自のコンセプトを持ち、ターゲット層に響く価値を提供し続けることで、リピーターを増やし、安定した経営を実現できるのです。
しかし、具体的にどのような方法を行えばいいのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
飲食店経営の学校では、飲食店マーケティングに役立てられる内容などを提供しています。