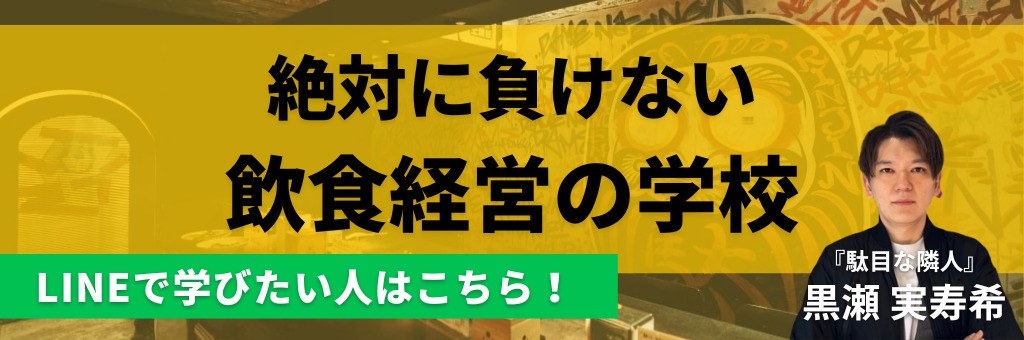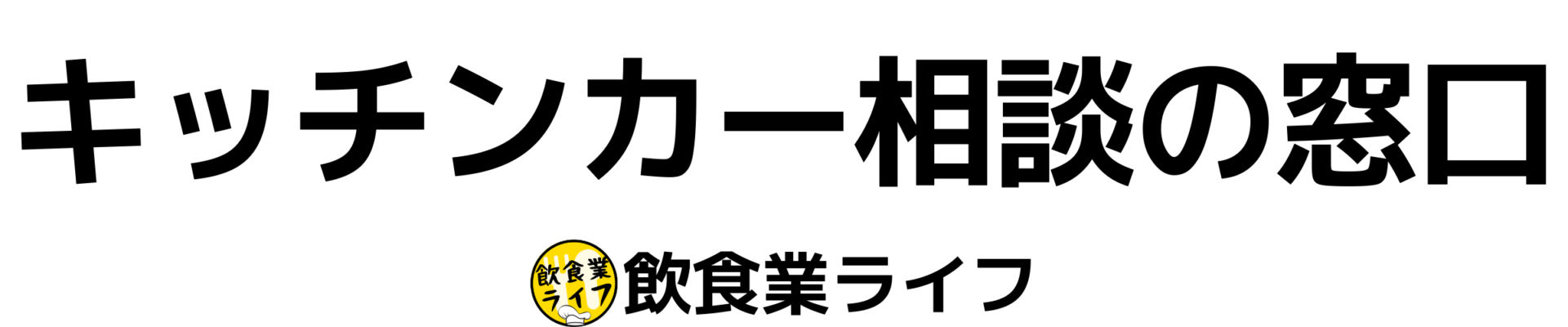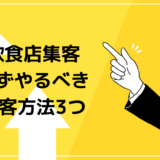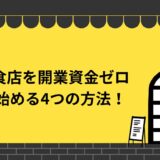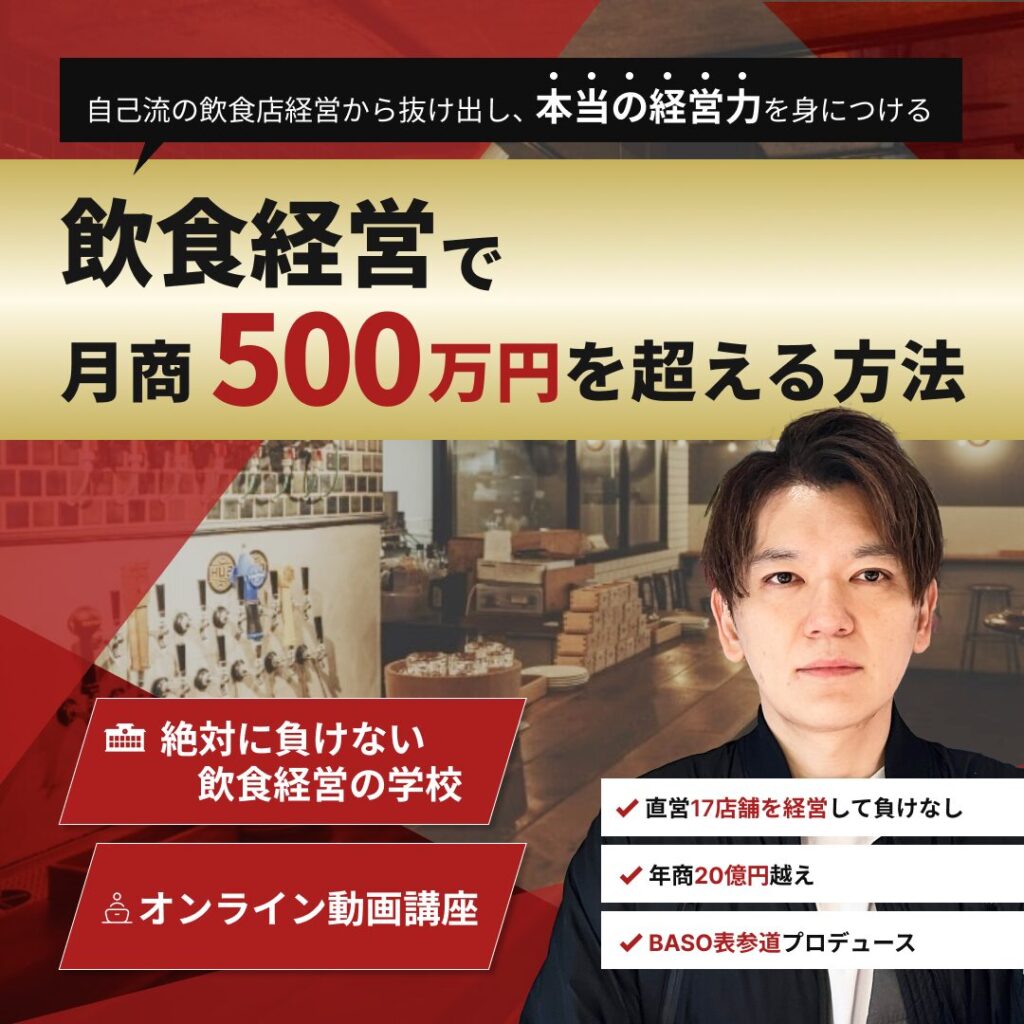「飲食店の開業に必要な資金ってどれくらい?」
「飲食店の開業に必要な資格や届出がわからない…」
「飲食店を開業するためのお金がないんだけど、融資を受けられる?」
本記事では上記の飲食店の開業準備に関する疑問やお悩みにお答えします。
飲食店を開業する場合に、必要な資金や資格などが分からず不安に思う方もいるでしょう。
しかし、必要なことが分かれば1つずつクリアしていくだけでよくなります。
今回は、飲食店開業に必要な資金や資格などについても具体的に解説します。
本記事のリンクには広告を含んでいます。
飲食店開業に必要なコンセプト作り

飲食店を開業するために、まず行うべきなのがコンセプト作りです。
コンセプトを明確にすれば、お店の方向性がブレずに開業後の経営ができるからです。
開業までの準備段階においても、店の外観、内装、メニュー、価格、ターゲットなど決めることはたくさんあります。
コンセプトが明確であれば、経営上の決断をしやすくなりますし、お店に一貫性を持たせられます。
繁盛しているお店は基本的に、明確なコンセプトを掲げている点が特徴です。
コンセプトが明確であると、お客さんにどんなサービスを提供するのかアピールできます。
お客さんにとっても、どんなお店でどんなサービスを受けられるのかを知るための判断材料となります。
コンセプトをまず考えることは、繁盛店を作るためのポイントとなるわけです。コンセプトを作る上で考えたいのは、「5W1H」です。
- 何を:どんなメニューを
- 誰に:どんな人に対して
- どこで:どの場所で
- いつ:どの時間帯に
- どのように:どんな空間でどんなふうに
頭の中で漠然と考えるよりも、上記の5つを紙に書き出すと効果的です。
5つの項目を埋めれば、自然とお店のコンセプトが決まるでしょう。
他店との差別化を図る点を、明確にするのがポイントです。
飲食店開業に必要な物件取得

飲食店の開業をするために、資金を調達する前に物件を確保しましょう。
理由として、融資を受ける時に事業計画書の提出が求められるからです。
事業計画書とは、出店場所や家賃、業種などをまとめた書類のことを言いいます。
自己資金だけでは開業できないため、銀行や日本政策金融公庫から融資を受けたいと考える方は必要になる書類です。
物件を見に行くときは、なるべく施工業者と一緒に回るといいでしょう。
イメージしている内装や外装を実現できそうか判断してもらえるからです。
物件は居抜き物件とスケルトン物件の2つに大きく分けられます。
居抜き物件
居抜き物件とは、以前飲食店を営んでいた物件であり、営業するために必要な設備が揃っているケースがあります。
居抜き物件の場合、設備投資費用などを抑えやすい傾向にあります。
スケルトン物件
スケルトン物件とは、内装が一切されておらず、コンクリートがむき出しになった状態の物件のことです。
スケルトン物件の場合、内装や設備投資などを1からする必要があるので、費用がかかりやすい点が特徴です。
また、以前のお店の内装をそのまま使った居抜き物件を「造作譲渡物件」と言います。
造作譲渡物件の場合、以前のお店は経営がうまく行かずに退去した可能性が高いと言えるでしょう。
そのため、開業して間もない頃は、周辺の方からいいイメージを持たれないリスクがあります。
希望する物件を見つけた場合、仮押さえしておきましょう。
飲食店開業に必要な資金

飲食店開業するために、具体的にどんな資金が必要になるのか抑えておきましょう。
ここから、開業するために必要な資金について具体的に解説します。
飲食店開業に必要な資金:①物件取得費用
飲食店を開業するためには、物件取得費用が必要となります。
物件取得費用とは、物件を契約する時に必要になる金額のことです。
物件を契約する時には、家賃の他にも保証金などのお金を支払う必要があります。
もし、家賃20万円の物件を契約する場合、目安として下記の費用が必要です。
| 物件取得費用の内訳 | 費用 | 内容 |
| 保証金 | 200万円(家賃10ヶ月分) | 大家さんに払う費用 |
| 礼金 | 20万円(家賃1ヶ月分) | 大家さんに払う費用 |
| 仲介手数料 | 20万円(家賃1ヶ月分) | 不動産会社に払う費用 |
| 前家賃 | 40万円(家賃2ヶ月分) | 大家さんに払う費用 |
上記の表の通り、家賃20万円の物件の場合、280万円くらいかかるケースがあると知っておくといいでしょう。
物件によっては、保証金が家賃の10ヶ月分以上になるケースもあります。
飲食店開業に必要な資金:②店舗投資費用
店舗設備費用とは、お店の設備を整える上で必要になる費用をいいます。
特にスケルトン物件の場合、コンクリートや配管などがむき出しになっているのが特徴です。
たくさんの工事が必要になるので、費用がかかりやすくなります。
店舗設備投資とは、具体的に下記の表のとおりです。
| 店舗設備費用の内訳 | 内容 |
| 厨房設備費 | ・シンク ・ガス台 ・調理台 ・冷蔵庫 ・オーブンなど |
| 外装費 | ・看板 ・外壁 ・正面のデザイン |
| 内装・設計費 | ・壁 ・床 ・天井 ・水回り ・ガス ・電気 |
| 備品費 | ・調理道具や洗剤など消耗品 |
| POSレジ導入費 | ・レジ |
| 販売促進費 | ・チラシ ・WEBの広告など |
| アルバイト募集費 | ・チラシ ・求人サイト |
参考:MIC store
上記の通り、大きく分けて7つの費用が発生します。
費用の相場に関しては、業者や物件等によって大きく変わるので一概には言えませんが、
目安でいうと、20坪のカフェだとおよそ600~1200万円と言われています。
なるべく費用を抑えるには、居抜き物件を選んだりDIYをしたりする方法があります。
また、中古の厨房機器を取得するなど工夫するといいでしょう。
飲食店開業に必要な資金:③運転資金
運転資金とは、家賃や光熱費、生活費、仕入れ代等、主に開業してから必要になる費用です。
目安としては、半年分の運転資金を用意しておきましょう。
なぜなら、飲食店を開業してから半年くらいは、一般的に赤字になるケースが多いといわれるからです。
つまり、お店が軌道に乗るまでには半年くらい時間が必要になるわけです。
運転資金が足りない場合、倒産せざるを得ない可能性もあります。
そのため、事前に売上見込を厳しめに設定しておくのも1つの方法です。
運転資金が十分にあれば、比較的心の余裕をもって営業できるでしょう。
飲食店開業に必要な資金の調達方法

自己資金だけでは開業資金が足りなくても、銀行から融資を受けるなどの方法があります。
ここから、開業資金を調達する方法を具体的に解説します。
資金の調達方法:①融資を受ける
開業資金を調達する方法として、融資を受ける方法があります。
融資を受けられるのは、具体的に下記の2つの金融機関です。
- 銀行
- 日本政策金融公庫
ここから具体的に紹介します。
・銀行
銀行での融資を受けるには実績が必要となるので、初めて開業する方の場合、審査に通らない可能性が高くなります。
そこで、利用を検討したいのが信用保証協会付きの融資です。
もし銀行にお金を返済できない場合、信用保証協会が代わりに代金を立て替えてくれる点が特徴になります。
そのため、銀行からの融資を受けやすくなるわけです。
ただし、お金を建て替えてもらった場合、信用保証協会に返済する義務が発生する点は注意が必要です。
信用保証協会付きの融資を受けた場合、お金を受け取れるのは基本的に開業した後になります。
そのため、運転資金として利用する点を念頭に置いておきましょう。
・日本政策金融公庫
日本政策金融公庫とは、政府系の金融機関であり国が100%出資している点が特徴です。
民間の金融機関とは異なるので、初めて開業する方でも融資を受けやすくなっています。
日本政策金融公庫の融資の中には、無担保・無保証人でも融資を受けられる制度があります。
また、自己資金0円の方も融資を受けられる可能性があるなど、初めて開業する方をサポートしてくれるでしょう。
日本政策金融公庫の融資に限りませんが、融資を受けるには創業計画書の作成が求められます。
所定のフォーマットに記載した上で、提出しましょう。
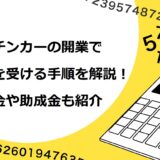 キッチンカーの開業で融資を受ける手順を7ステップで解説!補助金や助成金も紹介
キッチンカーの開業で融資を受ける手順を7ステップで解説!補助金や助成金も紹介
資金の調達方法:②補助金・助成金を利用する
飲食店開業の資金調達手段として、補助金や助成金を活用する方法があります。
補助金や助成金を受けられれば、お店を営業するための助けとなるでしょう。
補助金と助成金の違いは、具体的に下記のとおりです。
| 補助金 | 助成金 | |
| 実施機関 | 経済産業省・中小企業庁 | 厚生労働省 |
| 対象者 | 企業、個人事業主 | 企業、個人事業主、民間団体 |
| 財源 | 税金 | 雇用保険料 |
| 審査 | ある | ない場合もある |
| 募集期間 | 1ヶ月以内 | 半年や通年 |
出典:FOOD GYM
上記の通り、補助金や助成金は国が支給するお金であり、対象者が異なります。
審査の有無や募集期間などが違う点が特徴です。
 キッチンカーでの開業に使える6つの補助金・助成金を紹介!開業にかかる資金も4つに分けて解説
キッチンカーでの開業に使える6つの補助金・助成金を紹介!開業にかかる資金も4つに分けて解説
飲食店開業に必要になる資格・届出

飲食店を開業するには、資格取得や届出などが求められます。
必要になる資格は、具体的に下記のとおりです。
| 飲食店開業に必要な資格・届出 | 内容 |
| 食品衛生責任者 | ・営業するお店のスタッフの中で、最低1名は取得する必要がある ・自治体の食品衛生協会が主催する講習を受けると取得できる ・調理師や栄養士の資格所持者は自動的に取得可能 ・費用は1万円ほど |
| 防火管理者 | ・お店の収容人数(スタッフを含む)が30人を超える場合に必要 ・消防署で講習を受けると取得できる ・【延床面積が300平米以上の場合】甲種防火管理者:1日で取得 ・【延床面積が30平米未満の場合】乙種防火管理者:2日で取得 ・営業開始までに提出する |
| 個人事業等の開廃業等届出書 | ・開業届のこと ・個人で開業する場合、開業日から1ヶ月以内に税務署に提出する ・同時に青色申告承諾書を提出すれば、青色申告を受けられる |
| 火を使用する設備等の設置届 | ・火気を使用する場合、消防署に提出する必要がある書類 ・オープン当日までに提出する |
| 食品営業許可申請 | ・店舗完成の10日ほど前までに保健所に提出する書類 ・保健所に事前に申請した上で、後日保健所の検査が入る |
| 深夜における酒類提供飲食営業開始届出書 | ・深夜営業届のこと ・午前0時を過ぎても酒類を提供する飲食店が警察署に提出する書類 ※牛丼屋やそば屋など、飲食をメインとする飲食店がお酒を提供する場合、提出しなくてもよい ・営業開始の10日前までに提出する |
| 風俗営業許可申請 | ・スナック等客に接待行為を行う飲食店や、バーなどの低照度飲食店が、警察に提出する書類 ・営業開始の2ヶ月前までに提出する |
食品衛生責任者や食品営業許可申請など、必要な手続きは多くあります。
1つひとつクリアしていきましょう。
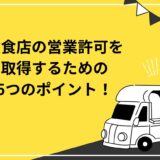 飲食店に必要な営業許可!取得するまでの5つのポイントを解説します!
飲食店に必要な営業許可!取得するまでの5つのポイントを解説します!
十分な準備で、失敗しない飲食店を作り上げましょう

ここまで、飲食店開業に必要な資格や資金などについて解説してきました。
本記事のまとめは下記のとおりです。
- 飲食店を開業するには、コンセプトを明確にするのがポイントである
- 飲食店を開業する場合、資金を調達する前に物件を取得すると良い
- 飲食店を開業するためには、物件取得や設備投資等の費用が必要である
- 飲食店開業するための資金は、銀行や日本政策金融公庫から融資や補助金を活用するのも良い
- 飲食店を開業するために必要な資格とは、食品衛生責任者の資格などである
本記事を参考に、飲食店の開業について理解していただければ幸いです。