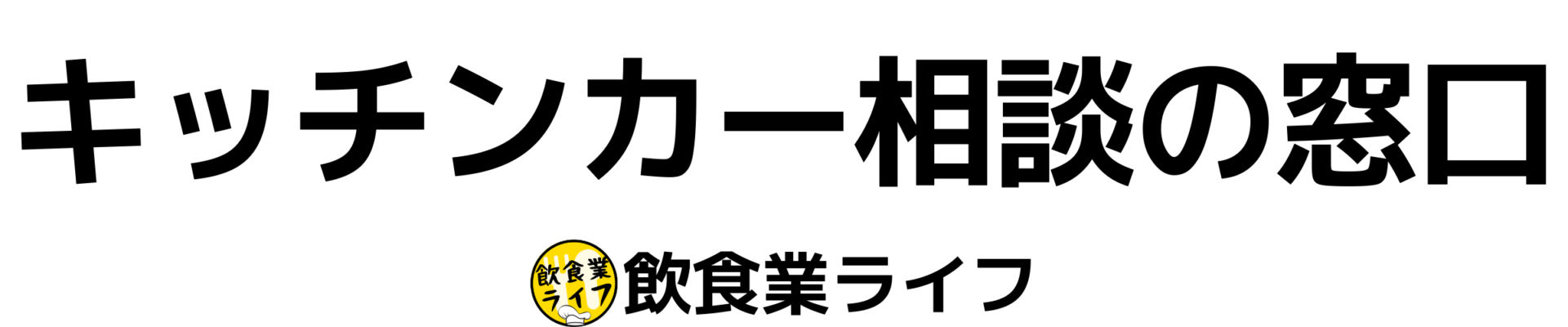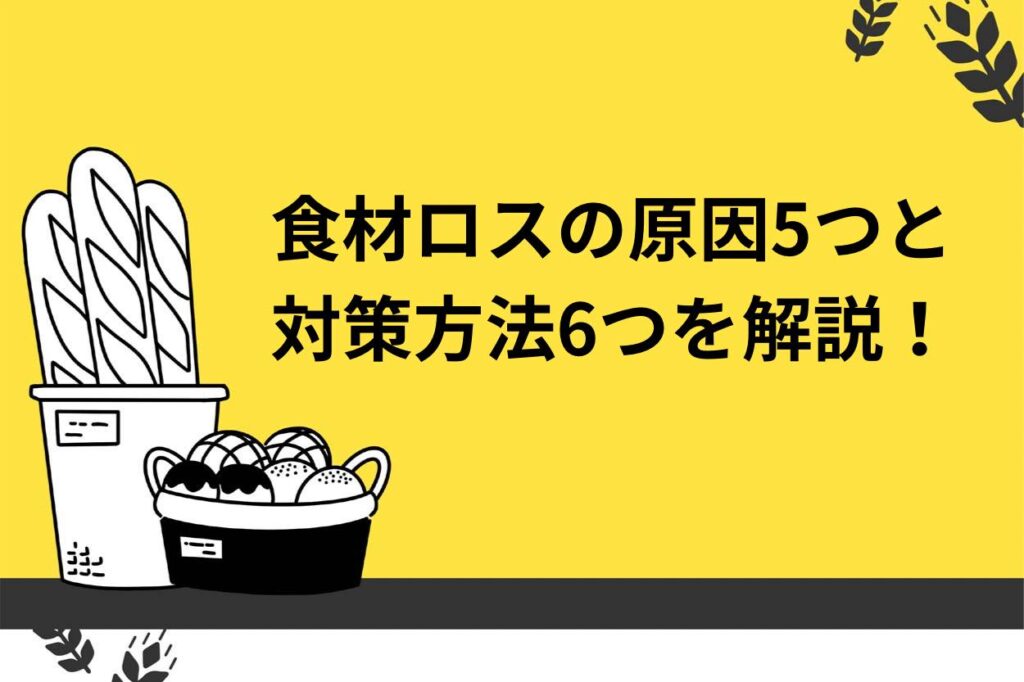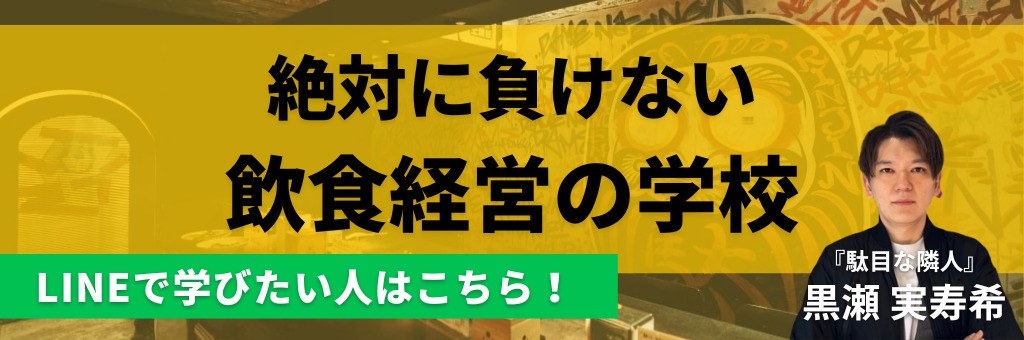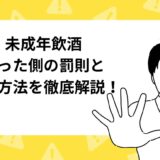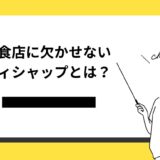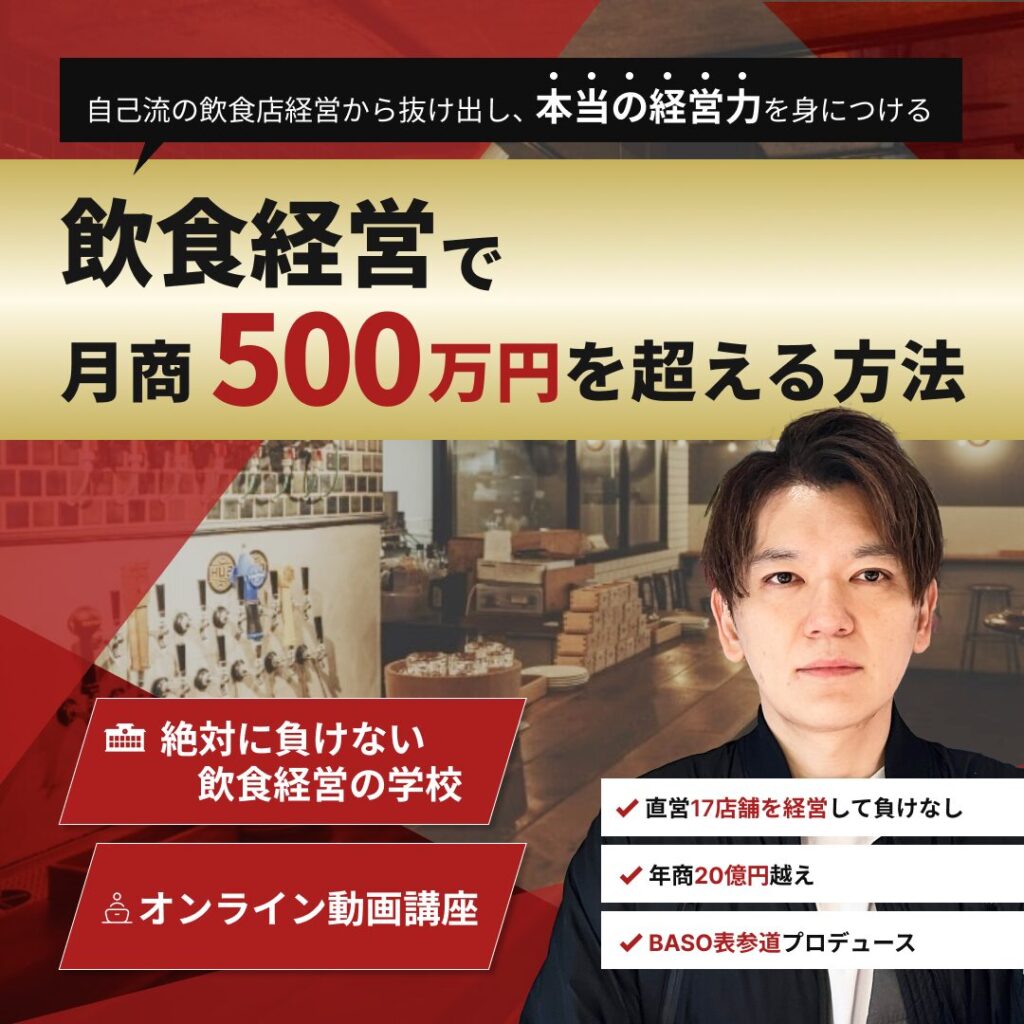「飲食店の食材ロスの原因って何?」
「飲食店で食材ロスを効果的に減らす方法が知りたい」
「飲食店を営業するために、食材ロスを減らすのは重要?」
本記事では上記の疑問や要望などにお応えします。
飲食店を開業するにあたり、食材ロスを減らす具体的な対策方法を知っておきたいと思う方もいるでしょう。
また、食材ロスが経営に与える重要性について、よくわからない方もいるかも知れません。
そこでここから、飲食店の食材ロスの現状、原因と対策法を具体的に解説します。
本記事のリンクには広告を含んでいます。
食材ロスの現状

食材ロスは日本だけでなく、世界的に見ても大きな問題となっているのが特徴です。
家庭や飲食店から多くの食材ロスが出る一方で、食糧難で困っている人もいるのが現状です。
ここから、食材ロスの現状について詳しく解説します。
世界的な問題になっている
食材ロスとは、本来であれば食べられるはずの食材が、さまざまな理由によって捨てられることをいいます。
FAO(国際連合食糧農業機関)の調査によると、世界中で食べられずに捨てられる食材の割合は1年で約13億t になることが判明しています。
13億t の食材とは、食糧生産量の3分の1になる計算です。
一方で、世界にいる人の約9人に1人は、栄養不足の問題を抱えているのが現状です。
日本でも1年で東京ドーム5杯分の食材を捨てている
日本の場合、2017年の食材ロスは1年間に612万t で東京ドーム5杯分に相当します。
国民1人あたりで換算すると、毎日お茶碗1杯分の食材を捨てていることになります。
日本での食材ロスの原因は、具体的に以下の2つに分けられる点が特徴です。
- 事業系:スーパーやコンビニなどの売れ残りや飲食店の食べ残しなど
- 家庭系:家庭での料理の作りすぎや賞味期限切れなど
事業系の食材ロスは328万t、家庭系は284万tで、事業系のほうが多くの食品を廃棄しています。
飲食店の場合、食材ロスの原因第1位は「お客さんの食べ残し(58%)」第2位は「仕込みすぎ(39%)」であると判明しました。
出典:農林水産省
「しょうがないのでは」と思うかも知れませんが、いずれもお店側の姿勢で対策できると言えます。
食材ロスの対策をしないと、食材もお金もどちらも無駄にすることになり、開業前にしっかり理解しておくのがポイントです。
飲食店で食材ロスになる原因5つ

飲食店で食材ロスになる原因は、以下のように特定できます。
- お客さんが食べ残している
- 料理を仕込みすぎている
- 食材を仕入れすぎている
- オーダーミスが発生している
- 調理で失敗している
ここから、食材ロスになる原因について具体的に解説します。
①お客さんが食べ残している
飲食店で食材ロスになる原因として、お客さんの食べ残しがあげられます。
前述の通り、飲食店の食材ロスの中で最も割合を占めるのが食べ残しであり、対策が求められています。
食べる量はお客さんによって異なるのが基本になりますが、毎回のように料理を残される場合は、さまざまな点を見直す必要があるでしょう。
見直すとよいポイントは、具体的に下記の通りです。
- メニュー内容
- 盛り付ける量
- 味など
特に、多すぎる量を提供している可能性が高く、最初に見直すのが賢明です。
②料理を仕込みすぎている
飲食店で食材ロスになる原因は、仕込み量が多すぎる点です。
完全予約制の飲食店以外の場合、1日にどのくらいのお客さんが来るのかを正確に把握できないためです。
お客さんの来る数が予想よりも少ない場合、食材ロスになる可能性があります。
仕込み量を正確に予測するには、季節やイベント、曜日や時間などによるデータを分析するのが効果的な方法です。
開業した頃は正確に予測しにくいかも知れませんが、天気予報や地域のイベントなどに合わせて、仕込み量の微調整が求められます。
③食材を仕入れすぎている
飲食店で食材ロスになる原因として、食材を仕入れすぎている点があげられます。
特に、肉や野菜、果物などの生鮮食品の場合は賞味期限が短い傾向にあり、余らせたり保存方法が不適切だったりすると食材ロスになりやすい点が特徴です。
ある程度の売上予測を立てたうえで、適正な量を仕入れるのがポイントになります。
数量を予測したり計算したりするのは面倒かもしれませんが、食材ロスを減らし売上を上げることにもつながります。
仕入れ量を適正にするためには、仕入れの担当者を固定したり、食品別に仕入れ量のマニュアルを作成したりするのも1つの方法です。
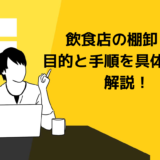 飲食店の棚卸しで浮き彫りになる経営上の問題点とは?在庫管理のポイントを解説!
飲食店の棚卸しで浮き彫りになる経営上の問題点とは?在庫管理のポイントを解説!
④オーダーミスが発生している
飲食店で食材ロスになる原因として、オーダーを取るときのミスがあげられます。
オーダーミスを起こすと、料理を捨てたうえで1から作り直しになるケースがあるためです。
オーダーミスが起こる原因は、具体的に以下の通りです。
- スタッフの聞き間違い
- お客さんの勘違い
スタッフが料理名を間違えるだけでなく、お客さんが勘違いするケースもあるのが特徴です。
オーダーミスを対策するには、注文時に確認を徹底するのが基本ですが、業態や時間帯によっては確認しにくいかも知れません。
タブレットやQRコードなどによる注文方式を導入するのも1つの方法で、注文を聞きに行く手間や時間も削減できる点がメリットになります。
⑤調理で失敗している
飲食店で食材ロスになる原因として、調理中に失敗する点があげられます。
調理中の失敗は誰しも経験があるでしょうが、食材が無駄になったり、提供する時間が遅くなったりとさまざまな悪循環を招きます。
どれほど急いでいるときでも、落ち着いて作業することが求められるでしょう。
もし調理中に何度もスタッフが失敗する場合、ポジションを見直したり、原因と対策を考えてもらったりするのが1つの方法です。
飲食店の食材ロスの対策法6つ

飲食店で食材ロスを減らすために効果的な方法として、以下の6つがあげられます。
- 料理の出すタイミングを考える
- 適切な量を注文してもらえるように工夫する
- メニューを見直す
- 残した料理を持ち帰ってもらう
- 適正量を把握し正確に仕入れる
- 食材に応じた保管方法を実施する
ここから、食材ロスを対策する方法について具体的に解説します。
①料理を提供するタイミングを考える
食材ロスを対策するには、料理を提供するタイミングを考えましょう。
一般的に、作りたての料理が最も美味しいとされているためです。
熱い料理は熱いうちに提供し、冷たい料理は冷たいうちに提供することを実践するのがポイントになります。
当たり前のことかも知れませんが、お客さんに喜ばれる可能性をあげられ、食材ロスを減らす効果が期待できます。
1度に多くのメニューを提供すると、時間の経過とともに味や風味が落ちる原因になり、注意が必要です。
お客さんの年齢層や食べるスピードなどに合わせて料理を提供するのも、ポイントの1つになるでしょう。
最も美味しく食べられるタイミングで料理を提供すれば、食材ロスを減らす可能性が高くなります。
②適切な量を注文してもらえるように工夫する
飲食店で食材ロスを対策するには、お客さんから適切な量を注文してもらえるように、お店側から訴えかける点があげられます。
前述の通り、飲食店の食材ロスの原因の1位は、お客さんの食べ残しであるためです。
適切な量を注文してもらうためにできることは、具体的に下記の通りです。
- メニューに写真を載せる
- 注文数が多い場合にアドバイスする
メニュー表に文字のみで書かれている場合、どのくらいの量が提供されるのかがわかりにくくなります。
また、団体のお客さんの場合、料理を注文しすぎるケースが多い傾向にあります。
そこで、メニュー表に写真を載せたり、一旦注文をストップして様子を見てもらったりするなどの対策が効果的になるでしょう。
③メニューを見直す
飲食店で食材ロスを対策する方法として、提供する料理の量を見直す点があげられます。
毎回のように料理が残される場合、多すぎる量を提供している可能性があるためです。
メニューの見直し方法は、具体的に下記の通りです。
- 料理の量を3種類(小盛り、普通、大盛り)(S、M、L)から選べるようにする
- 味を見直す
多く食べられる方や少食の方など、お客さんによって食べられる量は違うのは当たり前です。
体調や体質などに応じて量を選べるようにすれば、食べ残しを減らせる可能性があります。
また、提供する量を減らしても残される場合、料理が美味しくないと思われている可能性があります。
調理方法や食材を見直したり、メニューから外したりするなどが効果的な方法になるでしょう。
④残した料理を持ち帰ってもらう
飲食店で食材ロスを対策する方法として、料理が残った場合、お客さんに持って帰ってもらうことがあげられます。
食中毒のリスクが高くなるものの、アメリカではお客さんの自己責任で持ち帰るのが一般的になりつつあるためです。
衛生面で細心の注意を払ったうえで、持ち帰ってもらうのも1つの方法になるでしょう。
もしお客さんに料理を持ち帰ってもらう場合、具体的に以下の点を押さえることが必要です。
- 食中毒のリスクや取り扱い方法などを十分に説明する
- 十分に加熱された食品のみ提供し、生の食材には応じない
- 清潔な容器に、清潔な箸などを使って入れる
- 水分を切り、早く冷えるように浅い容器に小分けする
- 外が暑いときは保冷剤をつけたり、持ち帰りを実施しないようにしたりする
- 料理の取り扱いの注意書きを添えるなど
出典:消費者庁・農林水産省・環境省・厚生労働省「食べ残しに取り組むにあたっての留意事項」
基本的に、調理から時間が経過するほど食中毒のリスクが高くなる傾向にあります。
時期や料理の状態などに応じて、持ち帰ってもらえるか慎重に判断する必要があります。
⑤適正量を把握し正確に仕入れる
飲食店で食材ロスを対策する方法として、適正量を仕入れる点があげられます。
適正量を見極めるためには、天気や曜日、イベントなどから総合的に判断することが求められ、勘に頼らないのがポイントです。
適正量の仕入れをするためには、具体的に以下の点がポイントになります。
- メニューごとに食材の必要量を計算する
- POSレジなどのデータから販売実績を割り出し、品切れを起こさない最低限の量を把握する
- 棚卸しを月に1回実施する
- 発注するときに、在庫量を正確に把握しておく
農林水産省では、以下の取組みが紹介されています。
- 近隣店舗での食材在庫情報を共有し、過不足を近隣店舗で補い合う
- ロットの大きい食材を仕入れる際に、料理人仲間と食材をシェアする
- カット野菜導入し余剰部分の仕入れを避ける
参考:農林水産省
仕入れ1つとっても、食材ロスの対策としてさまざまな工夫ができるといえます。
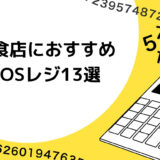 飲食店におすすめのPOSレジ比較13選|選ぶポイント・メリット・デメリットも徹底解説
飲食店におすすめのPOSレジ比較13選|選ぶポイント・メリット・デメリットも徹底解説
⑥食材に応じた保管方法を実施する
飲食店で食材ロスを対策するには、食材に応じて適切に保管する点がポイントになります。
食材を長持ちさせたり、よりよい状態でお客さんに提供したりする効果があるためです。
食材を保管するときの基本は、具体的に下記の通りです。
- 後入れ先出しを徹底する:賞味期限切れや傷みによる廃棄を減らすため
- 食材に合わせて、常温保管や冷蔵保管などを使い分ける:保存期間をながくするため
- 貯蔵庫の温度管理を習慣化する:温度異常による食材ロスを防ぐため
- 仕込み済み食材の場合、容器の消毒と空気に触れさせない点に注意する:よい状態で保管し、傷みにくくするため
冷蔵や冷凍など保管する温度を適切にしたり、先出し後入れなどの基本を実践したりすることで食材ロスを対策できるでしょう。
飲食店の開業後は食材ロスの削減により経営を安定させましょう

ここまで、飲食店の食材ロスの原因や対策方法などを解説してきました。
本記事のまとめは、具体的に下記の通りです。
- 1年間に13億トンが捨てられており、世界的な問題
- お客さんの食べ残しや料理の仕込み過ぎなどが原因
- 料理の提供タイミングを考えたりメニューを見直したりすることで対策可能
本記事を参考に、飲食店の食材ロスについて理解していただければ幸いです。