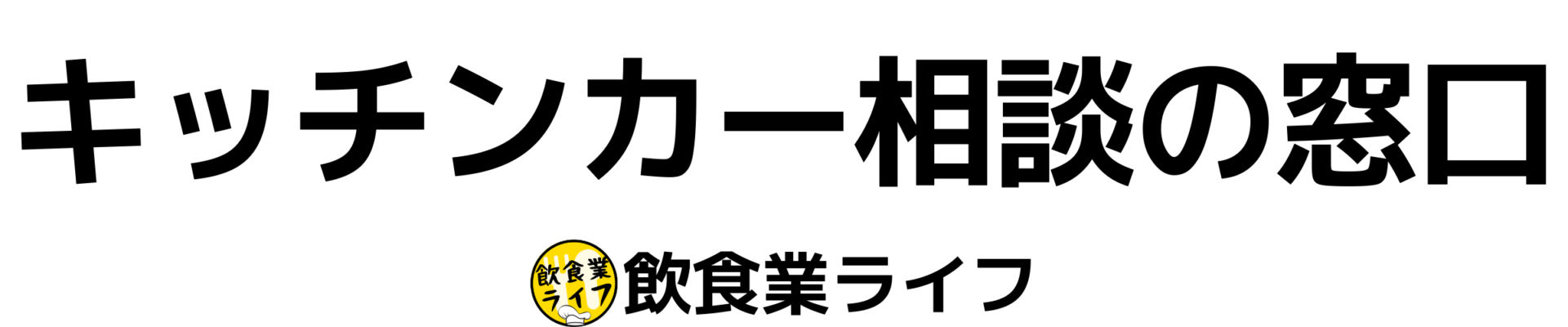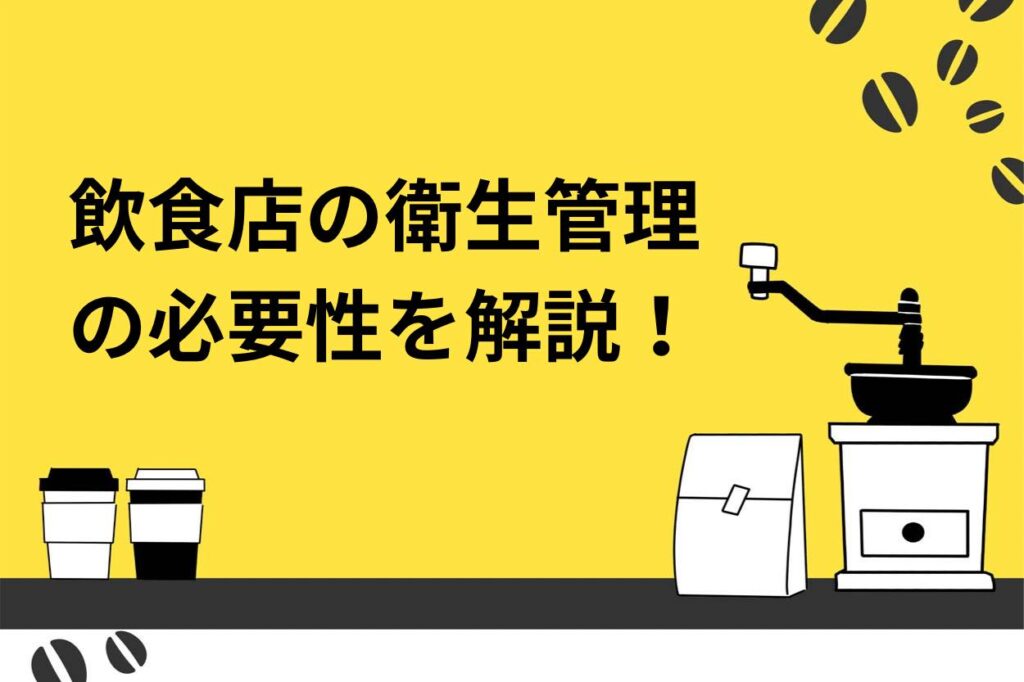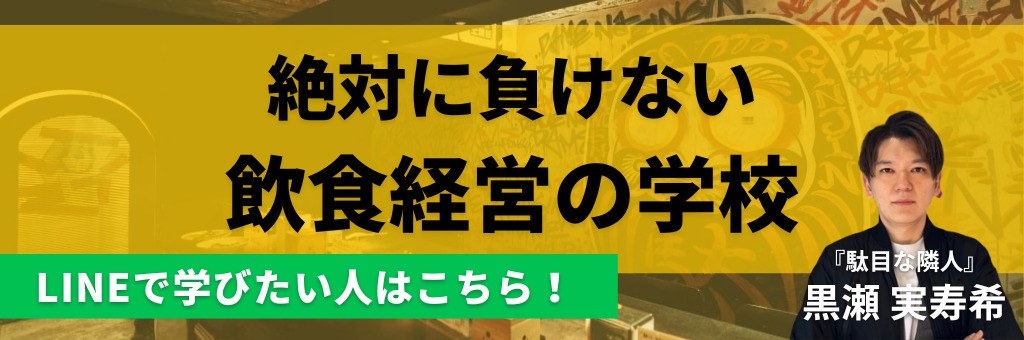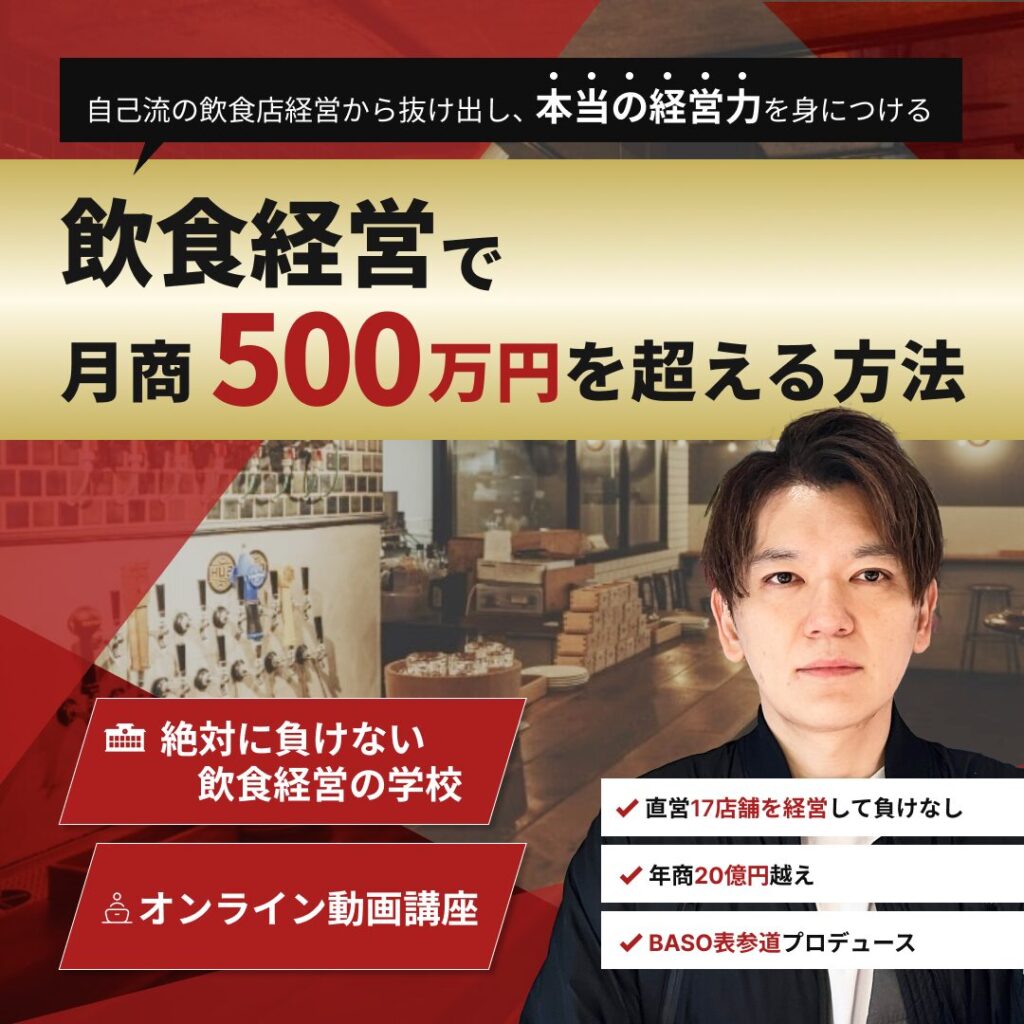「飲食店の衛生管理をするためには、どんな点に気をつければいい?」
「飲食店を開業するには衛生面の資格が必要になる?」
「コロナ対策でどのようなことをすればいいのか、わからない…」
本記事では、上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
飲食店を開業するときに、基本かつ重要となるのが衛生管理で、お客さんの健康を守るためには手を抜けないポイントです。
しかし、具体的にどのような点に気をつけて実施すればいいのかわからない方もいるでしょう。
そこでここから、飲食店の衛生管理のポイントや必要な資格、コロナ対策などについて具体的に解説します。
本記事のリンクには広告を含んでいます。
飲食店の衛生管理の必要性

飲食店を経営する上で衛生管理を徹底することは必要不可欠です。
- 食中毒のリスクを回避できる
- 売上につながる
ここでは、衛生管理を徹底するとどんなメリットがあるのか、詳しく解説します。
食中毒のリスクを回避できる
飲食店を開業するにあたり必ず押さえておくべき点は、衛生管理を徹底する点です。
「当たり前でしょう」と思う方もいるかも知れませんが、お店が忙しくなって衛生面が疎かになるケースもあります。
衛生面が疎かになった場合のリスクとして、食中毒があげられます。
厚生労働省の調査によると、学校や家庭、病院など食品を扱う施設の中で、食中毒が発生した件数の第1位は飲食店だと判明しているためです。
出典:厚生労働省 「令和3年食中毒発生状況」
全体の約4割を飲食店が占めており、飲食店開業者が知っておくべき点だと言えます。
もし、お店から食中毒が発生した場合、お客さんの健康を害したり閉店に追い込まれたりするケースもあります。
どれだけお店が忙しい状況や大変な状況でも、衛生面だけはしっかりできるようにしましょう。
売上につながる
飲食店で衛生管理を徹底すると、お店の売上も上がりやすくなる点は見逃せません。
- 食材の適切な管理による食品廃棄の低減
- 整理整頓による生産性の向上
- お店に対するお客さんのイメージアップ
上記のように、衛生管理によって間接的に売上をあげられることがわかります。
お客さんの動向によって売上は左右されやすいですが、衛生管理することで食品の廃棄などによる無駄な出費を抑えられると言えます。
利益を残しやすいお店にするために、重要なポイントです。
飲食店の衛生管理のポイント4つ

飲食店を開業して衛生管理を徹底するには、食材の管理やスタッフの健康面など、さまざまな点に気をつけることが求められます。
- 店内設備や備品
- 食材の管理
- スタッフの衛生・体調管理
- 食中毒対策
ここから、衛生管理のポイントを具体的に解説します。
①店内設備や備品
1.テーブルや椅子
お店の衛生管理の1つとして、テーブルや椅子があげられます。
お客さんが利用した後はきれいにテーブルを拭き掃除するのが基本で、コロナ対策のために椅子も拭くようにするとより衛生的です。
座席をパーテーションで仕切っている場合、パーテーションも適時アルコール消毒するようにしましょう。
2.トイレ
お店の衛生管理の1つとして、トイレがあげられます。
お店の清潔感だけでなく、イメージに直結しやすい点であり注意が必要です。
TOTOが行った調査によると、飲食店のトイレについて以下の点が判明しています。
- トイレがきれいな飲食店はイメージが上がる:はいと回答した方「79%」
- トイレが汚い飲食店はイメージが悪くなる:はいと回答した方「77%」
参考:TOTO
トイレをきれいに保つには、定期的に掃除することがポイントです。
曜日や時間帯によって担当者を決め、いつでもきれいな状態を保ちましょう。
3.メニュー表
お店の衛生管理の1つに、メニュー表をきれいにする点があげられます。
多くのお客さんが直接手で触れることによって、食中毒の原因となる細菌やウイルスが付着する可能性もあります。
毎回アルコールで拭き上げるのは大変かもしれませんが、営業中に適時実施するのが理想です。
ラミネート加工されているメニュー表を水拭きすると、雑巾の匂いが出るケースもあり、注意が必要です。
4.レジ裏やスタッフルーム
お店の衛生管理の1つとして、レジ裏やスタッフルームをきれいにする点があげられます。
お客さんの目につかず、手を抜きやすい場所かも知れませんが、スタッフの衛生に対する意識を上げるためにも、きれいな状態を保つようにすると効果的です。
トイレ掃除と同じく当番制にしたり、使った後はきれいにするなどのルールを決めるのが1つの方法です。
②食材の管理
1.検品し丁寧に保管
食材を衛生管理するには、業者に納品してもらった食材をしっかり検品し、なるべく丁寧に保管することです。
食材を検品するときは鮮度や状態をチェックし、よくない状態のものがあれば、その場で廃棄するようにしましょう。
食材の入っているダンボールやケースに汚れや菌が付いている可能性があり、調理場から離れた場所で検品するのが理想です。
検品後は中身だけを取り出して、冷蔵庫や冷凍庫などで保管するようにしましょう。
2.適切な温度で保管
食材の衛生管理のポイントとして、食材に応じて適切な温度帯で保管する点があげられます。
冷蔵庫や冷凍庫を使い、食品の廃棄をなるべく少なくするように工夫するのがポイントです。
冷蔵庫の温度は10℃以下、冷凍庫の温度は−15℃以下に保つのが基本となります。
冷蔵庫に食材を詰めすぎると空気が循環できず、温度が上昇して食品が痛む原因になります。
冷蔵庫を利用する場合、7割程度の量に留めたり、冷気の吹き出し口に入れたりしないように注意が必要です。
3.先出し後入れの徹底
食材管理のポイントとして、先に仕入れた食材を手前に出し、後から仕入れた食材を奥に入れる「先出し後入れ」があげられます。
先出し後入れは食品管理の基本で、古いものから使えば食品廃棄を最小限にできます。
食材を利用する前に、食材の状態や賞味期限などをチェックする習慣を持つようにするのも1つの方法です。
特に野菜類の場合は、仕入れたときの状態がそれぞれ異なり、古いものを見極めるのがポイントです。
4.冷蔵庫で自然解凍
食材管理のポイントとして、冷凍されていた食材を冷蔵庫で自然解凍する点があげられます。
冷蔵庫で解凍するには1日程度時間を必要とする点がデメリットですが、食品の味や色が変化したり匂いが出たりすることを抑えやすくなります。
どのように解凍すればいいのか迷った場合、冷蔵庫で自然解凍するのが1つの方法になります。
1度解凍した食品を再び冷凍すると食中毒菌が増殖する原因になり、基本的に避けるようにしましょう。
5.調理済み食材の温度管理
食材管理のポイントとして、調理済みの食材の管理方法があげられます。
基本的に、調理した食材はすぐにお客さんに提供できるのが理想ですが、難しいケースもあるでしょう。
保管する場合は、以下の点に注意が必要です。
- 冷蔵する場合:5℃以下
- 保温する場合:65℃以上
細菌の繁殖しやすい環境は37℃前後で、10℃から60℃の間でも繁殖できる点が特徴です。
6.まな板や包丁の管理
食材管理でポイントとなるのは、まな板や包丁など調理道具の管理です。
まな板や包丁を衛生的に使うには、以下の点に注意が必要です。
- 肉と野菜で使い分ける:生肉は細菌が増殖しやすい
- 表面に傷がついたまな板を使わないようにする:細菌類が増殖しやすくなる
- 油や汚れがついたままつけ置く:雑菌の温床となる原因になる
肉と野菜で使い分け、使ったらすぐに洗うのが、まな板と包丁を使うときの基本になります。
③スタッフの衛生・体調管理
1.手洗い・うがいを徹底する
従業員の衛生管理のポイントとして、手洗いやうがいの徹底があげられます。
作業開始前やトイレに行った後、ゴミ捨て後などは、特に丁寧に手洗いをする必要があります。
手洗いの時間・回数による効果の違いは、具体的に下記のとおりです。
| 手洗いの方法 | 残存ウイルス数 |
| 手洗いなし | 約1,000,000個 |
| 流水で15秒手洗い | 約10,000個 |
| ハンドソープで10秒または30秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎ | 約100個 |
| ハンドソープで60秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎ | 数十個 |
| ハンドソープで10秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎを2回繰り返す | 約数個 |
出典:厚生労働省
丁寧に手洗いをするとウイルスの数を減らせ、衛生効果を高められることがわかります。
感染予防効果に効果的なうがいのやり方は、具体的に下記のとおりです。
- 1回目:水を含み強く「ブクブク」する
- 2回目:新しい水を含み、上を向いて喉の奥まで「ガラガラ」うがいする
- 3回目:新しい水を含み、2回めと同様にもう1度「ガラガラ」うがいする
出典:日本赤十字社
2.頭髪を整える
従業員の衛生管理のポイントとして、頭髪を整える点があげられます。
頭髪を整えることで髪の毛が落ちにくくなったり、清潔感があると見られたりしやすくなる点が特徴です。
特に、食品の異物混入として多いとされるのは髪の毛で、特に注意が必要です。
東京都福祉保健局によると、平成30年度に髪の毛が異物混入した割合は、全体の10%になると判明しています。
参考:東京都福祉保健局
髪の毛の長いスタッフは縛るようにルール化したり、バンダナをつけたりするなどの対策が有効です。
3.体調をチェックする
従業員の衛生管理のポイントとして、体調をチェックする点があげられます。
発熱や頭痛などの症状を訴えるスタッフが出た場合、様子を見て休ませる判断をするのも重要なことです。
お店の営業が大変になるかも知れませんが、ノロウイルスや新型コロナウイルスなどは感染力が高く、侮れません。
もし店内に持ち込んだ場合、スタッフだけでなくお客さんにも感染が広がる可能性があります。
完治するまでは、無理に出勤させないようにしましょう。
④食中毒対策
飲食店の衛生管理のポイントは、食中毒対策をしっかりすることです。
厚生労働省の調査によると、令和3年の食中毒の件数は717件で、約1万人の方が食中毒になっていると判明しています。
出典:厚生労働省
食中毒防止の取り組みとしては、具体的に下記のとおりです。
- 適切に加熱する
- 施設、器具などを洗浄する
- 衛生的な作業着を着る
- 食品の温度管理を実施する
- 原材料受け入れ時にチェックする
- 適切な手洗いを実施する
- スタッフの体調をチェックする
お店やスタッフ、食材などの衛生面をしっかりすることが、結果的に食中毒対策にもなると言えます。
飲食店を開業するために必要な資格
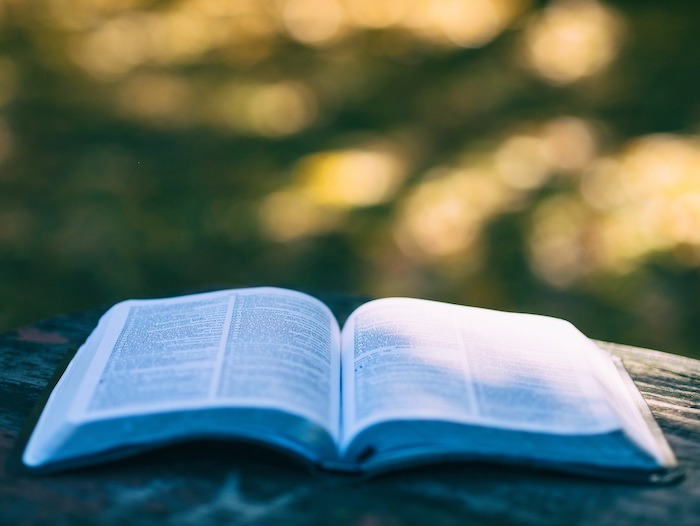
飲食店を開業するためには、基本的に食品衛生に関する資格と、火災の防止・対策をする責任者の資格などを取得する必要があります。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
ここから、開業するために必要な資格の一部を具体的に解説します。
食品衛生責任者
飲食店を開業するために必要な資格は、食品衛生責任者です。
お店の衛生管理をする責任者として、お店に最低1人は配置することが食品衛生法で決められています。
資格を取得するには、各地方自治体の食品衛生協会が実施する、衛生講習会を受講する必要があります。
講習の内容は具体的に下記のとおりです。
- 講習時間:6時間
- 受講料:1万円程度
- 講習内容:衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学
受講するだけで資格を取得できる点が特徴で、早めに取得するようにしましょう。
防火管理者
防火管理者とは火災による被害の防止・対策をする責任者のことで、お店の収容人数が30人以上になる場合、取得が義務付けられています。
- 300平方メートル未満:乙種防火管理
- 300平方メートル以上:甲種防火管理
講習の内容は具体的に下記のとおりです。
講習時間
- (甲種防火管理)2日間で合計10時間
- (乙種防火管理)1日約5時間
費用
- (甲種新規講習)約8,000円
- (乙種防火管理)約7,000円火災の基礎知識や施設の維持管理などについて、講習を通して学べます。
 飲食店の開業に必要な資格は2つ!取得しておくと役立つプラスαの資格も解説
飲食店の開業に必要な資格は2つ!取得しておくと役立つプラスαの資格も解説
飲食店で衛生管理するためのチェックシート
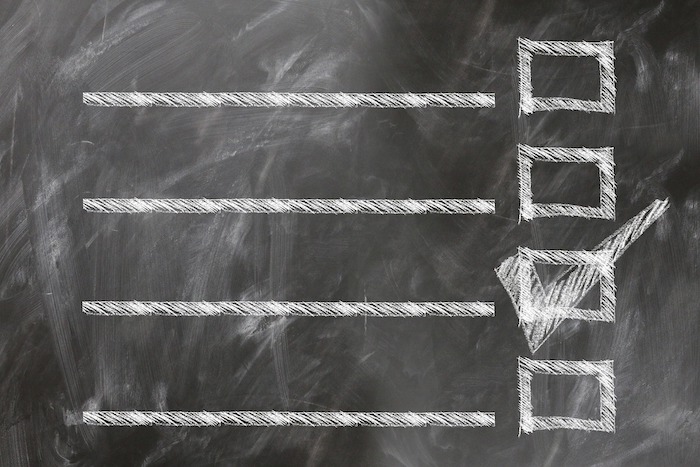
飲食店で衛生管理を実施するためには、チェックシートを作成するのが1つの方法で、作業漏れをなくす効果が期待できます。
チェックシートを作成するべきものは主に2つあります。
- お店全体の衛生管理
- スタッフの身だしなみ・健康管理
ここから作成するべきチェックシートについて具体的に解説します。
お店全体の衛生管理
お店の衛生管理を徹底するためには、さまざまな点をチェックする必要があります。
チェックシートの例は、下記のとおりです。
| チェック項目 | チェック内容 |
| 検品 | ・破損や汚れの有無 ・消費期限や賞味期限 ・発注内容と合っているか |
| 冷蔵・冷凍庫の温度 | ・適切な温度が保たれているか ・温度管理表が用意されているか |
| 2次感染の防止 | ・厨房内へ不用品の持ち込みはないか ・不衛生なものを放置していないか |
| 器具の洗浄や殺菌 | ・消毒や殺菌方法は適切か ・器具の使い分けは適切か |
| トイレ掃除 | ・定期的に掃除できているか ・必要な備品が揃っているか |
出典:フーズチャネル
チェックする項目が多く大変かもしれませんが、毎日の習慣にできると効果的です。
スタッフの身だしなみ・健康管理
スタッフの身だしなみや健康管理チェックシートは、具体的に下記の表のとおりです。
| チェック項目 | チェック箇所 |
| 作業場への入場手順 | ・作業着にローラー掛けをしたか ・手洗い・消毒を実施したか |
| 健康状態 | ・体調はよいか ・手指に怪我はないか |
出典:フーズチャネル
スタッフ自身の衛生管理を徹底させることで、お店全体の衛生管理にもいい影響が出ることが期待できます。
飲食店の新型コロナウイルス感染症対策のポイント

今でこそ感染対策について緩和されてきましたが、新型コロナウイルスをはじめとした、感染症対策は飲食店を経営する上で必ずするべきことです。
- お客さんの入店時の衛生管理
- お店の衛生管理
感染症対策として上記の2つに関して、詳しく解説します。
お客さんの入店時の衛生管理
お客さんの入店時の衛生管理は、具体的に下記の表のとおりです。
| 状況 | 衛生管理の内容 |
| 客席の案内 | ・客席をパーテーションで区分する ・1m以上の間隔を空けて座れるようにする ・カウンター席は適度にスペースを開けるか、パーテーションで区分する ※少人数の家族や介助者が同席する場合などは除く |
| テーブルとカウンターサービス | ・適時アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで消毒する ・スプーン、箸など食器の共有や使い回しを避けるように伝える |
| 会計 | クレジットカードなどの受け渡しが発生する場合、消毒する |
| テイクアウトサービス | 事前予約注文を受付け、店内滞留時間を短くする |
| 会計処理 | ・発熱や咳など異常が見を目られる場合、飲食をお断りさせていただくことを掲示する ・消毒液を用意する ・マスク着用を注意喚起する |
| デリバリーサービス | 料理の受け渡しのとき、手指を消毒する |
参考:日本フードサービス協会
お客さんの入店から退店まで、なるべく距離を保ち、接触を避けられるように行動することが求められます。
お店の衛生管理
お店の衛生管理での注意点は、具体的に下記のとおりです。
| 衛生管理の項目 | 衛生管理の内容 |
| アルコール消毒 | ・ドアノブ、券売機、テーブル、椅子、パーテーション、メニューブックなど、適時アルコール消毒を実施する |
| トイレ掃除 | ・毎日清掃 ・ドアやレバーなど定期的にアルコール消毒 |
| 換気 | ・徹底した換気が基本 ・窓、ドアの定期的な開放、常時換気扇の使用 |
| 手洗い | 作業開始前やゴミ捨て後は必ず手を洗う |
参考:日本フードサービス協会
換気とアルコール消毒が基本となり、手洗いもしっかりするのがポイントです。
お店の衛生管理を徹底しお客さんから信頼されるお店作りを目指していきましょう

ここまで、飲食店の衛生管理の必要性やポイント、コロナ対策などについて具体的に解説してきました。
本記事のまとめは、以下の通りです。
- 飲食店の衛生管理は、食中毒のリスクを回避したり売上に繋がったりする効果が期待できる
- 飲食店の衛生管理のポイントは、設備や食材・調理器具、スタッフの体調面などを適切に管理することである
- 飲食店を開業するために必要な資格は、食品衛生責任者と防火管理者の資格である
本記事を参考に、飲食店の衛生管理について理解していただければ幸いです。