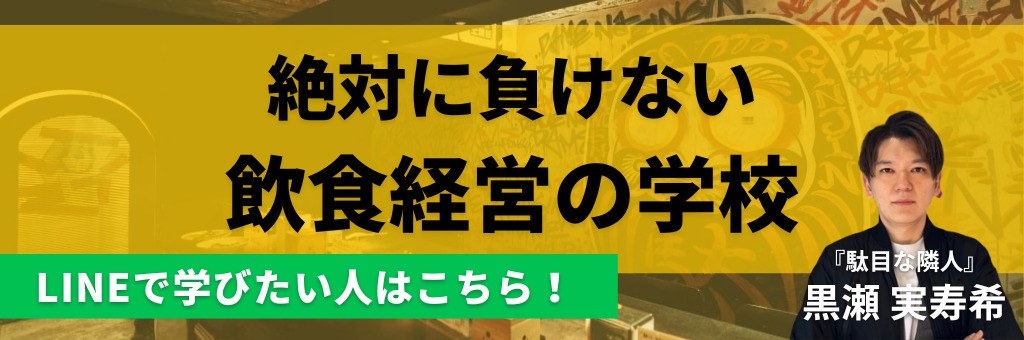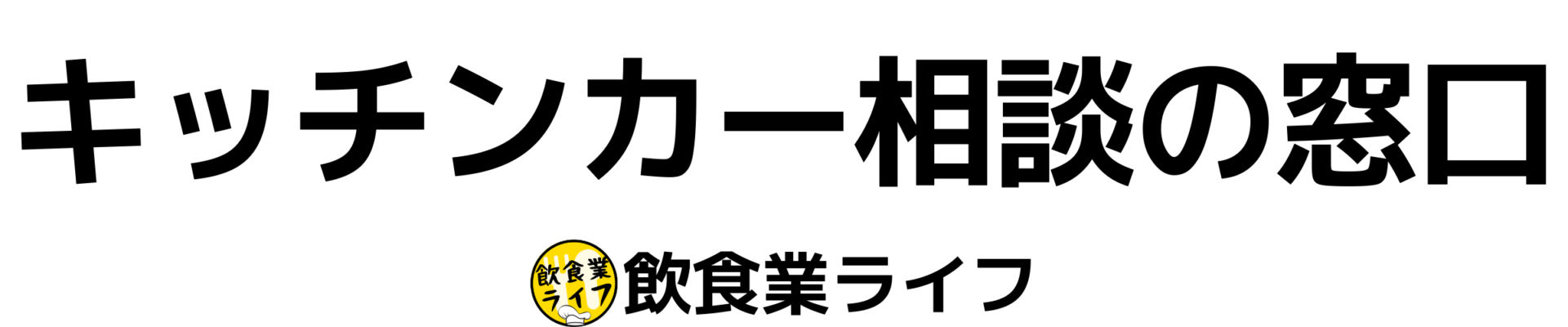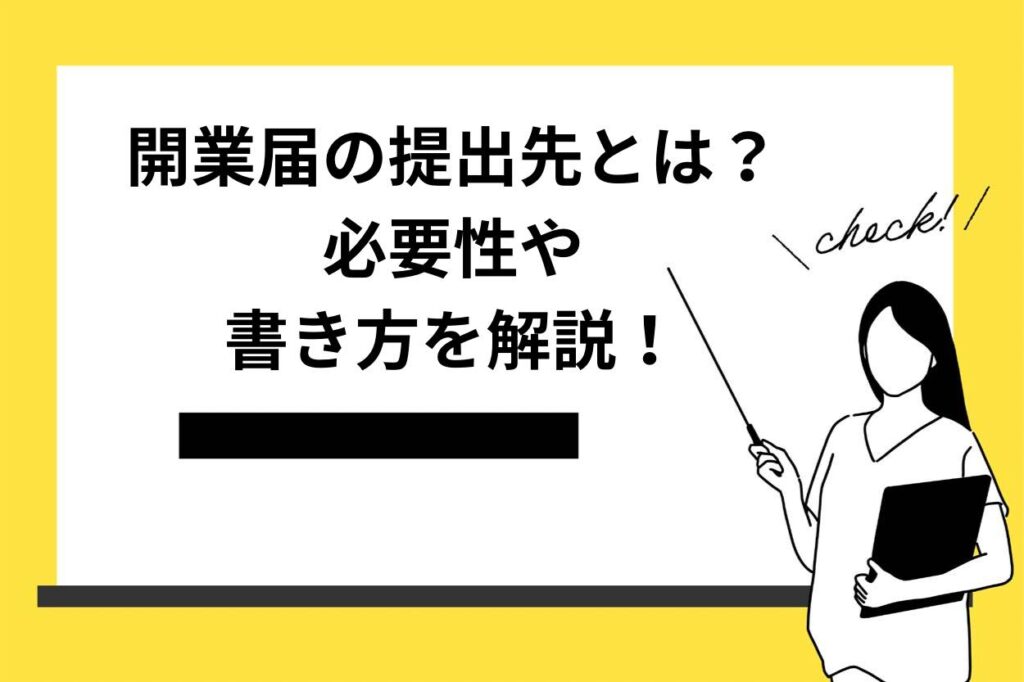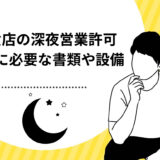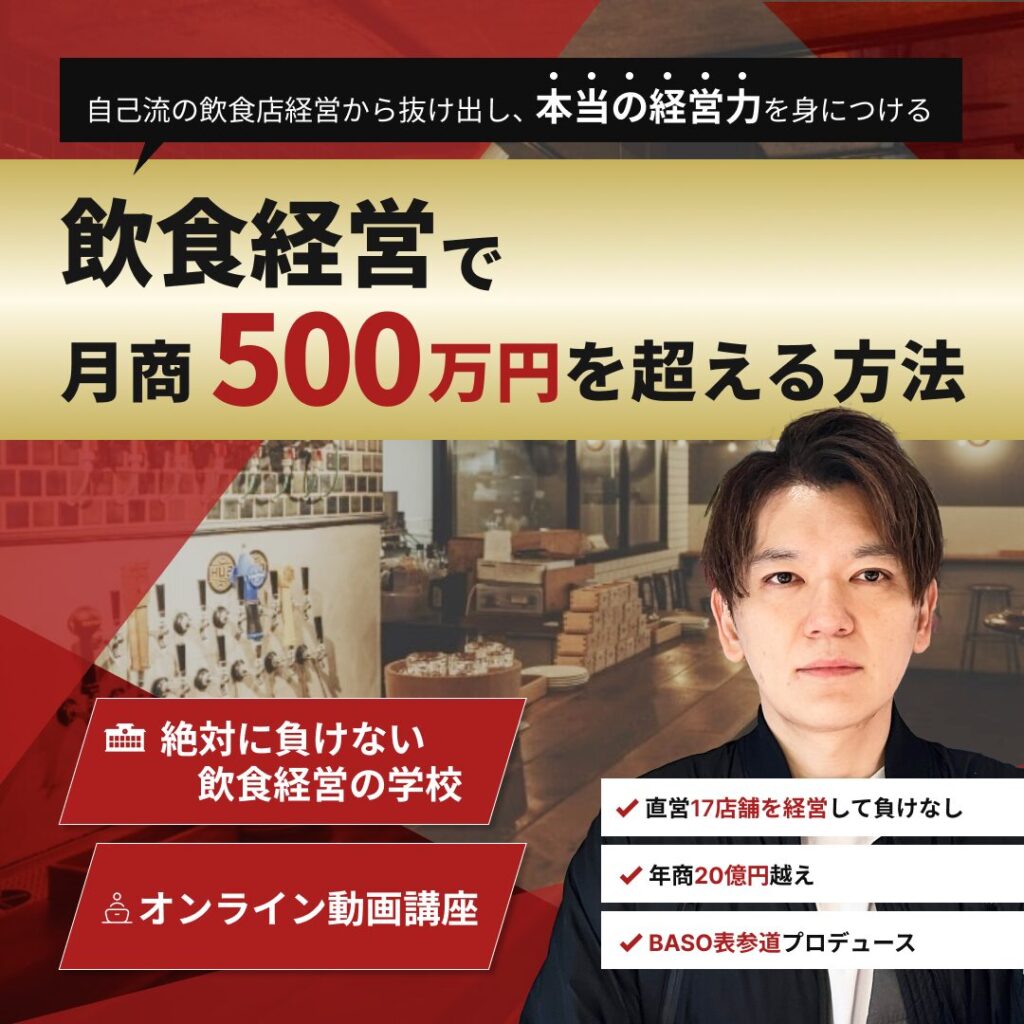「開業届はどこに出せばいい?」
「開業届の書き方がわからない…」
「開業届を提出するメリットって何?」
本記事では上記の開業届に関する疑問やお悩みなどにお答えします。
事業を始めるに当たって必要になるのが開業届ですが、どこに提出すればいいのかわからない方もいるでしょう。
開業届を提出しないと、いろいろなメリットを受けられなくなる恐れがあります。
そこで今回は、開業届の提出先やメリットなどについて具体的に解説するので、参考にしてください。
本記事のリンクには広告を含んでいます。
開業届とは

開業届とは正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
どこでどのような事業を始めたのかを、税務署に知らせるために提出する書類になります。
開業届の提出期限は原則として、新しく事業を始めてから1ヶ月以内と決められてるのが特徴です。
新しく事業を始める時以外にも、下記のケースで書類を提出します。
- 事業を廃止した場合
- 事務所を新設・増設・廃止・移転する場合
ただし、開業届の提出は義務付けられているわけではありません。
提出しなくても罰則を受けるわけではありませんが、さまざまなメリットを享受できなくなります。
例えば、開業届を提出する時に青色申の申請書を一緒に提出すれば、事業所得が最大で65万円課税所得額から引かれます。
そのため、新しく事業を始める時は基本的に開業届を出すようにしましょう。
開業届の提出が遅れると、提出までの期間の費用を経費にできないケースがあります。
開業届の提出先とは

開業届の提出先は、納税地を管轄する税務署になります。
それぞれの住所によって、管轄する税務署が決まっていますので予め確認しておきましょう。
どこの税務署に持っていけばいいのかよくわからない方は、国税庁のWEBサイトで郵便番号を入力すれば該当する税務署が分かります。
基本的にはご自宅の住所が納税地となります。
しかし、事務所を別の地域に設ける場合、該当する地域を管轄する税務署に開業届を提出するのも可能です。
開業届の書き方

開業届を書くために、開業届を国税庁のWEBページからダウンロードします。
ダウンロードできたら、下記の13項目を埋めていきましょう。
| 項目 | 書く内容 |
| 提出先と日付 | 提出する税務署名と提出する日付を記入します。 |
| 納税地 | 原則として、自宅の住所を記入します。 ※別に事務所を設置する場合や納税地を事務所の場所にする場合、「上記以外の住所地・事業所等」に記入します。 |
| 氏名・生年月日・個人番号・職業 | 個人番号はマイナンバーカードの番号を記載します。 |
| 届出の区分 | 開業する場合、「開業」に◯をします。 事業を継いだ場合のみ、住所と氏名を記入します。 |
| 所得の種類 | 基本的には事業所得となります。 ※不動産から所得を得る場合は不動産所得を、山林から所得を得る場合は山林所得を選びます。 |
| 開業・廃業等日 | 開業した日を記入します。 |
| 事業所等を新増設、移転、廃止した日 | 新しく開業する場合、記載不要です。 |
| 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 下記の書類を同時に提出する場合、「有」に◯します。 ・青色申告承認申請書 ・消費税課税事業者選択届出書 上記書類がない場合、「無」に◯します。 |
| 事業の概要 | 事業の内容を分かりやすく書きます。 例えば飲食業の場合、「イタリア料理の調理と提供」など、何をする事業なのか記載します。 |
| 給与等の支払いの状況 ①従業員数 ②給与の定め方 ③税額の有無 |
スタッフを雇う場合に、記載する項目です。 ①(専従者:配偶者や親族、使用人:スタッフ)それぞれの人数を記載します。 ②給与の支払い方法を書く項目です。 例:月給〜円、時給〜円など具体的に記載します。 ③給与を支払って人を雇う場合、基本的に源泉徴収するため「有」を選びます。 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 源泉徴収する場合、基本的には毎月税務署に納付する必要があります。 しかし、従業員が10人未満の場合は非効率であるため、書類を提出すれば年2回にまとめられます。 書類とは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。 開業届と合わせて提出する場合「有」を選びます。 |
| 給与支払を開始する日 | スタッフに給料を支払い始める日付を記載します。 |
| 関与税理士 | 顧問税理士を雇っている場合、氏名と電話番号を書きます。 |
出典:セゾンカード
上記の表の通り各項目を埋めていけば、開業届の記入は完了します。
開業届の3つの提出方法

開業届を提出するには、具体的に3つの方法があります。
どれを選んでもいいので、ご自分のやりやすい方法を選ぶといいでしょう。
1、税務署に持参する
開業届を提出するには、税務署へ直接持っていく方法があります。
ご自分の住所地を管轄する税務署に開業届を持って行けば、受理してもらえます。
税務署の受付時間は8時30分から17時までです。
もし受付時間に間に合わない場合、時間外収受箱に投函できるケースがあります。
2、郵送する
開業届を提出する方法として、郵送があります。
郵送する場合、簡易書留やレターパック等を利用して、確実に届いたかを確認すると安心でしょう。
郵送する場合に、開業届と同封するものは下記のとおりです。
- 開業届をコピーしたもの:控えとして税務署印を押して返送してもらえます
- 返信用封筒:開業届の控えを返送してもらうために必要です
- マイナンバーカードか本人確認書類:マイナンバーカードがない場合、住民票などのマイナンバー確認書類と運転免許証などの身分確認書のコピーが必要になります
- 青色申告承認申請書:開業届の提出と同時に青色申告をしたい場合、「所得税の青色申告承認申請書」が必要です
郵送の場合、税務署まで持っていく手間が省けますが、往復分の送料が必要になります。
3、e-Taxを利用する
e-Taxを利用すれば、開業届を提出できます。
e-Taxの場合、インターネットを使って開業書の作成・提出まで行える点が特徴です。
出典:e-Tax
e-Taxを利用するには、下記を揃える必要があります。
- マイナンバーカード
- インターネット環境
- マイナンバーカードを読み込めるスマホかICカードリーダー
上記の条件が揃っている方の場合、比較的簡単に開業届の提出までを完了させられます。
e-Taxのソフトをダウンロードして、支持される手順通りに進めていけばOKです。
e-Taxで開業届を提出した場合の控えは、「受信通知」になります。
税務署から受信通知が送られてきたら、印刷しておくといいでしょう。
開業届を提出する5つのメリット

開業届を提出するまでに時間と手間がかかりますが、多くのメリットを受けられます。
ここから、開業届を提出するメリットを具体的に解説します。
1.節税効果がある
開業届を提出するメリットは、青色申告特別控除を受けて節税効果が期待できる点です。
青色申告特別控除を受けるには、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しなければいけません。
控除を受けられれば、納税額を計算する時の課税所得額が最大65万円圧縮されるため、納税額を削減できます。
開業してから間もない頃は特に、収入が不安定になりやすい個人事業主にとって、見逃せない制度の1つです。
2.赤字の繰越しと繰戻しができる
開業届を出すメリットは、事業を通して計上した赤字の繰越と繰戻しができる点です。
年間の収入が赤字になった場合、翌年から3年間繰り越せます。
翌年以降に黒字を計上した場合、繰り越した赤字分を差し引いた金額に対して課税されます。
そのため、赤字を繰越すことで節税ができるわけです。
繰戻しとは、前年の黒字分を使って現在の赤字分を補填する仕組みのことで、支払った所得税を返金してもらえることを意味します。
ただし、前年も青色申告をしていなければなりません。
3.屋号で銀行口座を開設できる
開業届を提出するメリットは、屋号を使って銀行口座を開設できる点にあります。
個人の口座と分けて口座を持つと、全うなビジネスを行っていることが伝わり、取引先からの信頼を得やすい点が特徴です。
口座を2つ開設するのは手間に感じるかも知れませんが、長い目で見ると恩恵を受けられるでしょう。
銀行口座を分けて持つと、プライベート用と事業用でお金の管理をしやすくなる点もメリットです。
特に、お金の管理が苦手な方にとってメリットが大きいといえます。
4.屋号でクレジットカードに申し込みできる
開業届を提出するメリットは、屋号を使ってクレジットカードの申し込みができる点です。
事業用のクレジットカードを作るメリットは具体的に下記の3点です。
- 経費の精算を効率的にできる
- 資金繰りに活かせる
- 屋号付き口座を選択できる
事業用のクレジットカードを作れば、事業で使ったお金のみをまとめて管理できます。
事業以外で使ったお金と分けて管理できるので、ひと目でわかりやすくなるでしょう。
また、会計ソフトに連携できるため経費精算をより効率的に行なえます。
事業用のクレジットカードの場合、締日から引き落としまで2ヶ月の期間が設けられているケースがあります。
特に、事業を始めたばかりで費用がかかりやすい時など、資金繰りに活かせる点がメリットです。
5.小規模企業共済に加入できる
開業届を提出すれば、小規模企業共済に加入できます。
小規模企業共済とは、毎月一定の金額の積み立てによって、廃業時や退職時に掛け金に応じた給付金を受け取れる制度です。
フリーランスや個人事業主には退職金制度がありませんが、小規模企業共済に加入すれば退職金代わりとなるお金を受け取れるわけです。
加入するには、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体や金融機関に問い合わせる方法があります。
忘れずに開業届を提出して様々なメリットを受けましょう

ここまで、開業届の提出先やメリットなどについて解説してきました。
本記事のまとめは下記の通りです。
- 開業届は、どこでどのような事業を始めたのかを税務署に知らせるために提出する書類
- 開業届の提出先は、納税地を管轄する税務署
- 開業届は、開業届をダウンロードした上でフォーマットに沿う必要がある
- 開業届の提出方法は、税務署に直接持って行く方法や郵送する方法などがある
- 開業届を提出するメリットとは、節税や屋号でクレジットカードを作成出来る点など
本記事を参考に、開業届の提出先などについて理解していただければ幸いです。