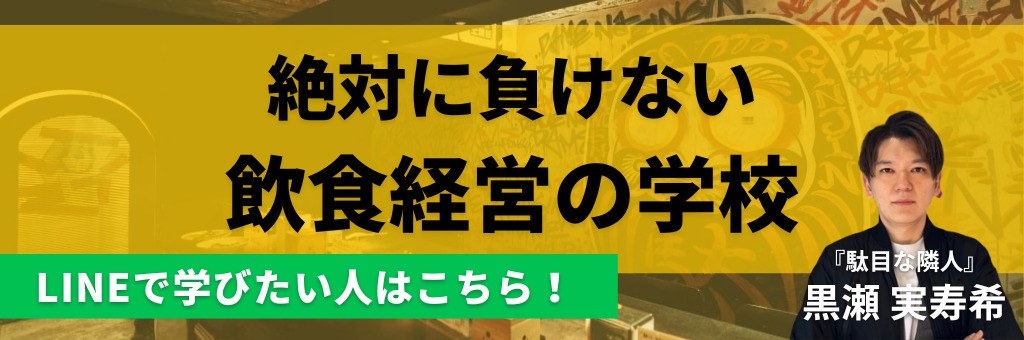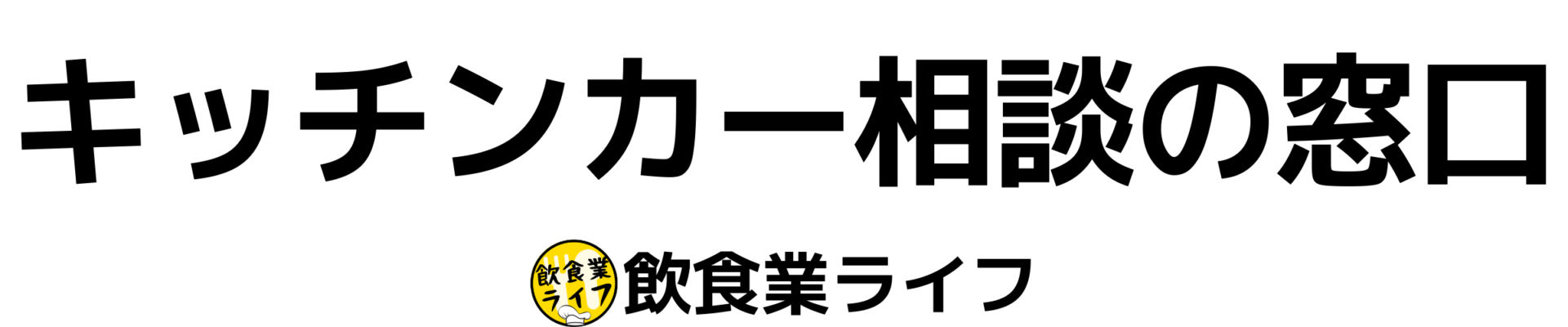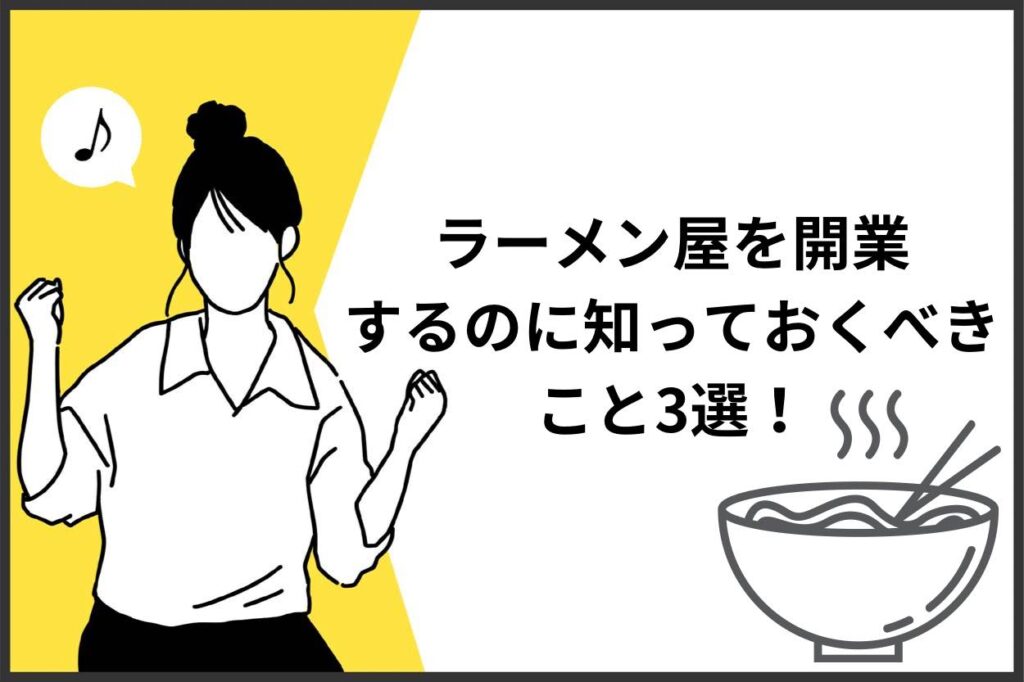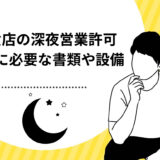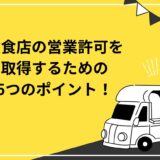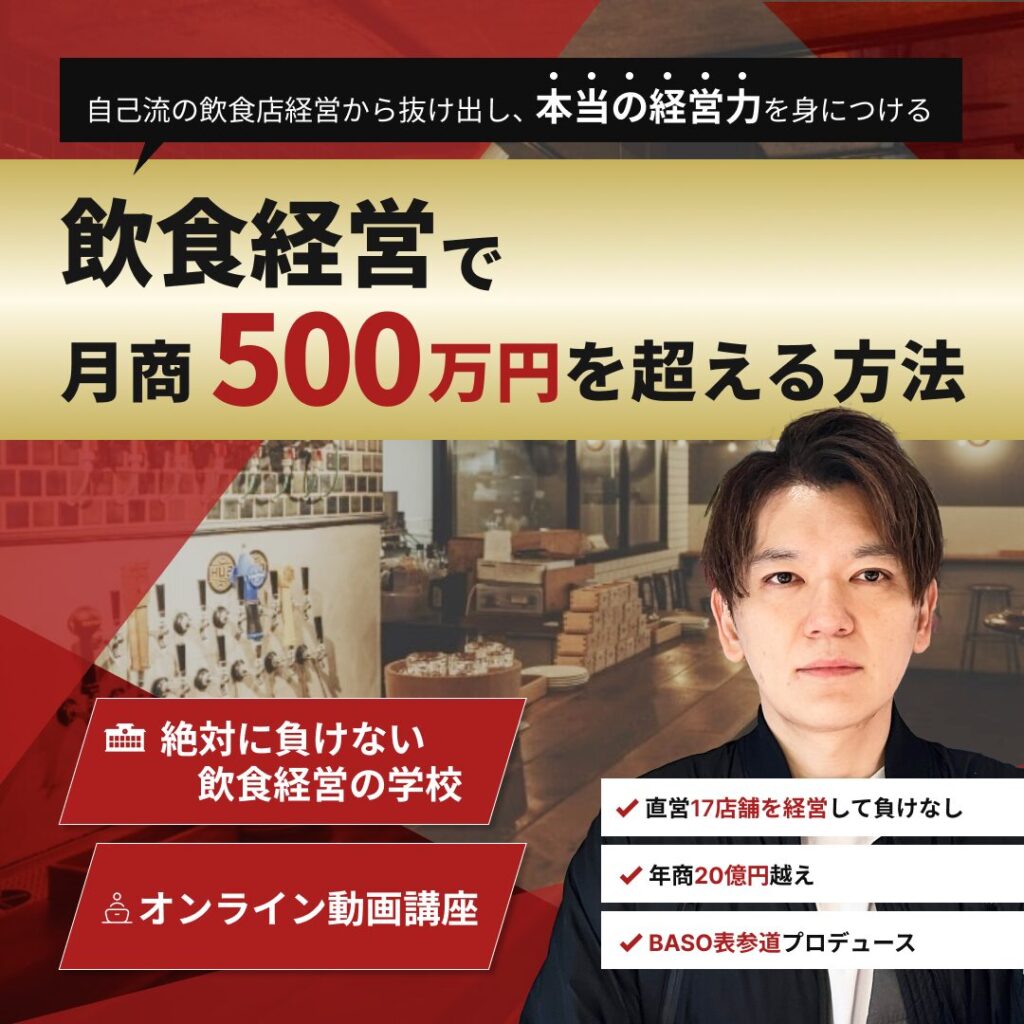街を歩けばラーメン屋はいたるところに存在します。ラーメンは日本人にとって最も馴染みのある食べ物の1つです。
それゆえ、ラーメン屋を開業したいと考える人も多いのではないでしょうか?
「大好きなラーメンで自分の店を持ってみたい」
「でも、何から始めて良いかわからない」
「ラーメン屋を開業するまでに必要なことを知りたい」
きっとこのような悩みを抱えているのではないでしょうか?
そこでこの記事では、ラーメン屋を開業するにあたって何を知っておくべきなのか、重要なポイントを3つにまとめて解説していきます!
本記事のリンクには広告を含んでいます。
事業計画を作りこむ

1番最初にしなければならないのが事業計画を立て、入念に準備することです。
具体的に何を準備するのかというと、重要なことが2つあります!
①コンセプトを考える
ラーメン屋に限らず、飲食店を開業するにあたって一番最初に着手するべきところはコンセプト設計です。
コンセプトとは、どのような飲み物・食べ物を、どんな人たちをターゲットにして、どのような雰囲気のお店で、価格帯をどうするのか、という具体的なイメージを決めることです。
事業計画書を作成したことがない、どうやって作成したらいいかわからない……そんな方におすすめなのが、経済産業省が後援するDREAM GATEです。専門家への無料相談や、事業計画書の作成に関するノウハウ公開など、これからラーメン屋を開業したい方に役立つ情報を無料で得ることができます。
安定した飲食店は規模の大小に関わらず、このコンセプトがあることが特徴です。
ラーメン屋で例えるなら、
「老若男女問わないラーメン屋にしたい!」
「思い切ってターゲットを男性に絞ったメニューにしたい!」
「話題になるような一風変わったお店にしたい!」
などなど、最初は思いついたことをどんどん羅列していきましょう。メニュー開発にも必ず生きてきますし、きっとこだわりたいポイントが各々あるはずです。
簡単な具体例ですが、少しはイメージしやすくなったと思います。最初はこのように思い浮かぶだけやりたいコンセプトを洗い出してみましょう!
コンセプトが一通りまとまってきたら、それに付随して利益計画も必ず立てましょう!
一般的に、飲食店で必要な経費を表でまとめると下記のようになります。
| 家賃 | 約10% |
| 水道光熱費 | 約5~8% |
| 人件費 | 約25~30% |
| 材料費 | 約30% |
| 広告費 | 約3% |
| 通信費・消耗品費 | 約5% |
これはあくまでも目安です。
簡単に捉えるなら、ラーメンの材料費の約3倍を販売価格に設定すると無難ということです。ラーメン1杯600円なら材料費は200円ほど、1杯900円なら材料費は300円ほどに抑えるべきです。
予めこの利益計画を入念にシミュレーションして、しっかり利益の残るように商品価格を設定しましょう!
②物件選び・競合リサーチ
ラーメン屋を開業するにあたって物件選びは非常に重要です。
最も重要だと言い切る人も少なくありません。物件を考えるにあたって押さえておくべきポイントが4つあります!
1.飲食店舗物件
店舗物件を選ぶときに確認しておかなければならないのが、その店舗が「飲食店舗物件」であるか否かということです。
簡単にいえば、その物件で飲食店を営業して良いのかどうかということです。飲食店舗物件には2パターンに分かれており、「軽飲食専用店舗」と「重飲食専用店舗」があります。
ラーメン屋は一般的に重飲食専用店舗であることが多いですが、軽飲食専用店舗でも営業できる可能性はあります。どうしてもその物件にこだわりたいと思ったら、不動産会社やオーナーに交渉してみましょう!
2.面積
店舗の面積も物件選びをするうえで重要です。
飲食店の業種によって必要な店舗面積は異なりますが、ラーメン屋に必要な面積は15〜20坪程度となっています。
またカウンターのみの店舗の場合は、10坪程度でも可能です。 一般的な店舗では、1坪あたり1.5席の客席を設けると良いとされています。
したがって、 店舗の面積によって客席数もおのずと決まってくるので、自分がどの程度の大きさの店舗を構えたいのか、そして店舗の回転率などを踏まえて適切な面積の店舗を選びましょう。
3.賃貸料

店舗の賃貸料も物件選びをするうえで重要です。
月の売上金額に対して賃貸料が大幅に高い物件は、当然ですが利益が見込めず赤字になってしまいます。そのような物件は、店舗には適していないと判断できます。
あらかじめ営業日数、メニュー単価、一日の来客数を想定し、一ケ月当たりのおおよその売上金額を算出しておきましょう。
そうすることで、営業にも支障のない自分の店舗に見合った物件を選ぶことができます。
4.立地
店舗の立地も物件選びをするうえで重要です。
まず、出店しようとしている場所周辺の人口や通行人数、交通量について調査しましょう。
この調査をすることで、その立地がにぎわっている地域か否かをある程度把握することができます。
この調査で役に立つのが役所のホームページに掲載されている「町丁別人口統計」といったものです。簡単に調べることができるのでおすすめです。
また、競合店の有無についても調査しましょう。
周辺にあるラーメン屋の件数や飲食店のカテゴリーが把握しておきたいポイントです。その地域にラーメン屋が出店されていない場合、ラーメンがその地域には合っていないのではないか?という仮説が立てられます。
以上の2点をある程度調べたうえで実際に足を運び、周辺環境を確認してみましょう!
資金調達
ラーメン屋を開業するにあたって、事業計画に目処が立ったら次に着手すべきは資金調達です。
ラーメン屋を開業するには初期費用はどの程度かかるのでしょうか?もちろん店舗の広さや出店する場所によって変わりますが、カウンター席だけを用意する10坪程度で家賃が15万円程度と想定すると、開業資金は約1000万円〜1500万円と言われています。
余談ですが、日本政策金融公庫の2020年7月の調査によると、飲食店の開業資金の平均は989万円となっています。
初期費用の内訳は、
・物件取得費
・内外装工事費
・厨房設備費
・広告宣伝費
・資格取得費
主にこの5つです。
なかでも大きな割合を占めるのが、物件取得費・内外装工事費・厨房設備費の3つです。
あくまで目安ですが、
| 物件取得費 | 300万円 |
| 内外装工事費 | 760万円 |
| 厨房設備費 | 360万円 |
| 広告宣伝費 | 40万円 |
| 資格取得費 | 3万円 |
| 合計 | 1463万円 |
引用:https://www.fc-hikaku.net/dokuritsu_kaigyo/1953#anchor2
飲食店の開業資金の調達として一番メジャーなのが日本政策金融公庫からの借入です。
その理由は様々ありますが、主に5つメリットがあります。
1.開業初期でも申し込みやすい
日本政策金融公庫は、民間の金融機関の取り組みを補完し、事業に取り組む人を支援することを理念においているため、銀行や信用金庫よりも申し込みやすい傾向があります。
申込者の条件や利用する融資制度によっても異なりますが、創業初期でも申し込みやすい点は、銀行や信用金庫に申し込めなかった人にとってはメリットのひとつです。
銀行や信用金庫など、民間の金融機関にも創業者向けの融資制度はありますが、これから4つ解説するメリットを含めて考えると、日本政策金融公庫から融資を受けるほうがメリットがあるでしょう。
2.民間の金融機関よりも金利が低い
日本政策金融公庫は、民間の金融機関の取り組みを補完し、事業に取り組む人を支援することを理念においているため、銀行や信用金庫よりも金利が低めです。
実際の金利は融資制度や契約内容によって様々ですが、金利の幅が低めに設定されています。
しかし、日本政策金融公庫では、他の金融機関からの借り換えを認めていません。そのため、他の金融機関からの借り換えとして日本政策金融公庫から融資を受けることを検討中の人は注意が必要です。
3.無担保・無保証の融資制度がある

一般的に、銀行や信用金庫などの民間の金融機関から融資を受ける場合、保証人が必要になる傾向があります。
日本政策金融公庫の新創業融資制度は原則保証人が不要であるため、保証人を立てることに不安がある人にとってはメリットと言えます。
「知人の連帯保証人になってしまい、借金を負ってしまった」という話はよく聞きますが、この制度を利用すると、その心配がいりません。
この融資制度についてもっと知りたい方はこちらの動画がおすすめです→https://www.youtube.com/watch?v=m5ijyV0ASVI
4.民間の金融機関よりも返済期間が長め
日本政策金融公庫の融資制度は、返済期間が長めに設定されている傾向があります。
返済期間が短ければ短いほど、毎月の返済負担は重くなる傾向があるため、余裕ある返済計画を立てたい人にとってはメリットになります。
たとえば、日本政策金融公庫の新規開業資金では、「設備資金は20年以内(うち据置期間2年以内)」「運転資金は7年以内(うち据置期間2年以内)」の返済期間になります。
返済期間が長ければ、余裕ある返済計画を立てることもできるため、毎月の返済負担を軽減したい人は、日本政策金融公庫から融資を受けることはメリットと言えるでしょう。
5.民間の金融機関よりも手続きがスムーズ
日本政策金融公庫から融資を受ける場合、信用保証協会を経由することなく融資を受けることになります。
信用保証協会に提出する書類を準備する必要がないため、手続きにかかる工数を少なくしたい人にとってはメリットになります。
銀行や信用金庫など、民間の金融機関から融資を受ける場合、原則として信用保証協会の保証を受ける傾向があります。そういった際、利用する金融機関に加え、信用保証協会の提出書類も準備する必要があります。
また、銀行や信用金庫などの民間の金融機関の場合、信用保証協会の保証を受けることになれば、金融機関と信用保証協会の両方の審査を受けることになります。審査を2回受けるということは、審査結果を得るまでの時間もそれぞれ異なります。
こういった背景から、銀行や信用金庫で信用保証協会の保証を受けられる可能性がありますが、手続きにかかる手間が多くなってしまいます。
スムーズに融資を受けられるという点でも日本政策金融公庫がおすすめです。
他に飲食店開業時に使える補助金・助成金があります。
創業補助金
平成25年から始まった新たに事業を創業する個人または法人が国から最大200万円の補助を受けられる制度。
小規模事業者持続化補助金
日本商工会議所が運営する、修行員数が5人以下の小規模事業者を対象に、上限50万円を支給してもらえる制度。
開店に向けた準備
ラーメン屋を開業するにあたって、資金調達に目処が立ったら次に着手すべきは開店に向けた準備です。
具体的にやるべきことは3つあります!
資格

飲食店開業に必要不可欠な資格は「食品衛生責任者」です。
飲食店を開業するために、調理師免許を持っていなければならないと思う方もいると思いますが、実際には調理師免許を持っていなくても飲食店の開業は可能です。
届出は主に保健所や消防署など、店舗を管轄する行政機関に提出する必要があります。
食品衛生責任者は、店舗内の衛生管理や従業員の衛生管理指導を行うことを仕事とし、飲食店を営業する際必ず1名以上置かなければなりません。
この「食品衛生責任者」の資格を得るためには、都道府県が実施する講習を受講しなければなりません。例外として、調理師や栄養士の免許を持っている人は講習を受講しなくても良いことになっていますが、その他の方は絶対に取らなければなりません。
受講費用は約1万円ほどで講習は1日~2日です。詳細は地域によって異なるため、保健所に詳細を確認してみましょう。
難易度は低く、講習後には修了試験が実施されますが、講義の内容をしっかり聞いていれば応えられる内容のため、事前勉強は必要ありません。
従業員雇用
オープン1か月前になったら求人を始めましょう。
オープン直前だと研修が間に合いませんし、早すぎると辞退されてしまう可能性があるからです。
従業員の雇用・育成に関しては次のサイトをおすすめします。
→https://www.tenpos.com/kaigyo/ramen-step09/
販促
オープン前に必ず販促ツールを作成しましょう。
具体的には、
・ホームページの作成
・SNSアカウントの作成
・ポイントカードの作成
この3つです。
特にSNSアカウントの作成・運用は必須です。Twitter・インスタグラム・TikTokのいずれか、できれば全てやったほうがいいでしょう。
現代ではSNSで食べに行く場所を決めることが急激に増加しました。特に20代~30代はその世代です。
ラーメン屋のターゲット層も主に20代~30代であることが多いことを考えると、SNSアカウントの作成・運用をさぼると集客に歯止めがかかると言っても過言ではないでしょう。
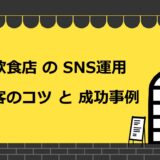 飲食店がSNSで売上・集客につなげる8つのコツ!成功事例や注意点も紹介
飲食店がSNSで売上・集客につなげる8つのコツ!成功事例や注意点も紹介
事前準備をしっかりして夢のラーメン屋開業を成功させよう!
今回はラーメン屋を開業するにあたって知っておくべきこと3選について解説しました。
知らなかったことも多かったのではないでしょうか?
何事も開業するとなったら大きな資金、数多くの準備が必要不可欠ですが、後悔のない開業の手助けとなれたら幸いです。