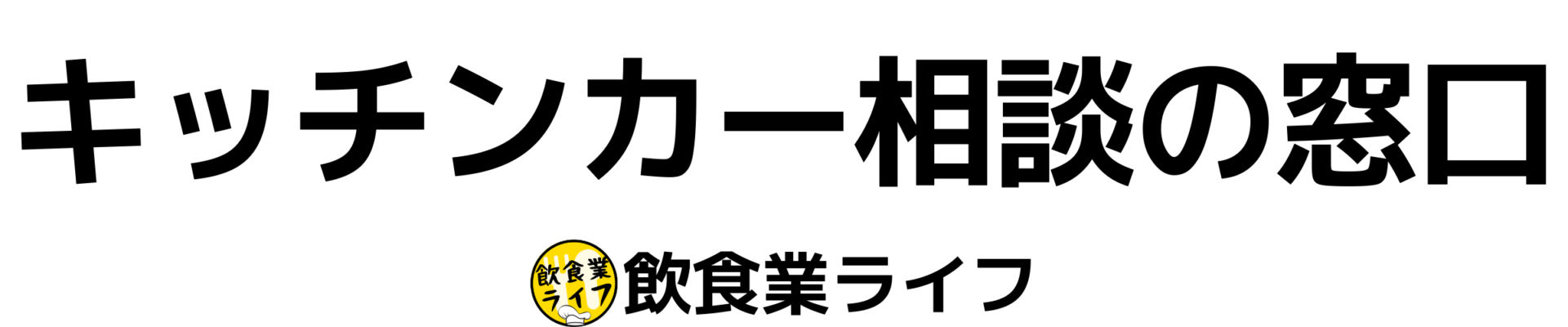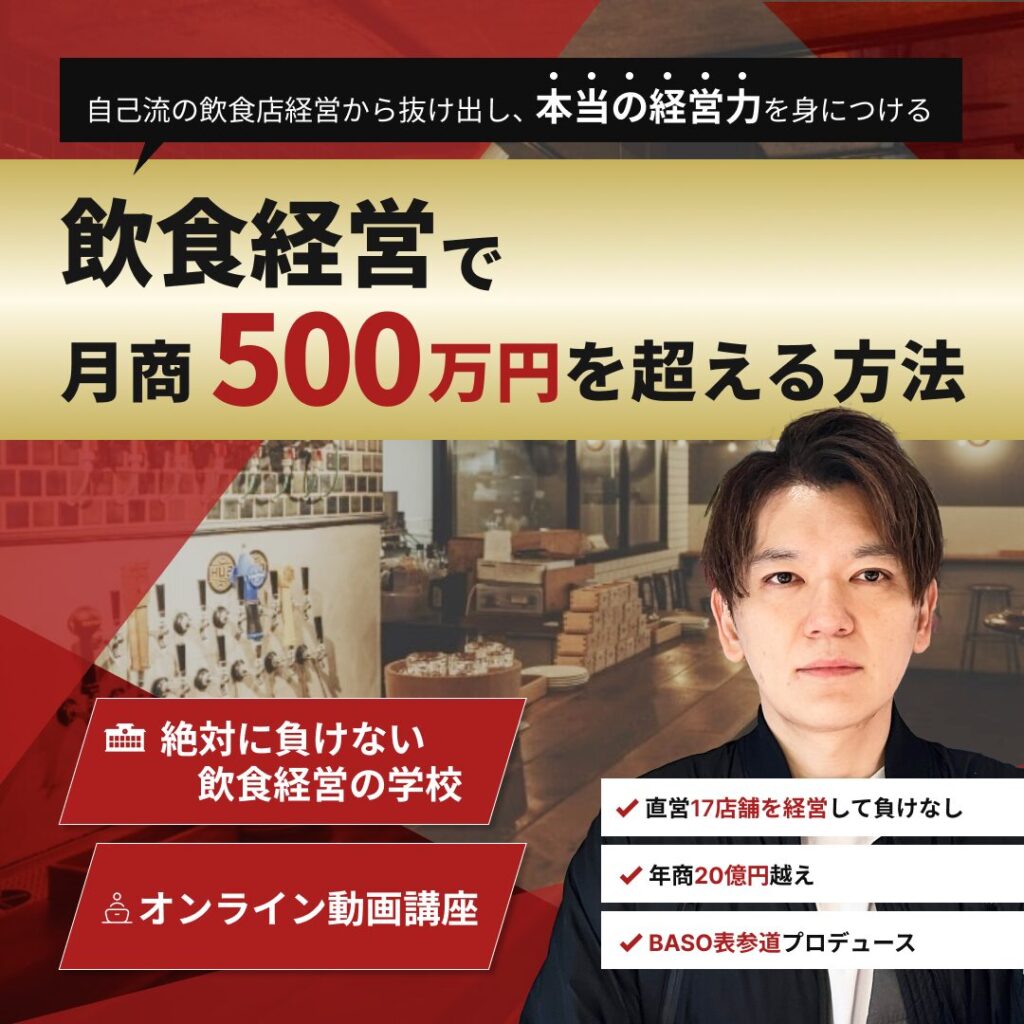「キッチンカーの耐用年数ってどのくらいなの?」
「中古のキッチンカーのだと耐用年数は異なる?」
「キッチンカーの減価償却はどうやって求めたらいい?」
このようなお悩みを抱えていませんか?
減価償却費を算出するには、保有している資産の耐用年数を把握しておかなければなりません。
キッチンカーの耐用年数がどのくらいなのか知りたい方も多いと思います。
しかし、キッチンカーと一言でまとめても、新車・中古車と購入方法が異なったり、様々な車両の種類があったりします。
そのため、保有している車両の耐用年数がどのくらいなのか、判断が難しいですよね。
そこでこの記事では、キッチンカーの耐用年数を新車や中古車、車の種類などに分けて解説します。
減価償却の計算方法や耐用年数における注意点も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
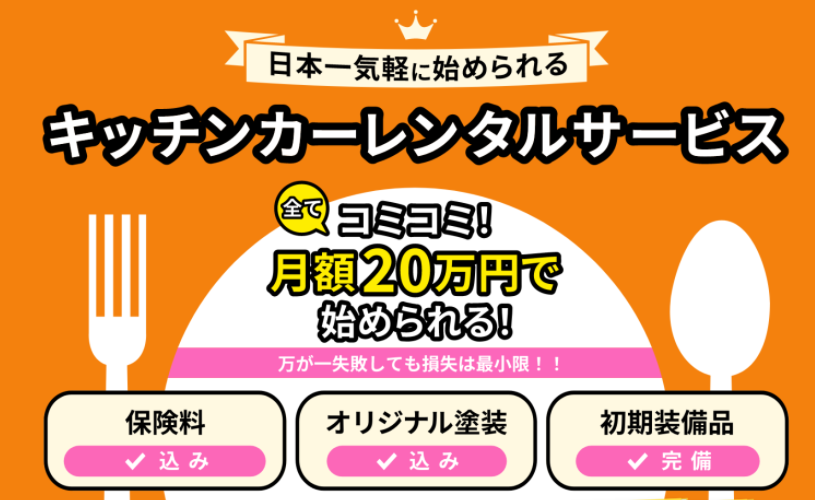 移動販売を始めるなら、キッチンカーレンタルサービスの「ためしてキッチンカー」がおすすめです。
移動販売を始めるなら、キッチンカーレンタルサービスの「ためしてキッチンカー」がおすすめです。
- 半年間の契約で月額20万円
- 開業に失敗しないためのサポート
- 最短納期なら1ヶ月半後にスタート
本記事のリンクには広告を含んでいます。
キッチンカーの耐用年数を新車・中古車に分けて解説
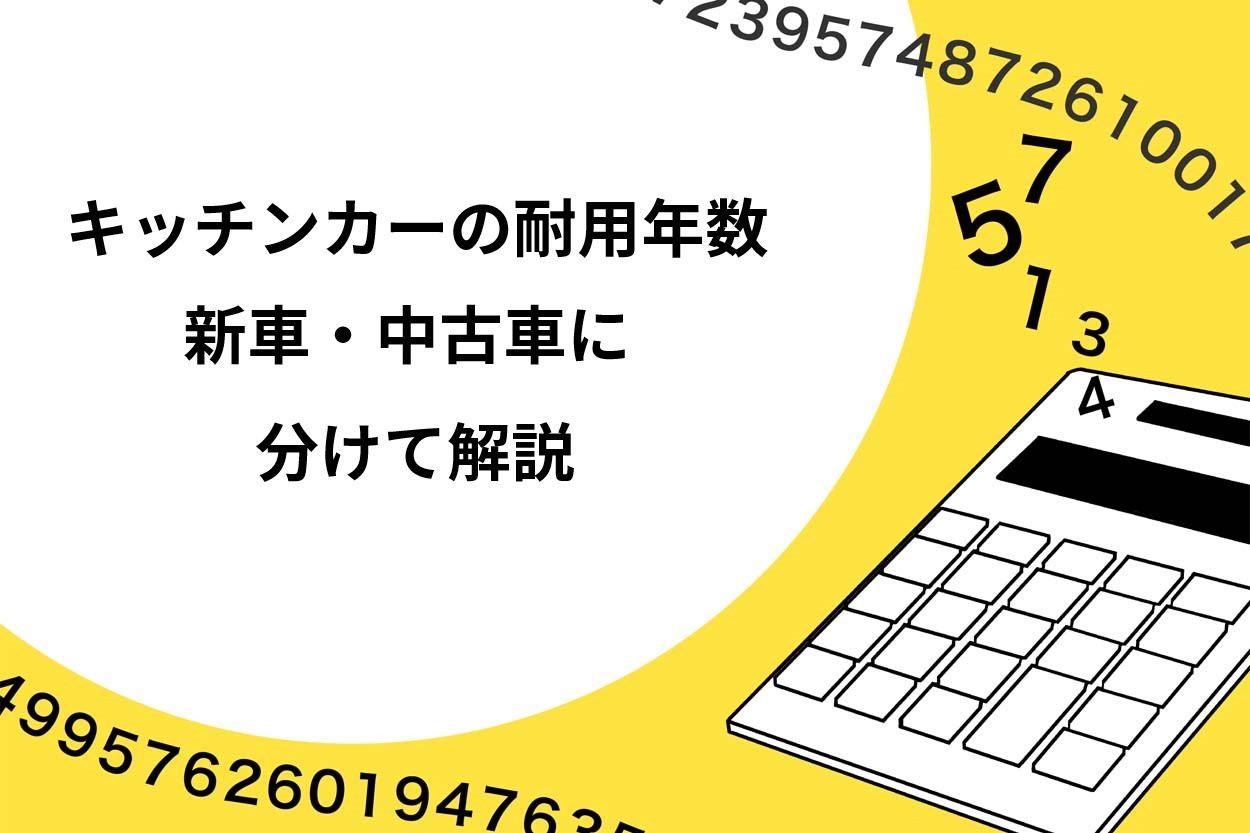
キッチンカーの耐用年数は、新車と中古車によって異なります。そのため、これからキッチンカーを購入しようと考えている方は、注意が必要です。
こちらでは、耐用年数を
- 新車
- 中古車
に分けて解説します。
1.新車
キッチンカーが新車の場合、耐用年数は車両の種類によって異なります。
以下の表は、車両の種類と耐用年数をまとめたものです。
| 車両の種類 | 耐用年数 |
| 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) | 4年 |
| 普通車 | 6年 |
| 貨物自動車(トラック) | 5年 |
| リヤカー | 4年 |
参考:国税庁「耐用年数(車両・運搬具/工具)」
イメージが湧きやすいよう、キッチンカーでよく使われる車両でみてみましょう。
主に使用される車種の耐用年数は、以下の通りです。
- スズキ キャリー(小型車):4年
- スズキ エブリィ(小型車):4年
- 日産 バネット(普通車):6年
キッチンカーを新車で購入しようとしている方は、欲しい車両が何の種類なのか、耐用年数はどのくらいなのかを確認してみてください。
2.中古車
キッチンカーが中古車の場合は、新車と比べて耐用年数が短くなる傾向があります。
ただし、以下2つのケースで見解は異なるので、注意が必要です。
- 法定耐用年数を全て経過している場合
- 法定耐用年数の一部を経過している場合
中古車の耐用年数を求めるには、計算が必要になります。
具体例を用いながら分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
1.法定耐用年数を全て経過している場合
法定耐用年数を全て経過している中古車の場合は、法定耐用年数 × 20%の計算式で求められます。
例えば、10年落ちの普通車のキッチンカーの計算は以下の通りです。
6年(法的耐用年数)× 20%=1.2年
計算上では1.2年になりましたが、2年未満だった場合は、耐用年数は自動的に2年となります。
なお、計算結果が2年以上になると1年未満の端数は切り捨てます。
例えば、計算結果が3.5年の場合、耐用年数は3年です。
2.法定耐用年数の一部を経過している場合
法定耐用年数の一部を経過している場合は、(法定耐用年数 − 経過年数) +( 経過年数 × 20%)の計算式で求められます。
例えば、2年10ヶ月落ちの普通車の計算は、以下の通りです。
(6年-3.4年)+(3.4年×20%)=(72ヶ月-34ヶ月)+(34ヶ月×20%)=44.8ヶ月
44.8ヶ月を年数に直すと、3年7ヶ月となります。
1年未満の端数を切り捨てるため、耐用年数は3年です。
定耐用年数の一部を経過している場合は、計算がややこしくなるため注意しましょう。
キッチンカーにおける減価償却の計算方法を2つの場合で解説
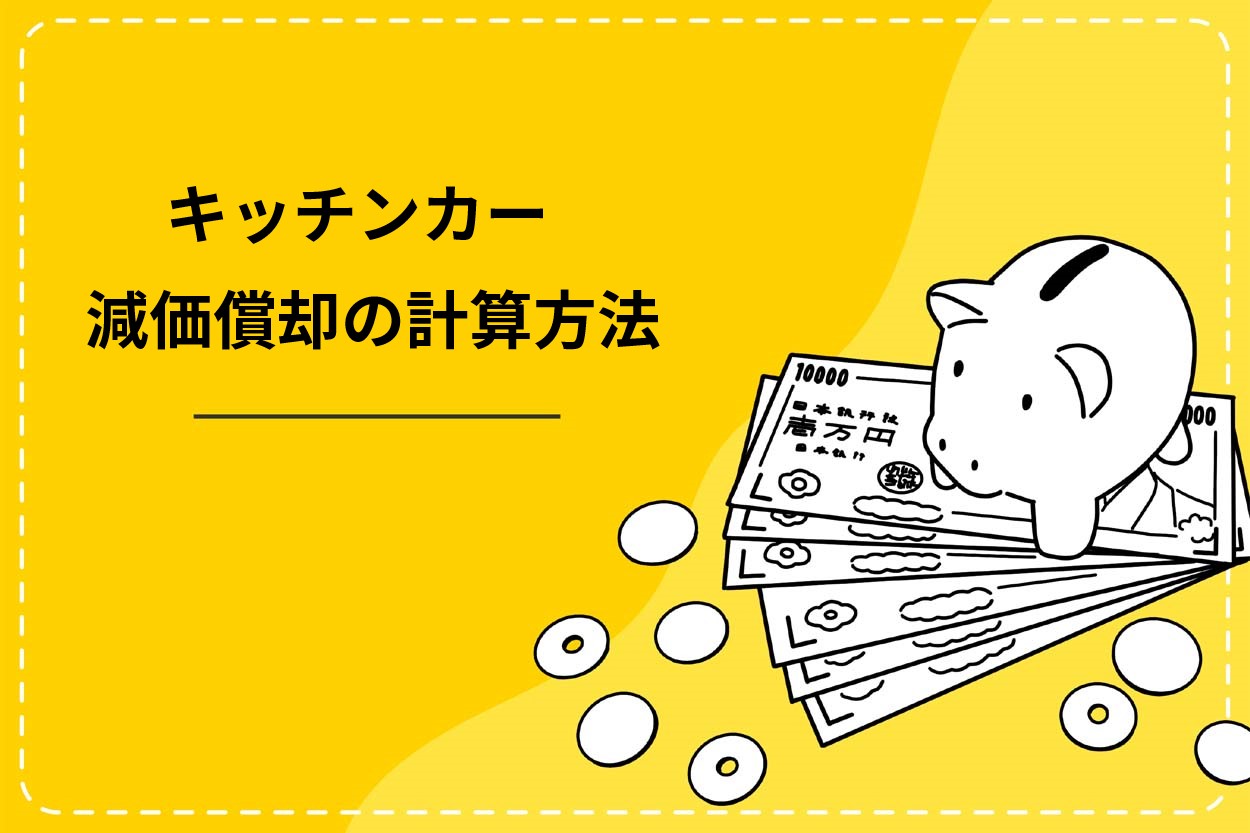
キッチンカーにおける減価償却の計算方法は、以下の2つに分けられます。
- 定額法の場合
- 定率法の場合
具体例を使用し、分かりやすく解説します。
1.定額法の場合
定額法とは、減価償却費が毎年一定額になるよう計算する方法のことです。
個人事業主の場合は、自動的にこの方式が採用されます。
定額法の計算方法は、以下の通りです。
取得原価(購入価格) × 定額法の償却率=1年分の減価償却費
定額法の償却率は、以下の通りです。
| 耐用年数 | 償却率 |
| 2年 | 0.500 |
| 3年 | 0.334 |
| 4年 | 0.250 |
| 5年 | 0.200 |
| 6年 | 0.167 |
参考:国税庁「減価償却資産の償却率等表」
一例として、耐用年数5年、取得原価(購入価格)120万円のキッチンカーで考えてみましょう。
計算式は120万円 × 0.200=24万円となるため、1年間の減価償却費は24万円です。
2.定率法の場合
定率法は、経過年数ごとの償却率を基準に計算する方法です。
法人の場合は、定額法か定率法のどちらかを選択できます。
定率法の計算方法は、以下の通りです。
未償却残高 (年度初めの固定資産の価値)× 定率法の償却率=1年分の減価償却費
定率法の償却率は、以下の通りです。
| 耐用年数 | 償却率 |
| 2年 | 1.000 |
| 3年 | 0.667 |
| 4年 | 0.500 |
| 5年 | 0.400 |
| 6年 | 0.333 |
参考:国税庁「減価償却資産の償却率等表」
一例として、耐用年数5年、120万円で購入したキッチンカーで考えてみましょう。
今回は、1~3年目までの減価償却費を求めます。
- 1年目…120万円×0.400=48万円
- 2年目…(120万円-48万円)×0.4=28万8,000円
- 3年目…(120万円-48万円-28万8,000円)×0.4=17万2,800円
定額法と同じ条件ですが、1年目の減価償却費は2倍になっています。
キッチンカーを購入した年に減価償却費を多めに計上したい場合は、定率法を選びましょう。
キッチンカーの耐用年数・減価償却における2つの注意点

キッチンカーの耐用年数・減価償却費を求める際には、以下の2つに注意しましょう。
- 中古車の改造費は車両価格の50%に抑える
- ローン利用時でも減価償却をする必要がある
これらのポイントを注意しなければ、節税効果が低くなる可能性があります。
キッチンカーを購入しようとしている方は、ぜひチェックしてみてください。
1.中古車の改造費は車両価格の50%に抑える
購入した中古車をキッチンカーに改造する場合は、改造費を車両価格の50%に抑えましょう。
改造費が車両価格の50%を超えている場合は、新車と同様の耐用年数が適応されます。
新車よりも中古車の耐用年数は短いため、1年あたりの減価償却費が多くなりやすいです。
つまり、経費計上できる金額が高くなるため、節税効果が期待できるということです。
なおここでいう車両価格は、中古で購入した金額ではなく、新車時の価格となります。
新車価格が300万円だった場合は、改造費が150万円未満になるようにしましょう。
2.ローン利用時でも減価償却をする必要がある
キッチンカーを購入する場合、ローンを利用しようと考えている方も多いと思います。
ローンを利用する際にも、減価償却行う必要があります。
耐用年数は、本記事中の「キッチンカーの耐用年数を新車・中古車に分けて解説」で紹介した年数が適応されます。
新車の普通車であれば6年、小型車であれば4年といった具体です。
なお、ローンの元金と一緒に支払う利息分については、支払利息として経費計上が可能です。
ただし、ローンの元本返済部分は経費にはできないので注意しましょう。
キッチンカーの耐用年数が気になるならレンタルがおすすめ!4つのメリットを解説
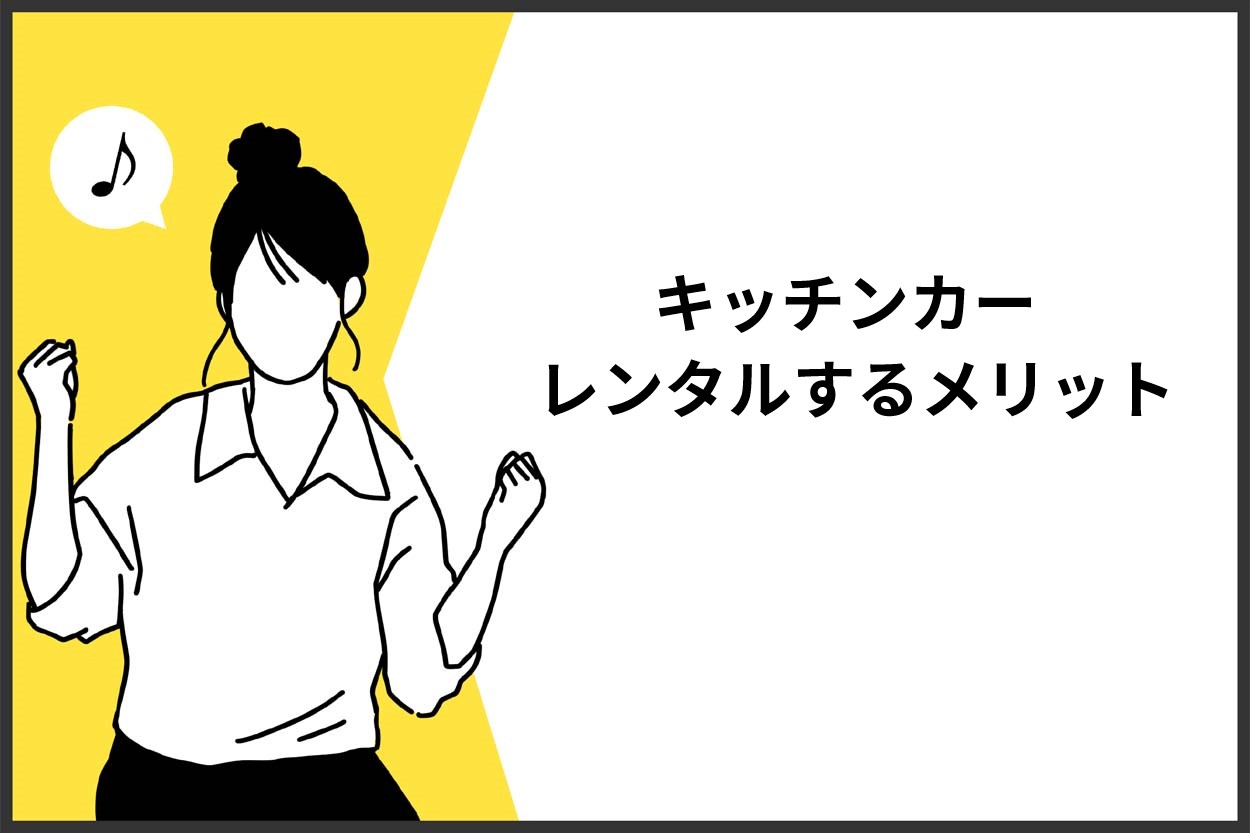
キッチンカーの耐用年や減価償却費を求めるには、計算を行わなければなりません。
日々の業務がある中、わざわざ計算するのはネックだと感じた方もいるのではないでしょうか。
キッチンカーの耐用年数が気になるなら、レンタルするという選択があります。
こちらでは、4つのメリットを解説します。
- レンタル料を経費計上できる
- 初期費用を抑えられる
- 出店までの準備が少ない
- 既にキッチンカーの営業許可が取れている
順番にみていきましょう。
キッチンカーのレンタルについては、関連記事「【業者紹介あり】キッチンカー・移動販売車はレンタル可能!料金の相場や借りるときの注意点を解説」にて詳しく解説しています。
こちらのコラムのぜひチェックしてみてください。
1.レンタル料を経費計上できる
キッチンカーをレンタルする場合、年間で支払った費用はその年の経費として計上できます。
耐用年数や減価償却費を求める必要はありません。
そのため、ややこしい計算をしたり、計算を間違えたりする心配がないのが魅力です。
多少ながら、確定申告時の手間を省けるでしょう。
レンタル料金をそのまま経費計上できるのは、キッチンカーをレンタルするメリットといえます。
2.初期費用を抑えられる
キッチンカーをレンタルするメリットは、初期費用を抑えて移動販売事業を始められることです。
キッチンカーを購入する場合は、200~400万円程度必要です。
一方、レンタルなら最短1日2万円から借りられます。月額であれば20万円~(1日7千円程度)も可能です。
さらに、車検代や駐車場代などの維持費用も必要ありません。
キッチンカーの初期費用や維持費を抑えたいなら、レンタルがおすすめです。
3.出店までの準備が少ない
キッチンカーをレンタルすることで、出店までの準備を少なくできます。
レンタル車両には、水道やガスなどの設備が元から付いているものがほとんどだからです。
自分で1からキッチンカーを用意する際には、製作や営業許可申請の取得などで、数ヶ月の期間を要する場合もあります。
一方、レンタルなら、手続きしてから最短2週間で出店準備を完了できます。
「出店準備の手間を省きたい」と考えている方は、キッチンカーのレンタルを検討してみてください。
4.既にキッチンカーの営業許可が取れている
レンタル業者から借りるキッチンカーは、既に営業許可が取れているものです。
そのため、基準の満たすように改造したり、設備を整えたりする必要がありません。
そもそも移動販売事業を行う場合は、保健所から営業許可が必須です。
許可の条件は各自治体によって異なるため「A県では許可されたキッチンカーが、B県では許可が下りなかった」というケースも珍しくありません。
レンタル車両なら、保健所での営業許可取得に関する手間を省け、地域をまたいだ営業が行いやすくなります。
キッチンカーのレンタルなら「ためしてキッチンカー」にお任せください

キッチンカーをレンタルするなら、弊社が展開する「ためしてキッチンカー」の利用がおすすめです。
一般的には開業の際には約300万円の資金が必要ですが、当サービスであれば半年間のご契約で120万円(毎月20万円)で事業を始められます。
料金の中には、
- 初期装備
- オリジナル塗装
- 保険料
が含まれており、リスクを最小限に抑えられることが特徴です。
キッチンカー事業を始める前の予備知識も丁寧に説明し、開業まで手厚くサポートさせていただきます。
「キッチンカー事業が上手くいくか心配」「費用をできるだけ抑えて開業したい」と考えている方は、ぜひ利用を検討してみてください。
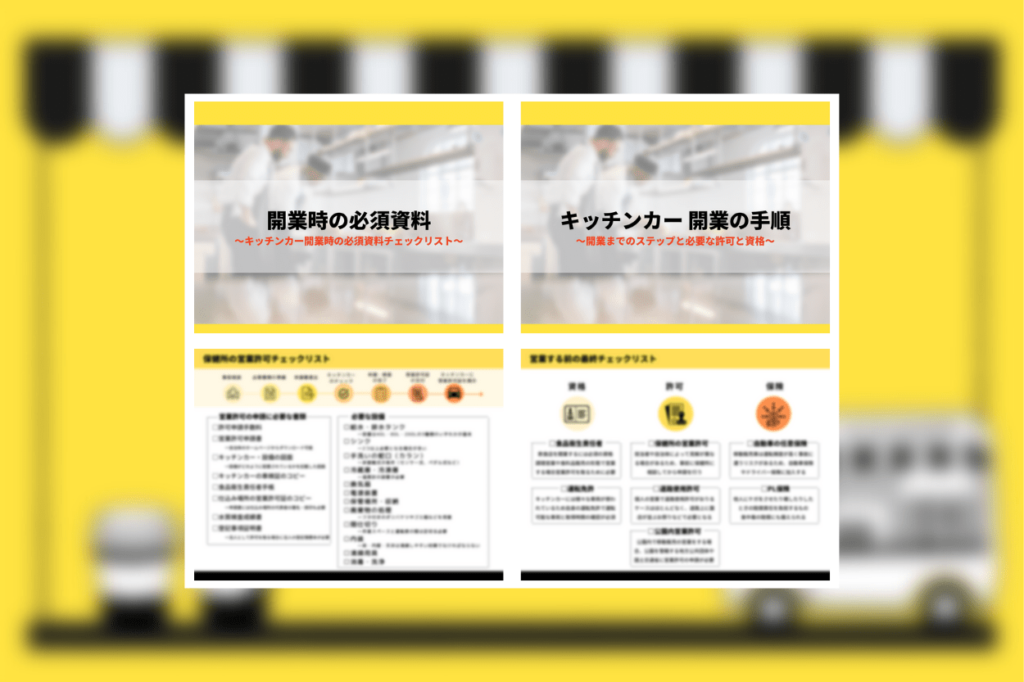 『キッチンカー相談の窓口』では、これからキッチンカーを始めたい人のためにキッチンカー開業の手順・保健所の営業許可&最終チェックリストを「LINE友だち追加」してくれた方全員に無料で配布しております。ぜひご活用ください。
『キッチンカー相談の窓口』では、これからキッチンカーを始めたい人のためにキッチンカー開業の手順・保健所の営業許可&最終チェックリストを「LINE友だち追加」してくれた方全員に無料で配布しております。ぜひご活用ください。