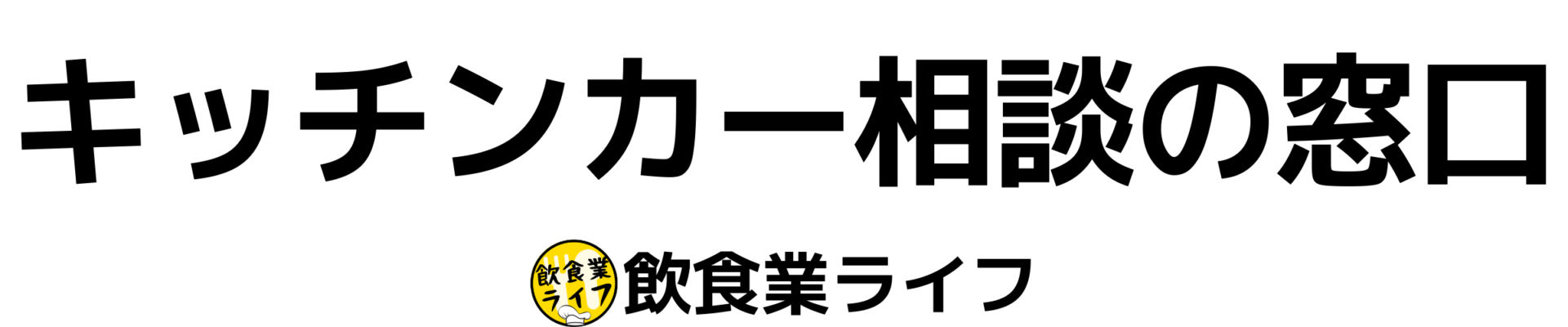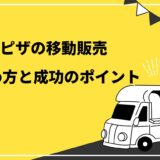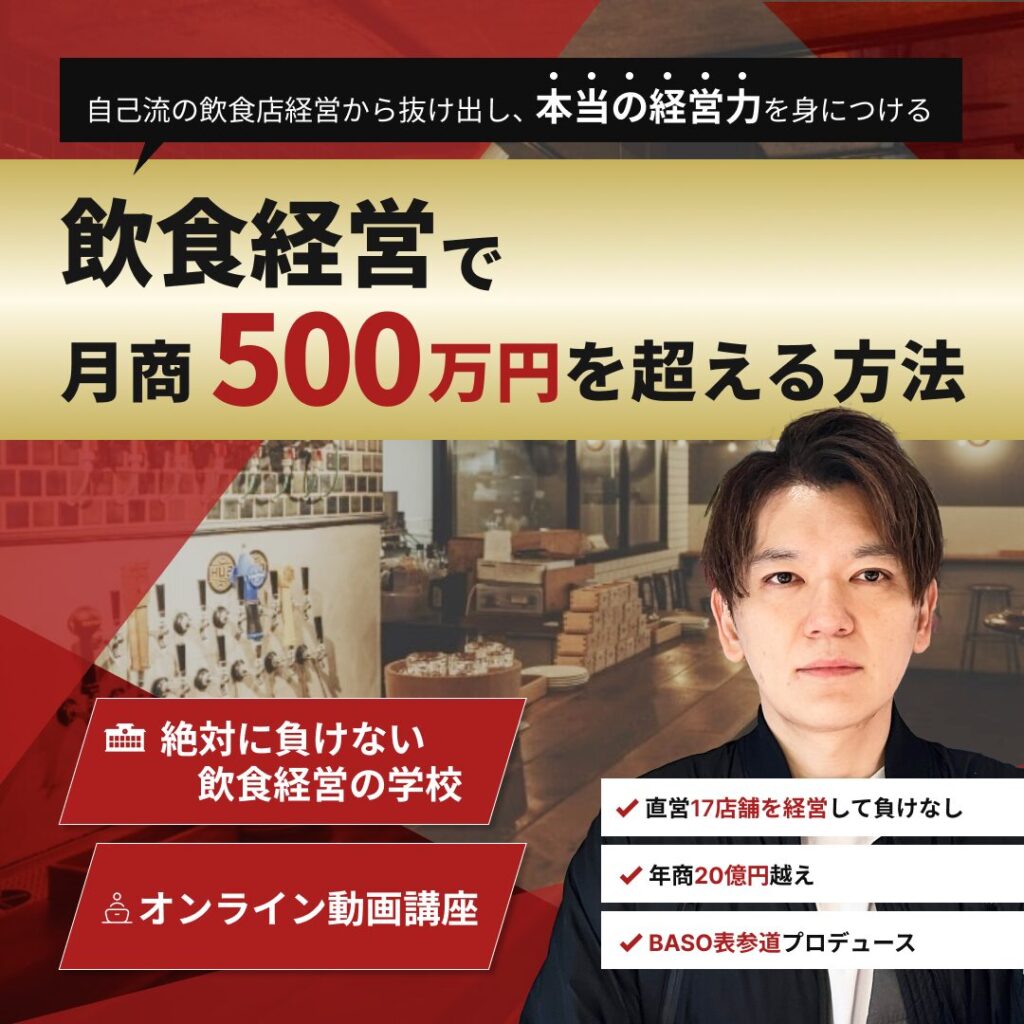「弁当は移動販売で売りやすい?」
「他の商材と比較してどのようなメリットがある?」
「販売に資格は必要?」
などと疑問に思っていませんか?
移動販売の商材で弁当を選べば、ランチタイムを狙って安定的な売上を期待できます。
すでに飲食店を営んでいる方でも、人気のメニューを弁当化することで、移動販売という新たな販路を拡大できるでしょう。
しかしどのように弁当の移動販売を始めれば良いのか、分からないことがあって困っている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、弁当の移動販売を開業する前に知っておきたい、以下の内容を解説していきます。
- 移動販売の方式
- 必要な資格・許可
- 出店場所の候補
- おすすめの弁当
- 注意点
ぜひ当記事を参考にしてみてください!
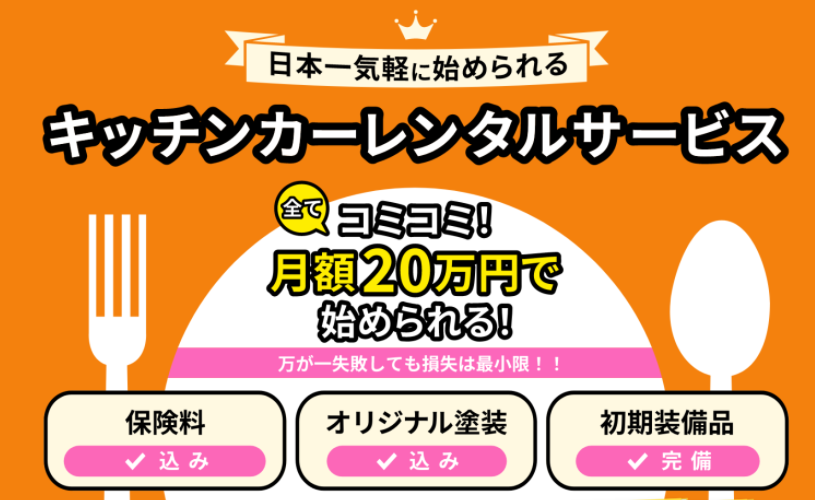 移動販売を始めるなら、キッチンカーレンタルサービスの「ためしてキッチンカー」がおすすめです。
移動販売を始めるなら、キッチンカーレンタルサービスの「ためしてキッチンカー」がおすすめです。
- 半年間の契約で月額20万円
- 開業に失敗しないためのサポート
- 最短納期なら1ヶ月半後にスタート
本記事のリンクには広告を含んでいます。
弁当の移動販売の方式は3パターン

弁当を移動販売で取り扱う方法には、いくつかパターンがあります。
- 弁当を仕入れる
- 弁当をその場で作る
- 別の場所で作った弁当を売る
それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。
準備が必要なものも一緒に紹介するので、ご自身に合った販売スタイルを見つけてみてください。
1.弁当を仕入れる
仕出し弁当を作っている業者から仕入れる方法です。
すでに出来上がった弁当を届けてもらい、販売のステップのみ自分で行います。
インターネットで「弁当 卸売」と検索すると、事業用に弁当を買い付けできる業者がたくさん見つかります。
いくつか業者を比較し、味や見た目に納得のできる弁当を探してみましょう。
1.メリット
業者から仕入れれば、自分で弁当を作るスキルがなくても、ハイクオリティな弁当販売が可能です。販売をスタートしたい時間に合わせて作ってくれるので、極端に冷めてしまう心配はありません。
業者によっては、指定の場所まで弁当を届けてくれるサービスもあります。
弁当作りはせずに販売に集中したい、本格的な移動販売車や仕込み場所を用意する手間を省きたいという方におすすめの方法です。
2.デメリット
業者側が用意したメニューから商材を選ぶことになるので、オリジナル弁当の開発などはできません。
おかずをカスタマイズするには、業者側と交渉する必要があります。場合によっては、弁当のメニューを変えるのに、取引先を見直さなければならないケースもあるでしょう。
また、弁当のでき映えは業者次第です。イメージに合う弁当を作ってくれる業者を探しましょう。
3.準備するもの
弁当を仕入れて移動販売するなら、必要な道具はそれほど多くありません。
主な準備物は以下の通りです。
- 割り箸
- 持ち帰り用の袋
- ブランディングのための包み紙やシール
- 弁当を保管する冷蔵庫・保冷庫
冷蔵庫・保冷庫は、保健所のチェックポイントの対象となる場合があります。
2.弁当をその場で作る
調理設備が整った移動販売車で、弁当を作って販売する方法です。
保健所の許可が下りるよう整備された移動販売車を使います。
丼ものや1品料理など、調理工程が簡単なメニューを選ぶことがポイントです。
1.メリット
できたてほやほやの温かい弁当を提供できます。温かい弁当は美味しさが引き立ち、お客様からの印象が良くなるでしょう。
中には作っているところを見せて、宣伝につなげるスタイルも。イベント会場や公園では、特に注目が集まります。
作る量を上手くコントロールできれば、廃棄率を減らすのにも効果的です。
2.デメリット
移動販売車で作る方法では、接客と調理を同時にこなさなければなりません。集客が上手くいくほどに、オペレーションが難しくなるでしょう。
1人では対応が難しく、スタッフを雇って営業している移動販売車もあります。
また、調理工程によっては別の場所で下ごしらえが必要です。
3.準備するもの
調理設備が整った移動販売車が必須です。
搭載する調理設備の例は次の通り。
- コンロ
- 電子レンジ
- 炊飯器
- 材料や弁当を保管する冷蔵庫・保温庫
- 手洗い・洗浄用シンク
- 給水・排水タンク
設備以外には、包丁やフライパンなどの細かな調理器具が必要です。
容器や割り箸も用意し、弁当を持ち帰れるようにしましょう。
3.別の場所で作った弁当を売る
移動販売車で調理をするのが難しい場合は、事前に別の場所で作ってから売る手法があります。
オリジナルの弁当を作った上で、営業時間中は接客対応に集中できます。
1.メリット
調理設備を車に搭載する必要がありません。移動販売車ではなく普通の車で販売できるので、車両の準備費用を節約できます。
仕込み場所の選び方によっては、本格的な調理スペースで弁当を作れます。
2.デメリット
仕込み場所の用意が必須です。他の方法にはない家賃やレンタル費用で、経費が膨らんでしまいます。
自宅を仕込み場所とする選択肢もありますが、保健所の許可要件を満たすにはハードルが高いです。一般家庭のキッチン設備にはない、防火加工や衛生環境が必要となるためです。
「移動販売なら安く開業できる」と考えていた方には、大きなデメリットとなるでしょう。
3.準備するもの
仕込み場所で使う調理器具や小物を準備しましょう。
自由に使える道具が揃った「シェアキッチン」を活用すると、準備を簡略化できます。
仕込み場所以外には、次のようなものを準備しましょう。
- 弁当の容器
- 割り箸
- 持ち帰り用の袋
- 作った弁当を保管する冷蔵庫か保温庫
仕込み場所以外の準備は、他の方法と大きな違いはありません。
弁当の移動販売で必要な資格・許可

弁当の移動販売では、次の資格・許可を取得しなければなりません。
- 保健所の許可
- 食品衛生責任者
それぞれの取得方法を解説していきます。
1.保健所の許可
保健所から飲食店営業の許可を得ます。
許可がないとそもそも営業ができないので、仕込み場所や移動販売車が要件を満たすように調整しましょう。
申請先は、出店を予定している地域の保健所です。
市町村や都道府県をまたいで移動販売する場合は、それぞれの自治体から許可を取得する必要があります。
注意したいのが、保健所ごとに許可基準の解釈がが変わる可能性があることです。扱う弁当の種類によっても、調理工程の違いで許可の判断基準が異なる場合があります。
不安があれば、出店先の保健所に相談してから、車両や調理設備の準備を進めましょう。
弁当を仕入れして販売のみを行う場合には、許可の対象にはなりません。保健所に営業の届出をすれば販売をスタートできます。
営業許可については、関連記事「【最新版】移動販売(キッチンカー)の営業許可の取り方まとめ。2021年6月の食品衛生法改正もわかりやすく解説!」で、詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
2.食品衛生責任者
食品衛生責任者は、食品の製造や販売をするにあたり必要な資格です。店舗につき1人、資格を持ったスタッフを配置しなければなりません。
食品衛生責任者の資格は、各自治体が開催している衛生講習を受け、保健所に申請することで取得可能です。
講習会のスケジュールや費用は、自治体によって異なります。
例えば東京都なら毎月17回前後開催されていて、費用は12,000円です。
弁当で移動販売をするための出店場所3選

弁当の移動販売で稼ぐなら、出店場所の選定が重要です。
おすすめの出店場所は次の3つです。
- オフィス街
- 学校・学校のそば
- イベント会場
ご自身が考えるターゲットによって、ピッタリな出店場所を探してみてください。
1.オフィス街
オフィス街での移動販売は、弁当との相性が抜群です。
「ランチ難民」を狙って弁当を販売すると、効率的に売上を伸ばせます。
ランチ難民とは、オフィスの周りに飲食店が少なかったり、お店が見つかっても昼時に混雑したりしていて、昼休み中にランチを食べ損ねてしまう人たちのこと。
注文後すぐに手渡せてテイクアウトできる弁当は、ランチ難民の強い味方です。
例えば東京なら次の場所で、ランチ難民をターゲットにしたキッチンカーが出店しています。
- PICNIC GOHAN(中野四季の森公園)
- 常盤橋FOOD TRUCK STREET(東京駅日本橋口前)
- Workstore Tokyo Do ネオ屋台村(首都圏各所)
オフィスビルのすぐそばや、オフィス街にある公園に移動販売車を出店できれば、待っているだけでも弁当が売れるようになるでしょう。
2.学校・学校のそば
学校の敷地内や周辺でも、弁当の移動販売への集客を期待できます。
高校や大学に営業をかけて、敷地内で昼休みに出店します。
営業の手間がかかる分、ライバルの移動販売が少ないため、出店さえできれば学生から人気を集めることが可能です。
大学生であれば、昼時は敷地外に買い物に行けます。たとえ構内で許可を取れなくても、大学の近くで待機していれば学生にたくさん販売できるでしょう。
運動部の学生のお腹を満たすようなガッツリ系メニューの弁当から、女子学生が好むインスタ映えを狙ったカフェ風ランチボックスまで、幅広い戦略で販売できます。
学生でも購入しやすい値段設定が鍵となりますが、学校関係の場所に出店できれば安定した売上を作れます。
ただし長期休みで学生が登校しなくなる時期もあるので、注意が必要です。
3.イベント会場
弁当の移動販売は、イベント会場にも出店できます。
大型イベントでは1度に大量の来客があるので、売上も伸びること間違いなしです。
弁当の移動販売で出店できるイベントの例は、次の通り。
- スポーツイベント
- お花見会場
- 音楽フェス
- グルメイベント
中でもグルメイベントは、移動販売車が主役になれる舞台です。「B級グルメフェス」「肉フェス」のように、テーマに沿った移動販売車が集結して、弁当や軽食を提供します。
毎週末のように各地でイベントが開催されているので、ぜひスケジュールや出店募集の要項を確認しておきましょう。
移動販売で参加できるイベントの例や探し方は「【保存版】大型のキッチンカーイベント5選!探し方や出店料を解説」をぜひチェックしてみてください。
移動販売でおすすめの弁当5選

開業に必要な許可や出店場所の例が分かっても、どのような弁当を売ればいいのか分からないという方も多いでしょう。
そこでこちらでは、移動販売で取り扱うのにおすすめの弁当を6種類紹介していきます。
- 幕の内弁当
- サンドイッチ
- カレー
- ロコモコ丼
- 牛タン丼
- サラダ
自分でもチャレンジしやすそうなメニューがないか、ぜひ確認してみてください。
1.幕の内弁当
幕の内弁当は、ご飯と複数種類のおかずからなる、大定番のメニューです。
古くから親しまれていたり、冠婚葬祭の仕出し弁当でもよく取り扱われていたりして、普遍的な人気を誇っています。
自分で弁当を作る場合は、季節や出店場所によって中身を一部変えられることがメリットです。
「これがないとメニューとして成り立たない!」という特別なおかずがないので、柔軟に中身をカスタマイズできます。
仕出し弁当として扱っている業者も多いです。
2.サンドイッチ
サンドイッチの魅力は、作り方が簡単なことです。具材を用意して挟むだけで、華やかなメニューが完成します。
具材の準備は野菜のカットくらいなので、移動販売車の中でも作業しやすいです。
「ベーコン・レタス・トマト」「ローストビーフ・レタス・トマト」など、具材を部分的に変えるだけでメニューのレパートリーを増やせます。
割り箸がなくても食べられるので、揃えるべき道具も少なくて済むでしょう。
3.カレー
カレーではご飯を盛り付けてルーをかけるだけなので、提供までの手順が簡単です。
事前に仕込みを済ませておけば、注文を受けてから、お客様を待たせることなく弁当を提供できます。
ファミリーレストランでもよく扱っている定番のメニューなので、安定した人気を期待できるでしょう。
さらに「バターチキンカレー」や「キーマカレー」など、スパイス系の本格的なメニューも開発可能です。
4.ロコモコ丼
ロコモコ弁当は、ご飯にハンバーグを乗せたハワイ料理です。
ハンバーグは冷凍や作り置きのものを活用すれば、1から調理する必要はありません。
レタスやトマトのトッピングで彩りを出せるのも嬉しいポイントです。
マラサダやコナコーヒーなどといったハワイ系の軽食も一緒に買ってもらえれば、客単価のアップも期待できます。
5.牛タン丼
焼肉でお馴染みの牛タン(牛の舌部)も、弁当にして移動販売できます。
材料はご飯と牛タンだけで、準備がとてもシンプルなことが特徴です。
ご飯に焼いた牛タンを添えるだけで簡単に提供できます。
イベント会場やサービスエリアなどの日常から離れた場所で販売すれば、少し高めの価格設定でも高級感を演出できるでしょう。
牛タンを商材にした移動販売は「【完全版】牛タンの移動販売の始め方8ステップ!成功するコツと必要な準備も紹介」で詳しく紹介しています。ぜひあわせてご確認ください。
6.サラダ
サラダでは、ダイエット中のOLや健康志向の人にアプローチできます。
野菜を切るだけで下ごしらえができ、加熱なしで簡単に提供できることがメリットです。
野菜のカラフルさで見栄えの良いサラダ弁当ができるでしょう。
弁当の移動販売に関する3つの注意点

移動販売で弁当を取り扱う際は、次の3点に注意してください。
- 食材だけでなくトレイの形状にもこだわる
- 食品表示ラベルを用意する
- 取り扱う商品によってはさらに資格が必要
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.食材だけでなくトレイの形状にもこだわる
弁当の移動販売では、トレイの形状にもこだわることが重要です。
弁当を運ぶ際に、揺れや振動でおかずのレイアウトが乱れることがあります。
乱れによってソースが他のおかずに付いてしまったり、食材が混ざったりすると、弁当の見栄えが悪くなってしまいます。
さらにお客様が弁当を購入して持ち運ぶ間にも、揺れは起きてしまうのでレイアウトが崩れるリスクは高いです。
- 仕切りがあるトレイでおかずを区切る
- 密封性が高い容器で汁もれを防ぐ
など、トレイ選びで弁当が崩れるのを防ぎましょう。
2.食品表示ラベルを用意する
移動販売車で調理してその場で販売する方式以外では、表示ラベルを貼らなければなりません。
表示ラベルに掲載する項目は次の通りです。
- 名称
- 原材料名
- 原料原産地名
- 添加物
- アレルゲン
- 内容量
- 消費期限
- 保存方法
- 製造者名、製造者住所
(引用:静岡市「テイクアウトの弁当・総菜に係る食品表示について(営業者の方向け)」)
中身が見える容器ならおかず類を「おかず」としてまとめて表記してOKです。ただし添加物とアレルゲンの表記は省略できません。
シール用紙に印刷したり、専用のラベルプリンターを導入したりして、表示ラベルを準備しておいてください。
3.取り扱う商品によってはさらに資格が必要
取り扱う商品によっては、追加の販売許可や届出が必要です。
牛乳を使ったメニューや乳飲料などの販売で必要な乳類販売業届出などがあります。
弁当と一緒に飲み物や軽食を販売する予定の方は、条件を調べておきましょう。
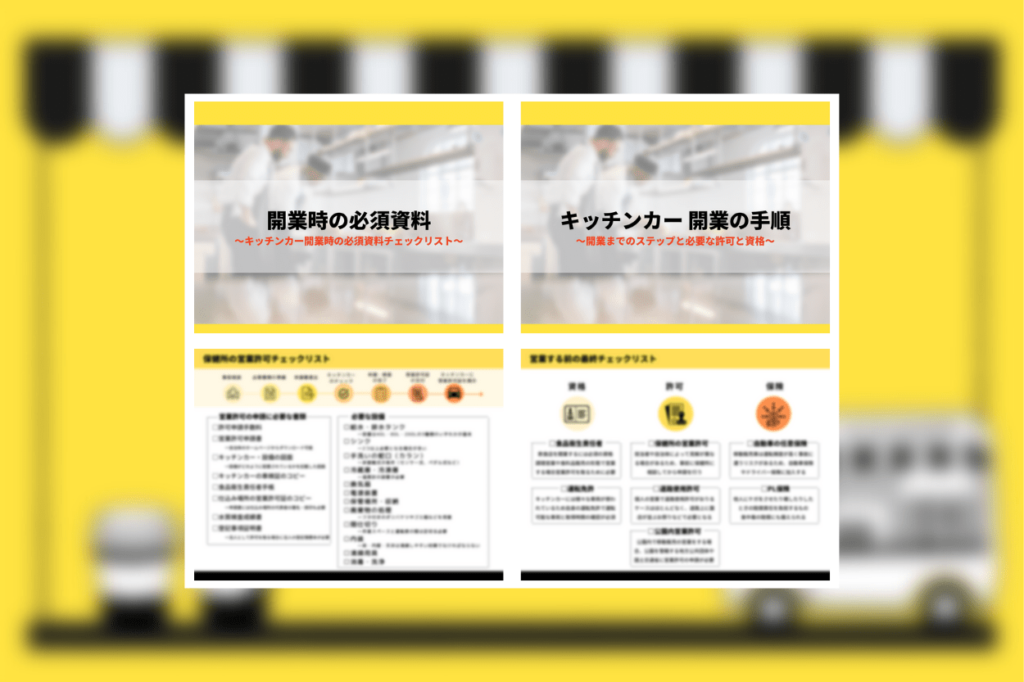 『キッチンカー相談の窓口』では、これからキッチンカーを始めたい人のためにキッチンカー開業の手順・保健所の営業許可&最終チェックリストを「LINE友だち追加」してくれた方全員に無料で配布しております。ぜひご活用ください。
『キッチンカー相談の窓口』では、これからキッチンカーを始めたい人のためにキッチンカー開業の手順・保健所の営業許可&最終チェックリストを「LINE友だち追加」してくれた方全員に無料で配布しております。ぜひご活用ください。