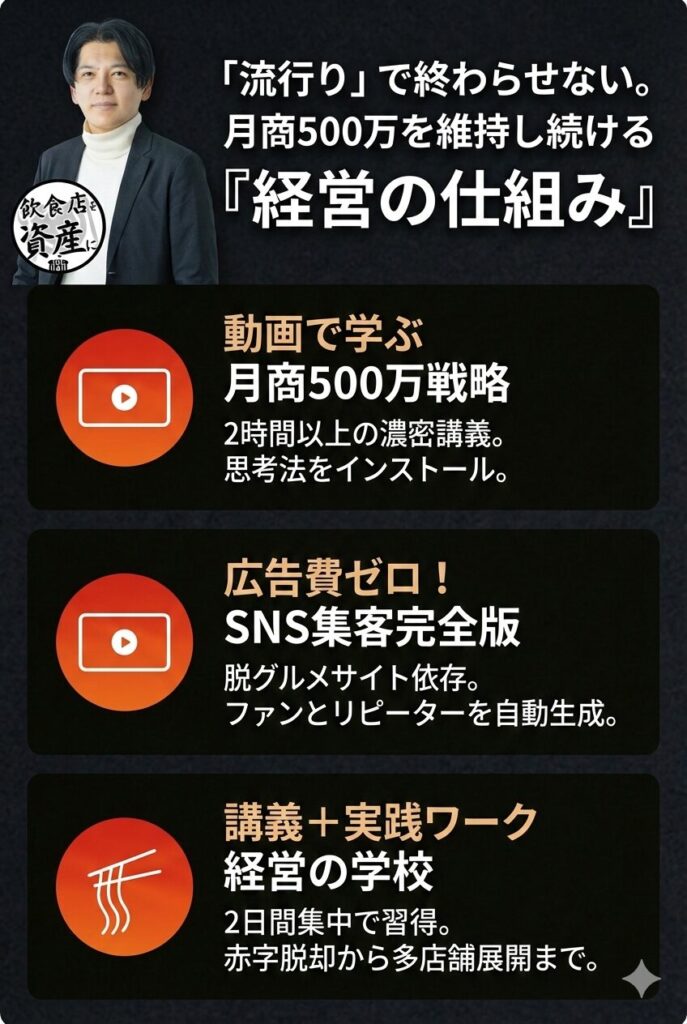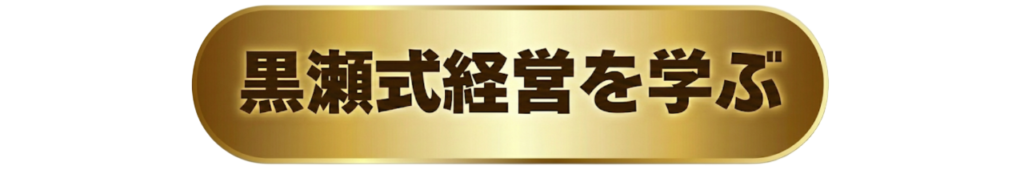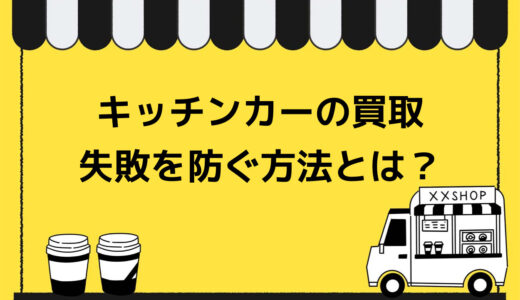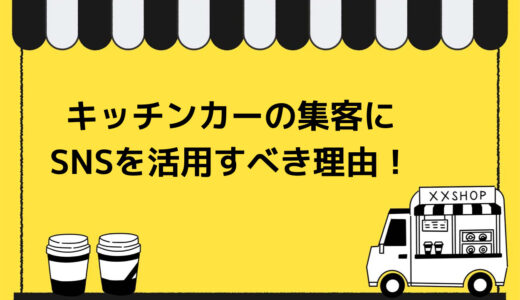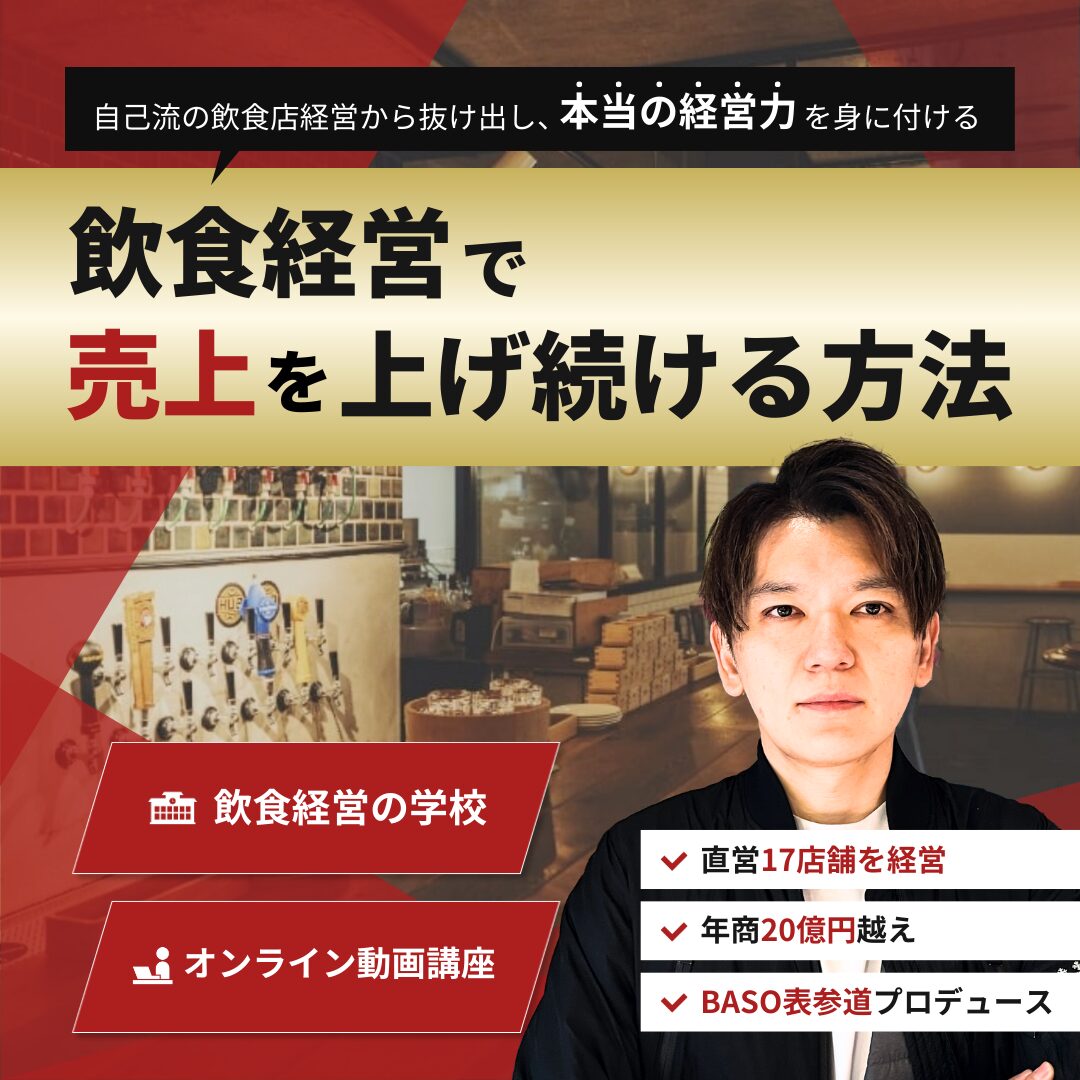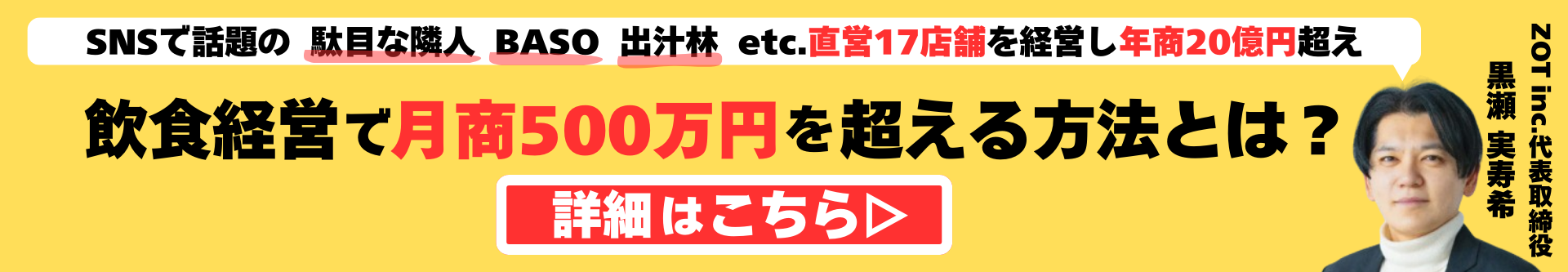【必見】飲食店の食材の仕入先7選!選ぶ手順と失敗しない方法を紹介

「食材の仕入先選びに失敗したくない」
「選択肢が多くて迷う……」
「どうやって仕入先を選べばよいのだろう」
などと考えていませんか?
近年は、インターネットも含めて食品の流通網が発達したことで、仕入先の選択肢が増えています。
便利になった反面「仕入先の選び方が分からない」という方が多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では
- 飲食店の食材の仕入先
- 仕入先選びの手順
- 仕入れに失敗しない方法
について解説します。これから飲食店を始めたいと思っている方だけでなく、すでに始めている方にとっても有益な記事になっています。
ぜひ最後までお読みいただき、自信を持って仕入先を選べるようになってください!
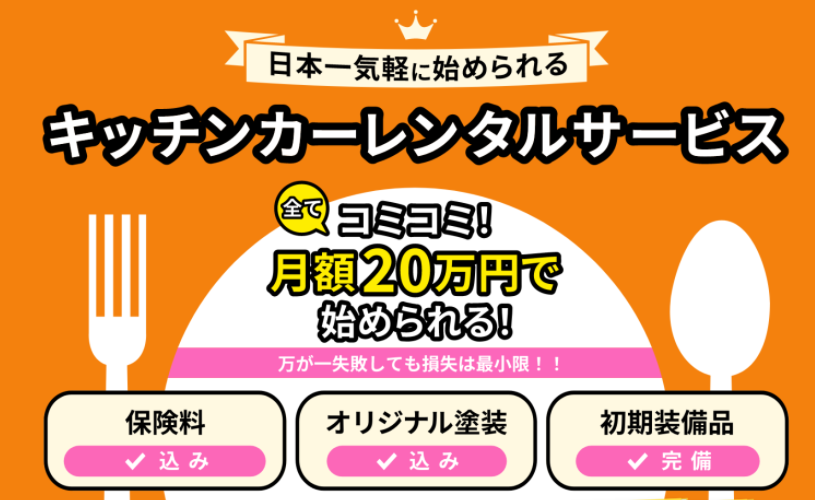 移動販売を始めるなら、キッチンカーレンタルサービスの「ためしてキッチンカー」がおすすめです。
移動販売を始めるなら、キッチンカーレンタルサービスの「ためしてキッチンカー」がおすすめです。
- 半年間の契約で月額20万円
- 開業に失敗しないためのサポート
- 最短納期なら1ヶ月半後にスタート
本記事のリンクには広告を含んでいます。
飲食店の食材の仕入れ先7選

食材の仕入先を決める際、どのような選択肢があるのでしょうか。
ここでは、飲食店の食材の仕入れ先を7つ紹介します。
- 卸売業者
- 小売店
- 業務用専門スーパー
- 市場
- ネット通販
- カタログ通販
- 生産者
それでは、1つずつ解説していきます!
1.卸売業者
卸売業者は、最も多くの飲食店が利用している仕入先です。エリアや顧客ごとに担当者がいて、見積作成や価格交渉などを受け付けてくれます。
卸売業者から仕入れるメリットは、以下の通りです。
- 業界の事情に精通していて、情報を教えてもらえる
- 大量発注するケースなどで価格交渉ができる
- 配送料無料などのサービスが受けられる
一方でデメリットは、以下のようなものです。
- 即日納品などはできない
- 最初の申込みに手間がかかる(口座開設など)
- 担当者によって対応レベルにばらつきがある
卸売業者は担当者と良い関係性が築ければ、より良いサービスが受けられます。
2.小売店
近所のスーパーや肉屋や八百屋などを指します。家庭で使うような食材であれば、すぐに手に入るのが特徴です。
小売店から仕入れるメリットは、以下のようなものがあります。
- 直接手に取って商品を見られること
- すぐに買いに行けること
- 新鮮な食材を入手できること
一方でデメリットは、以下のようなものです。
- 配送サービスがない
- 在庫が限られていて大量購入できない
- 店に行く時間と手間がかかる
- かけ払い(後払い)ができない
小売店は、基本的には一般消費者向けの店舗です。日常的な仕入れで利用するというより、その日に足りなくなった食材を応急的に買いに行くなどの使い方が適しているでしょう。
3.業務用専門スーパー
業務用専門スーパーとは、飲食店などの業者専用のスーパーです。
もともとは業者以外は入店できない店が多かったのですが、最近は一般の方が入れるスーパーが増えています。
生鮮食品により、冷凍食品や常温で消費期限の長い商品を扱っていることが特徴です。
業務用専門スーパーから仕入れるメリットは、以下のようなものがあります。
- 大容量の商品を購入できる
- 割安価格で販売されている
- 実物を見てから購入できる
- 珍しい商品が揃っている
- そのまま持ち帰れる
一方でデメリットは、以下のようなものです。
- 出店エリアが限られており、店の近くにない場合が多い
- 現金払いが主流で、かけ払い(後払い)ができない
- 基本的に配送ができないので、大量仕入れの場合は車が必要
業務用専門スーパーは非常に便利ですが、店舗数があまり多くありません。
遠い場所に何度も足を運ばないようにするためにも、必要な商品はある程度まとめ買いしておくことがおすすめです。
4.市場
「食材の仕入れと言えば市場」というイメージをお持ちの方が、多いのではないでしょうか。
市場といえば豊洲市場(旧築地市場)が有名ですが、どの都道府県にも中央市場があります。
市場から仕入れるメリットは、以下のようなものがあります。
- 鮮度の良い商品が仕入れられる
- 目利きの経験豊富な仲買人が選んだ食材が買える
- 仲買人から貴重な情報が得られる
- なかなか流通していない食材が揃っている
- 割安に仕入れられる
一方でデメリットは、以下のようなものです。
- 市場独自のルールがあり敷居が高い
- 非常に朝が早い
- 週に2日程度の休場日がある
食材の鮮度や品質にこだわる方は、市場で仕入れることをおすすめします。「市場で仕入れる」ことは、お客様に対しても大いにアピールできるポイントだからです。
5.ネット通販
インターネットの普及により、食材の仕入れもネット上で完結するようになりました。
ネット通販で仕入れるメリットは、以下のようなものがあります。
- いつでもどこでも注文できる
- 選べるメニューの幅が広い
- 小ロットでも発注可能
- 送料無料のサービスが多い
一方でデメリットは、以下のようなものです。
- 即日入荷はできない
- 直接商品を見られない
- 担当者がいないので融通がきかない
ネット通販の進歩はめざましく、多くの業者が参入してきています。
実店舗よりも安い価格で販売されている商品も多いので、納期と照らし合わせてバランスよく利用していきましょう。
6.カタログ通販
カタログで仕入れる食材を選んで、電話やFAXで注文する方法です。長年飲食店を営んでいる方にとっては、馴染みのある仕入れ方法なのではないでしょうか。
カタログ通販で仕入れるメリットは、以下のようなものがあります。
- 幅広い商品ラインナップが一覧できる
- 慣れている人にとっては探しやすい
- わからないことはコールセンターに質問できる
- PCやスマホ操作が苦手な人でも利用できる
一方でデメリットは、以下のようなものです。
- タイムリーな情報更新ができない
- カタログを保管するスペースが必要
- 割引商品がない
- 値下げ交渉がしにくい
カタログはメーカーに問い合わせるか、食品展示会に足を運ぶことで入手できます。
ネット通販を利用する方が増えていますが、カタログもいまだに根強い人気があります。
7.生産者
近年は、生産者と飲食店を直接結びつけるサービスが発達しています。野菜や魚、肉などを生産者から直接仕入れる方が増えています。
生産者から直接仕入れるメリットは、以下のようなものです。
- 中間マージンが省ける
- 生産者の顔が見える
- 高品質な食材が手に入る
一方でデメリットは、以下のようなものがあります。
- 仕入量の急な変更に対応しづらい
- 仕入コストが高くなる
- 生産者と直接コンタクトを取るので一定の手間がかかる
「生産者から直接仕入れていること」は、それだけでお店のイメージ向上に繋がります。
ただし全ての食材を生産者から仕入れるとコストが上がってしまうので、お店の目玉となるメニューなどに活用することがおすすめです。
食材の仕入先選び5ステップ

たくさんある仕入先から「どうやって選べば良いか分からない」という方が、多いのではないでしょうか。ここでは、食材の仕入先選びを5つのステップで解説します。
- 店のコンセプトを明確にする
- メニューを決める
- 仕入先の得意分野を見極める
- 原価を計算する
- 品質をチェックする
それでは、解説していきましょう!
1.店のコンセプトを明確にする
最初に、どのようなお店にしたいかを決めます。お店のコンセプトを決めることで、メニューや仕入先を決める基準となるでしょう。
例えば、以下のようなコンセプトが考えられます。
- オーガニック食材にこだわって、健康志向の人に来てほしい
- おしゃれなテラス席を作って、流行に敏感な人に来てほしい
- ボリューム重視のメニューで、若い学生などに来てほしい
実際に色々な飲食店に足を運んで、目標とするようなお店をベンチマークとするのもおすすめです。
食材の仕入先を決めるためには、まずお店のコンセプトを明確にしましょう。
2.メニューを決める
お店のコンセプトが明確になったら、提供するメニューを決めます。メニューを決めて必要な食材を洗い出すことで、自然と仕入先の目処が立ってきます。
メニューがなかなか決まらないという方は、同じようなコンセプトのお店を参考にするのも良いでしょう。どうせ参考にするなら、繁盛しているお店がおすすめです。
お店によって「採算度外視の集客用メニュー」や「利益が出やすいメニュー」などを設定しているはずです。他のお店を研究することは、自分のお店のメニューを決めるのに大いに役立ちます。
お店にとってメニューは最も大事な要素のひとつなので、しっかりと考えて決めましょう。
3.仕入先の得意分野を見極める
いよいよ、仕入先を決めていく段階に入ります。数ある仕入先の得意分野を見極めて、自分のお店のコンセプトとマッチングさせましょう。
仕入先を見比べて「生鮮食品の品揃えが多い」「納品が早い」などの観点でチェックします。自分のお店にとって、優先順位の高い得意分野をもっている仕入先を見つけましょう。
例えば、以下のように分類していきます。
- 食材の鮮度や品質を売りにしたい:生産者・市場
- 多彩なメニューを揃えたい:卸売業者・ネット通販
- 季節によって食材を切り替えたい:カタログ通販・ネット通販
- その日の注文によって食材を補充したい:小売店・業務用専門スーパー
得意分野を見極めて、自分の店で採用する仕入先を絞っていきましょう。
4.原価を計算する
候補となる仕入先が見つかったら、値段をチェックしましょう。いくら使い勝手が良くて高品質な食材を納品する仕入先でも、予算をオーバーしていたら使えません。
飲食店において売上に占める原価の割合を示す「原価率」という指標があります。原価率は以下の計算で求められます。
原価 ÷ 売上 × 100=原価率(%)
一般的に、飲食店の原価率は30%が目安と言われています。あくまで目安ですが、仕入先を選ぶ際は原価率が30%を大きく超えないように注意しましょう。
5.品質をチェックする
当然ですが、食材の品質は大変重要です。仕入先の値段やサービスだけでなく、食材の「品質=味」は必ずチェックしましょう。
仕入先がお店の近くであれば、実際に購入して確認することをおすすめします。
たとえ店舗形式の仕入先でなくても、サンプルなどを取り寄せることも可能です。
お店のコンセプトによって優先順位が異なりますが、味が悪くてお店が繁盛することはないでしょう。仕入先を決定する際は、品質のチェックを行ってください。
食材の仕入れに失敗しない方法は「組み合わせ」
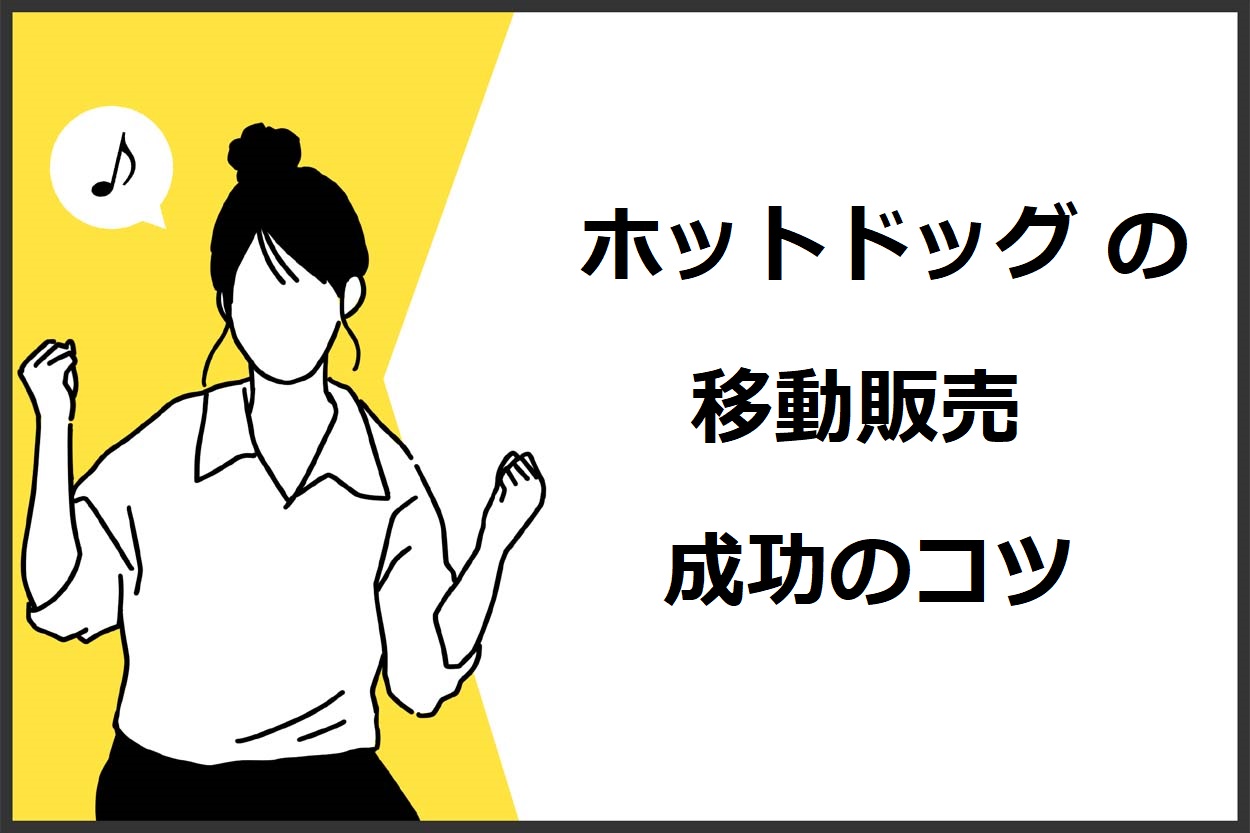
実は、食材の仕入れに失敗しない方法があります。それは、複数の仕入先を組み合わせることです。
複数の仕入先を併用することで、品切れなどのリスクが分散されます。
例えばメインの仕入先が通販である場合、サブを近隣のスーパーなどにしておけば、急に必要になった食材などを買いに行けるでしょう。
他にも、メインで使う肉・魚や野菜は市場や生産者から、他の食材は卸売業者から仕入れるなどの使い分けも考えられます。
各仕入先の得意分野を組み合わせて、自分のお店にとって効率的な組み合わせを見つけると、食材の仕入れに失敗する可能性が減らせます。
移動販売では食材の仕入れ先選びが重要

移動販売では、メニューや予算の中から最もコストパフォーマンスが良い仕入先を見つけることが重要です。
各仕入先の特徴や得意分野を理解して、お店のコンセプトに合致する組み合わせを考えてみましょう。
そして原価率を考慮して、しっかりと利益が出る食材を仕入れることがお店の成功に繋がります。
それでも「なかなかベストな仕入先が決められない」という方は、専門家の意見を聞くという手段も有効です。
もしこれから移動販売を始めたいと考えているなら「キッチンカー相談の窓口」にご連絡ください。
仕入先のご検討から開業のお手伝いまで、お気軽にご相談頂けます。まだ検討段階という方でも、ぜひお気軽にご相談ください。
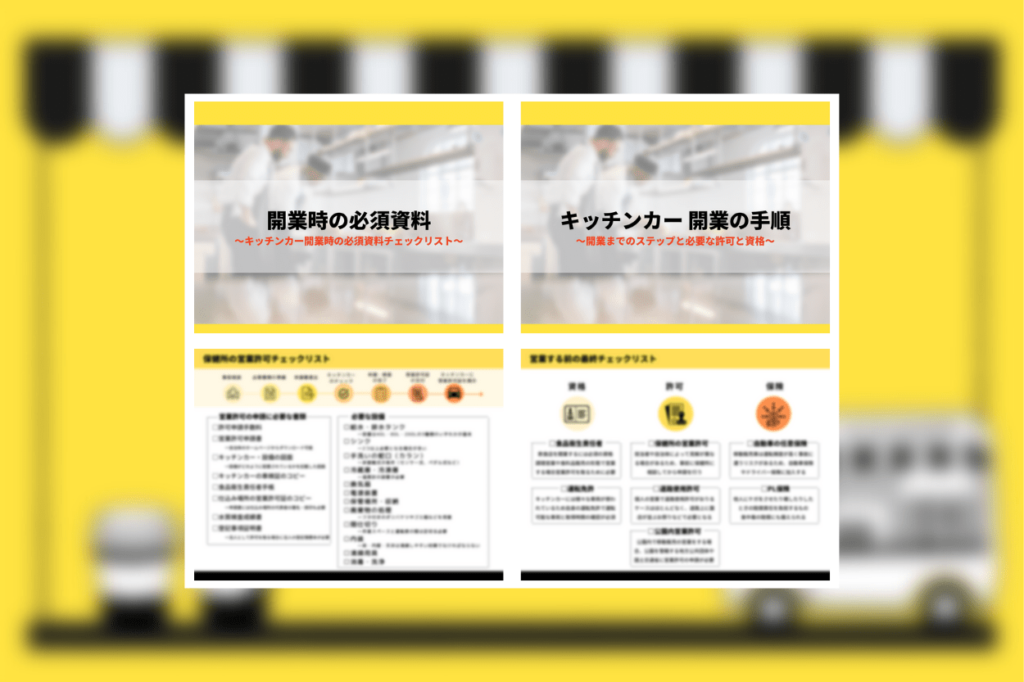 『キッチンカー相談の窓口』では、これからキッチンカーを始めたい人のためにキッチンカー開業の手順・保健所の営業許可&最終チェックリストを「LINE友だち追加」してくれた方全員に無料で配布しております。ぜひご活用ください。
『キッチンカー相談の窓口』では、これからキッチンカーを始めたい人のためにキッチンカー開業の手順・保健所の営業許可&最終チェックリストを「LINE友だち追加」してくれた方全員に無料で配布しております。ぜひご活用ください。